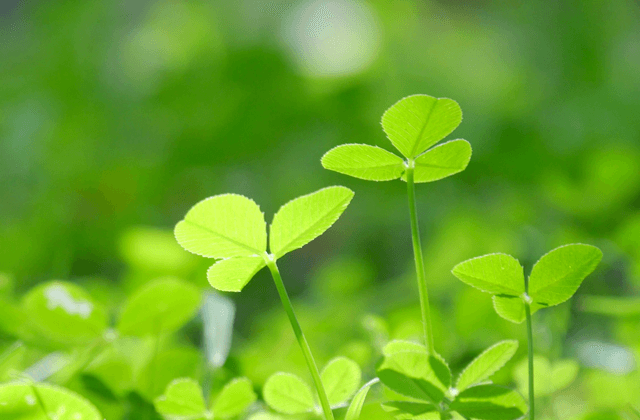
人を殺してはいけない理由を説明できますか?
皆さんは、たとえば自分のお子さん、あるいは知り合いのお子さんから「なぜ、人を殺してはいけないの?」という質問をされたことがありますか。唐突にこう質問されると実際にどう答えていいか、迷ってしまいますよね。
ではなぜこの質問を最初にあげたのかというと、この質問を入口に「道徳と多様性は両立するか」という超難問にチャレンジしている、東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻教授・鄭雄一氏の取り組みを紹介したかったからです。
鄭氏は、多種多様な価値観がうずまくグローバリゼーション時代の今だからこそ、道徳を根本から見つめ直す必要があると考え、道徳と多様性の両立について疑問点の検出と分析という形で科学的アプローチを試みました。
神とか国の権力者とか、とにかく社会を支配する権威ある存在が、社会を守るために「殺人はいけない。戦争、死刑は社会を守る行為だから許される」と決めたという考え方と、「死にたくないから自分も皆も殺人はいけないと考える。でも、自分が殺されないためには戦争や死刑は認める」という考え方があるのです。
鄭氏は三つの疑問が見出した道徳的矛盾を「道徳の空白」と言います。世はグローバリゼーションの時代、あらゆる境界は消えつつあると言われながら、世界を貫く道徳体系はいまだ存在しないということなのですね。
一つ目の道徳モデルは社会に重点を置くもの。宗教とか伝統、習慣に基づく「理想の社会」という枠組みがあり、そのなかで決まった道徳があるというモデルです。「○○しなければいけない」「○○してはいけない」がはっきりと決まっていて、それを守ってさえいれば社会は非常に安定します。ただし、与えられた特定の枠組みからはみ出すことは決して許されず、まるごと受け入れる必要があります。鄭氏はこれを「社会を神格化」と定義します。
これに対立するのが個人に重点を置く道徳モデルです。鄭氏によれば、それは17世紀のフランスの哲学者デカルト以前と以降で様相が異なるとのことなのですが、いずれにしても「道徳は個人個人が決めるもの」という考え方であることに変わりありません。個人と社会を切り離し、しかも社会より個人を上位に位置づけるというのが特徴です。特にデカルト以降は、主役は「自由で理性を有する個人」となりました。「個人の神格化」です。
個人に重点を置くモデルは、「道徳は個人が決める」と考えますから、それぞれの理性を重んじ、とても自由です。それだけに、具体的な道徳律、「○○をしてはいけない、○○をするべきだ」といったものがなく、まとまり、決定力に欠ける。紛争が起こってもただ傍観するだけになってしまいます。
つまり、社会重点モデルは多様性を担保できず、個人重点モデルは道徳性を担保できないということになり、「道徳と多様性は両立できない」という分析結果が導き出されるのです。
ではなぜこの質問を最初にあげたのかというと、この質問を入口に「道徳と多様性は両立するか」という超難問にチャレンジしている、東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻教授・鄭雄一氏の取り組みを紹介したかったからです。
鄭氏は、多種多様な価値観がうずまくグローバリゼーション時代の今だからこそ、道徳を根本から見つめ直す必要があると考え、道徳と多様性の両立について疑問点の検出と分析という形で科学的アプローチを試みました。
「殺人」を例に道徳の未解決問題を考える
鄭氏はまず、既存の道徳の未解決問題を考えるために「殺人」を例にとり、「なぜ、殺人はいけないのか」と「なぜ、戦争や死刑では殺人が許容されるのか」という二つの疑問から考え始めました。これらの問題の答えはいずれも大きく二種類のタイプに分かれます。それは、「社会」を理由の中心におくものと「個人」を理由にするものです。神とか国の権力者とか、とにかく社会を支配する権威ある存在が、社会を守るために「殺人はいけない。戦争、死刑は社会を守る行為だから許される」と決めたという考え方と、「死にたくないから自分も皆も殺人はいけないと考える。でも、自分が殺されないためには戦争や死刑は認める」という考え方があるのです。
突き詰めると「道徳の空白」にたどり着く
しかし、そもそも殺人を禁じていない社会など現代の社会にはないわけですから、「許容される殺人=戦争や死刑」ということ自体が大きな矛盾をはらんでいることとなり、さらに「では、人類全体に共通する道徳原理はないのか」という第三の疑問が生じます。人を殺してはいけないのは自明のことですが、戦争や死刑が許容される理由をきちんと説明できないと、「殺人はいい場合も悪い場合もある」とか「時と場所が変われば、善悪の区別、道徳観も変わる」ということになってしまいます。鄭氏は三つの疑問が見出した道徳的矛盾を「道徳の空白」と言います。世はグローバリゼーションの時代、あらゆる境界は消えつつあると言われながら、世界を貫く道徳体系はいまだ存在しないということなのですね。
過去の道徳モデルを分析する
「空白」という既存の道徳の問題点が分かったところで、鄭氏がとった次のアプローチは過去の道徳思想、道徳モデルの分析なのですが、どうやらここでも「社会」と「個人」をキーワードにすると整理がしやすそうです。一つ目の道徳モデルは社会に重点を置くもの。宗教とか伝統、習慣に基づく「理想の社会」という枠組みがあり、そのなかで決まった道徳があるというモデルです。「○○しなければいけない」「○○してはいけない」がはっきりと決まっていて、それを守ってさえいれば社会は非常に安定します。ただし、与えられた特定の枠組みからはみ出すことは決して許されず、まるごと受け入れる必要があります。鄭氏はこれを「社会を神格化」と定義します。
これに対立するのが個人に重点を置く道徳モデルです。鄭氏によれば、それは17世紀のフランスの哲学者デカルト以前と以降で様相が異なるとのことなのですが、いずれにしても「道徳は個人個人が決めるもの」という考え方であることに変わりありません。個人と社会を切り離し、しかも社会より個人を上位に位置づけるというのが特徴です。特にデカルト以降は、主役は「自由で理性を有する個人」となりました。「個人の神格化」です。
導きだされた結論は「道徳と多様性は両立しない」
こうして、過去の道徳モデルを比較してみるとそれぞれの特徴も欠点もはっきりと見えてきます。社会に重点を置くモデルは理想の社会の枠組みが明確で安定している、迷いがない。しかし、異なる枠組みをもつ社会と衝突すると紛争を引き起こしかねないということになります。個人に重点を置くモデルは、「道徳は個人が決める」と考えますから、それぞれの理性を重んじ、とても自由です。それだけに、具体的な道徳律、「○○をしてはいけない、○○をするべきだ」といったものがなく、まとまり、決定力に欠ける。紛争が起こってもただ傍観するだけになってしまいます。
つまり、社会重点モデルは多様性を担保できず、個人重点モデルは道徳性を担保できないということになり、「道徳と多様性は両立できない」という分析結果が導き出されるのです。
グローバリゼーションのなかで私たちに求められること
たしかに、道徳と多様性の両立は難しい問題かもしれません。しかし世界では、科学技術をはじめ、さまざまな分野でボーダレス化、グローバリゼーションが進み、私たちが今後異なる価値観、道徳に接する機会はますます増えていくはずです。少なくとも「自分の当たり前が相手の当たり前」という先入観を捨てること、自分個人や自分が属する社会の道徳が世界共通ではないと認識することが、私たちに最低限必要なことなのではないでしょうか。人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部







