テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
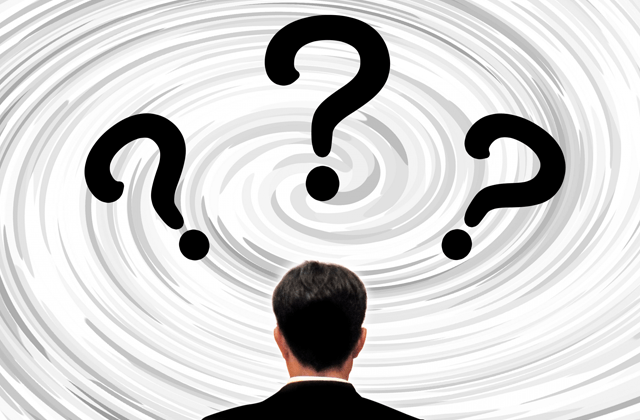
ニュースで話題の「忖度」ってどういう意味?
昨今、世間を騒がせている「森友学園問題」。本来なすべき議論をそっちのけで、メディアでも国会でも取り上げられ続けました。そんな旬のニュース場面で、「忖度」という言葉がにわかに注目を集めています。
「森友学園問題」では、官僚が総理夫人の「意向を推しはかった」という意味で「忖度」が使われています。海外メディアへの会見で、「忖度」の適切な訳し方に困惑し、一時通訳が止まるという事態もニュースになりました。
問題の取り扱われ方からも、何だか悪い言葉のように感じますが、本来「忖度」という言葉は、「“上役”の意向を推し量る」という意味ではないということをご存じでしょうか? 今回は「忖度」をはじめ、本来の意図とは違う意味で使われている言葉をご紹介します。
「上役の意図を推し量る」という場面で頻繁に使われるようになったのは2000年代に入ってからといわれます。今回ニュースの話題になるくらいですから、決して目にする頻度は多くはありませんでした。しかし、「忖度」は着々と、政治の場や上下関係の上に成り立つ、「上役への気遣い」というニュアンスが強くなっています。
・「潮時」
例えば「潮時」という言葉は、本来「物事をはじめたり終えたりするのに、適当な時機」、つまりポジティブな意味での好機ということで、はじまりにも、終わりにも使える言葉です。しかし、多くの人が「終わり」を意図する言葉として使っています。実際に2012年に文化庁が行った調査では、「ものごとの終わり」で使う人が36.1%という結果が出ました。「終わり」というニュアンスから、どことなくネガティブな印象を受ける人もいるかもしれません。
・「なし崩し」
なぜかマイナスで使われるようになった言葉に「なし崩し」があります。「仕事をなし崩しに進めて行く」というと、「そんな仕事の仕方で大丈夫?」と思いませんか? 実は、「なし崩し」の本来の意味は「物事を少しずつかたづけていくこと」。着々と進んでいるという意味で、投げやりにとりあえず済ませていくということではないのです。
・「敷居が高い」
レストランやお店などに「高級すぎたり、上品すぎて入りづらい」という意味で使う方は多いと思います。しかし、本来は「不義理や面目のないことがあって、その人の家へ行きにくい」という意味です。いずれも入りづらい、行きづらいという意味ですが、元々は後ろめたさのある言葉なんです。
・「煮詰まる」
答えが出ない、問題が解決しないときに「煮詰まった」と表現することがありますが、実はこれも本来の使い方ではありません。正しくは「結論が出る段階に近づく」こと。まるで逆の使い方です。
・「気がおけない」
誤用の代表例のような形で紹介されますが、「遠慮したり気をつかったりする必要がなく、心から打ち解けることができる」ことを指します。「ない」という言葉がネガティブに感じるためか、逆の場面で利用したり、「気がおける」など本来はない言葉が生まれたりもしています。
しかし、確かに言葉を正しく使うということは大切ですが、その一方で言葉は時代によって変化するものです。誤用でも使う人が多くなれば、辞書の内容も改訂され、誤用も正しい言葉となり、時には新しい言葉として認められるようになります。
大切なのは言葉はお互いの思いを伝えるためのツールだということです。プラスの意味で言ったつもりが、マイナスの言葉として受け取られたり、時にはその逆もあるでしょう。きちんと相手の意図を理解し、感情をくみ取ること、それこそ正しい意味での「忖度」が役に立つかもしれませんね。
「森友学園問題」では、官僚が総理夫人の「意向を推しはかった」という意味で「忖度」が使われています。海外メディアへの会見で、「忖度」の適切な訳し方に困惑し、一時通訳が止まるという事態もニュースになりました。
問題の取り扱われ方からも、何だか悪い言葉のように感じますが、本来「忖度」という言葉は、「“上役”の意向を推し量る」という意味ではないということをご存じでしょうか? 今回は「忖度」をはじめ、本来の意図とは違う意味で使われている言葉をご紹介します。
「忖度」についてしまったネガティブなイメージ
「忖度」は本来、「心を推測する」、「他人の気持ちを推し量る」という意味です。もちろん、相手の気持ちを察するという点において、今回のような「上役の意図を推し量る」という使い方もあるでしょう。無言のうちに空気を読むということと、近いニュアンスがあるかもしれません。しかし、決してそれだけの意味ではなく、相手の気持ちを想像し慮るという意味もあるのです。「上役の意図を推し量る」という場面で頻繁に使われるようになったのは2000年代に入ってからといわれます。今回ニュースの話題になるくらいですから、決して目にする頻度は多くはありませんでした。しかし、「忖度」は着々と、政治の場や上下関係の上に成り立つ、「上役への気遣い」というニュアンスが強くなっています。
誤用の多い言葉たち
「忖度」のように、本来の意味の一面がピックアップされたり、ニュアンスが変わってしまっている言葉はたくさんあります。・「潮時」
例えば「潮時」という言葉は、本来「物事をはじめたり終えたりするのに、適当な時機」、つまりポジティブな意味での好機ということで、はじまりにも、終わりにも使える言葉です。しかし、多くの人が「終わり」を意図する言葉として使っています。実際に2012年に文化庁が行った調査では、「ものごとの終わり」で使う人が36.1%という結果が出ました。「終わり」というニュアンスから、どことなくネガティブな印象を受ける人もいるかもしれません。
・「なし崩し」
なぜかマイナスで使われるようになった言葉に「なし崩し」があります。「仕事をなし崩しに進めて行く」というと、「そんな仕事の仕方で大丈夫?」と思いませんか? 実は、「なし崩し」の本来の意味は「物事を少しずつかたづけていくこと」。着々と進んでいるという意味で、投げやりにとりあえず済ませていくということではないのです。
・「敷居が高い」
レストランやお店などに「高級すぎたり、上品すぎて入りづらい」という意味で使う方は多いと思います。しかし、本来は「不義理や面目のないことがあって、その人の家へ行きにくい」という意味です。いずれも入りづらい、行きづらいという意味ですが、元々は後ろめたさのある言葉なんです。
・「煮詰まる」
答えが出ない、問題が解決しないときに「煮詰まった」と表現することがありますが、実はこれも本来の使い方ではありません。正しくは「結論が出る段階に近づく」こと。まるで逆の使い方です。
・「気がおけない」
誤用の代表例のような形で紹介されますが、「遠慮したり気をつかったりする必要がなく、心から打ち解けることができる」ことを指します。「ない」という言葉がネガティブに感じるためか、逆の場面で利用したり、「気がおける」など本来はない言葉が生まれたりもしています。
時代によって言葉は変化する
いかがでしたでしょうか? 調べてみると誤用が多い言葉はまだまだあります。しかし、確かに言葉を正しく使うということは大切ですが、その一方で言葉は時代によって変化するものです。誤用でも使う人が多くなれば、辞書の内容も改訂され、誤用も正しい言葉となり、時には新しい言葉として認められるようになります。
大切なのは言葉はお互いの思いを伝えるためのツールだということです。プラスの意味で言ったつもりが、マイナスの言葉として受け取られたり、時にはその逆もあるでしょう。きちんと相手の意図を理解し、感情をくみ取ること、それこそ正しい意味での「忖度」が役に立つかもしれませんね。
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部
歴史作家・中村彰彦先生に学ぶ歴史の探り方、活かし方
テンミニッツ・アカデミー編集部
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










