テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
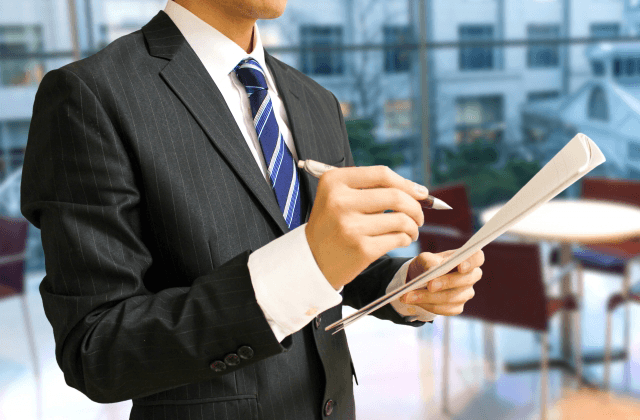
企業が取るべき最初の選択は「場」か「資源」か?
自分の会社がいつまでも繁栄してほしいと願わない経営者はいません。そのための「意思選択」のあり方を研究するのが「経営戦略論」です。なかでも有名なのが、「ポーターVSバーニー」論争。企業が取るべき最初の選択を「場(業界)」であるとしたのがマイケル・ポーターのポジショニング・アプローチ論、「VRINを満たす経営資源の保有」だとしたのがジェイ・バーニーの資源ベース論です。制度・組織経済学を専門とする慶應義塾大学商学部教授の谷口和弘氏は、対立するこの二つを「別々のメガネ(フレームワーク)」として紹介しています。
彼は、企業の戦略をダーウィンの「進化論」のようなものだと言ってのけました。最初から答えが見える戦略はない。良いものが残り、悪いものは淘汰される。できることは、変化の機会に対応して、どれだけフレキシブルに動けるかしかない。だから、「競争の場の選択」が重要になる。
どこで戦い、どんな事業をやっていくのか。経営者にとって本当に重要な選択とはそのことであり、勝つためにどこで戦うべきかをよく知り実践しているのが優れた経営者なのだと彼は言ったわけです。結果、インテルは世界最強の会社になりましたが、グローヴが経営畑ではなく理系出身だったのは、20世紀ならではのことだと谷口氏は分析しています。
業界に働く外的な力が企業のパフォーマンスを左右するのであれば、競争が激しくなくて魅力的な業界を選びましょうということです。そこにポジションをつくり、競争優位を確立しましょうということです。この考え方は、「ブルー・オーシャン戦略」として、さらに洗練されています。血で血を洗う激選区からの離脱です。
ポーターが強調しているのは、「やること」よりも「やらないこと」の選択です。企業の戦略にはコストと質の二つの軸があり、どちらで戦うかによって原料の調達や生産、マーケティング手法まで、すべてが違ってくる。「周りがやるからウチも」ではなく、「このために、ウチはこれをやらない」と、明確な旗印を立てるべきだというのです。
ただし、これは「あちらを立てれば、こちらが立たない」トレードオフの考え方であり、極めて21世紀的だと谷口氏。現在の消費者は、「安くて良いもの」を求めてやまないからです。
Value(価値)、Rarity(希少性)、In-imitability(模倣の不可能性)、Non-substitutability(代用の不可能性)。これらを備えた資源を開発し、確立することこそ、企業の最優先事項という考え方です。
一般の製品はリバース・エンジニアリングをかけて、部品からコピーすることが可能ですが、そうはできないことで有名なのがコカコーラのレシピ。また、ルイ・ヴィトンのブランドのように、目に見えない組織の特徴やビジネスモデルも分解できず、真似がしにくくなります。こうしたものを時間をかけて作るのが重要だというのが、バーニーの考えでした。
戦略経営を進める上で最も重要なのは、自己を知り、他者を知ること。ポーター理論は他者を知り、バーニー理論は自己を知るのにそれぞれ使い分けられそうだと、谷口氏は示唆しているのでしょうか。
伝説の経営者が取り入れたポジショニング・アプローチ
ポーターの「ポジショニング・アプチローチ」を実践したのが、インテル元CEOのアンディ・グローヴ。2016年に亡くなりましたが、「インテル3番目の社員」と呼ばれた伝説的経営者です。彼は、企業の戦略をダーウィンの「進化論」のようなものだと言ってのけました。最初から答えが見える戦略はない。良いものが残り、悪いものは淘汰される。できることは、変化の機会に対応して、どれだけフレキシブルに動けるかしかない。だから、「競争の場の選択」が重要になる。
どこで戦い、どんな事業をやっていくのか。経営者にとって本当に重要な選択とはそのことであり、勝つためにどこで戦うべきかをよく知り実践しているのが優れた経営者なのだと彼は言ったわけです。結果、インテルは世界最強の会社になりましたが、グローヴが経営畑ではなく理系出身だったのは、20世紀ならではのことだと谷口氏は分析しています。
「やらないこと」を宣言して、他と差をつける
場を選ぶには、まず自分の周りを知らなければなりません。周りを知るためにポーターの用意したメガネが「ファイブ・フォース・モデル」と呼ばれるものです。「ファイブ・フォース」とは五つの要因。「新規参入者、買手、売手、代替品、競争者」の五つが自社を脅かす脅威であるとして、これらを踏まえた上で経営戦略を策定することが必要だと説きました。業界に働く外的な力が企業のパフォーマンスを左右するのであれば、競争が激しくなくて魅力的な業界を選びましょうということです。そこにポジションをつくり、競争優位を確立しましょうということです。この考え方は、「ブルー・オーシャン戦略」として、さらに洗練されています。血で血を洗う激選区からの離脱です。
ポーターが強調しているのは、「やること」よりも「やらないこと」の選択です。企業の戦略にはコストと質の二つの軸があり、どちらで戦うかによって原料の調達や生産、マーケティング手法まで、すべてが違ってくる。「周りがやるからウチも」ではなく、「このために、ウチはこれをやらない」と、明確な旗印を立てるべきだというのです。
ただし、これは「あちらを立てれば、こちらが立たない」トレードオフの考え方であり、極めて21世紀的だと谷口氏。現在の消費者は、「安くて良いもの」を求めてやまないからです。
真似のできない資源づくりで、収益性を上げる
一方、バーニーの「資源ベース論」は、自社の持つ資源を生かして高い収益を得る戦略です。他の会社に真似できず、代替品が現れにくいしくみづくりがこの戦略のポイントになります。それをかなえる四つの要素が「VRIN」です。Value(価値)、Rarity(希少性)、In-imitability(模倣の不可能性)、Non-substitutability(代用の不可能性)。これらを備えた資源を開発し、確立することこそ、企業の最優先事項という考え方です。
一般の製品はリバース・エンジニアリングをかけて、部品からコピーすることが可能ですが、そうはできないことで有名なのがコカコーラのレシピ。また、ルイ・ヴィトンのブランドのように、目に見えない組織の特徴やビジネスモデルも分解できず、真似がしにくくなります。こうしたものを時間をかけて作るのが重要だというのが、バーニーの考えでした。
戦略経営を進める上で最も重要なのは、自己を知り、他者を知ること。ポーター理論は他者を知り、バーニー理論は自己を知るのにそれぞれ使い分けられそうだと、谷口氏は示唆しているのでしょうか。
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部










