テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
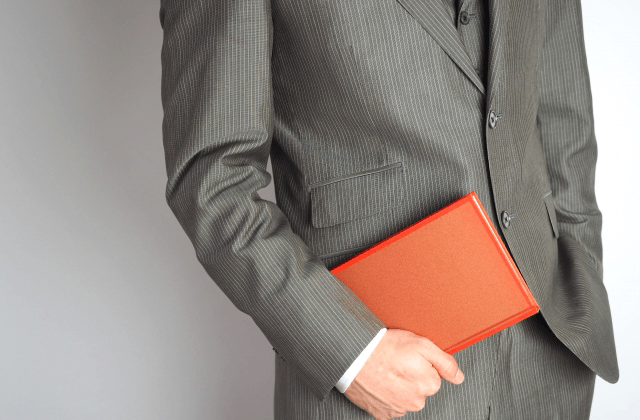
「不良債権処理」で育った事業再生の人材
今から15年前の5月、「産業再生機構」という組織が業務を始めました。2003年当時で40兆円と言われた不良債権を2年間で半減させ、企業の再生を進めることが狙い。機構は当初予定より1年前倒しの07年に解散しましたが、4年間で約312億円を納税、解散後の残余財産の分配によりさらに約432億円を国庫に納付するという業績を収めました。
実際に産業再生機構で勤務していた秋池玲子氏(ボストンコンサルティンググループ シニア・パートナー&マネージング・ディレクター、経済同友会副代表幹事)が、当時の手法について語ります。
また、破綻した企業を買い上げて立て直し、価値を上げて売却する案件の場合には、バイアウトファンドから見ると、「国に横取りされるのでは」と見えかねない懸念も生じていました。
そもそも不良債権処理は民間によってなされるのが最良なのですが、当時はまだそうした人材が国内に育っていませんでした。そこで産業再生機構では、当初5年間と時限立法された活動期間のうち2年間だけ買い取りをするとのルールを打ち立てました。残りの3年間については、買い取った1件1件の企業を3年以内に立て直して市場に戻す、すなわち売却するとの方針が立てられました。
多様なケースに同時に取り組むことにより、いろいろな見本ができただけでなく、金融機関やアドバイザー、弁護士や会計士、不動産業や事業再生支援ビジネスの人材が育っていきました。短期集中的に多くのケースに関わることで、専門家が育てられたのです。
産業再生機構に集まったのは、ピーク時220人ほど。うち官僚は1割程度で、それ以外は民間から集まったビジネス系人材、弁護士、会計士、不動産に詳しいプロなどでした。職員たちがいつも心がけたのは、「市場よりも市場らしく」行動すること。少しでも市場より甘い査定を行うと、民業圧迫につながりかねないからです。
新成長の分野など、未来に向けて新しい領域をつくっていく際、あるいは過去からの遺産として、うまく片を付けないと前に進めない課題がある場合、こうした短期集中的アプローチは今後も活用できるのではないか、と秋池氏は提言しています。
実際に産業再生機構で勤務していた秋池玲子氏(ボストンコンサルティンググループ シニア・パートナー&マネージング・ディレクター、経済同友会副代表幹事)が、当時の手法について語ります。
「民業圧迫」という懸念と戦いながら
産業再生機構が発足した当初、最も懸念されたのは「民業圧迫」という言葉だったと秋池氏は振り返ります。日本にようやくバイアウトファンドが生まれ始めていたこの頃、機構が同じ手法で不良債権処理を行い、市場価格よりも高く不良債権を買い取れば、民間には機会が訪れなくなるのではないかという懸念です。また、破綻した企業を買い上げて立て直し、価値を上げて売却する案件の場合には、バイアウトファンドから見ると、「国に横取りされるのでは」と見えかねない懸念も生じていました。
そもそも不良債権処理は民間によってなされるのが最良なのですが、当時はまだそうした人材が国内に育っていませんでした。そこで産業再生機構では、当初5年間と時限立法された活動期間のうち2年間だけ買い取りをするとのルールを打ち立てました。残りの3年間については、買い取った1件1件の企業を3年以内に立て直して市場に戻す、すなわち売却するとの方針が立てられました。
大小41件の事業再生に同時に取り組む
最初の2年間で一気に買い取りを行ったため、産業再生機構では41件の事業再生に同時に取り組むことになりました。その中にはダイエーやカネボウのような超大型の案件もあれば、地域のバス会社や地方を支えてきたメーカー、また温泉旅館を通してその町の再生を促すような案件もありました。多様なケースに同時に取り組むことにより、いろいろな見本ができただけでなく、金融機関やアドバイザー、弁護士や会計士、不動産業や事業再生支援ビジネスの人材が育っていきました。短期集中的に多くのケースに関わることで、専門家が育てられたのです。
産業再生機構に集まったのは、ピーク時220人ほど。うち官僚は1割程度で、それ以外は民間から集まったビジネス系人材、弁護士、会計士、不動産に詳しいプロなどでした。職員たちがいつも心がけたのは、「市場よりも市場らしく」行動すること。少しでも市場より甘い査定を行うと、民業圧迫につながりかねないからです。
短期集中的アプローチだから人材が育つ
産業再生機構で事業再生に取り組んだ人々は、4年後、民間に散っていきました。彼らが自分の周りでさらに人材を育てていくことにより、事業再生に携わる人材はさらにふくらんだとも言えます。新成長の分野など、未来に向けて新しい領域をつくっていく際、あるいは過去からの遺産として、うまく片を付けないと前に進めない課題がある場合、こうした短期集中的アプローチは今後も活用できるのではないか、と秋池氏は提言しています。
人気の講義ランキングTOP20










