テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
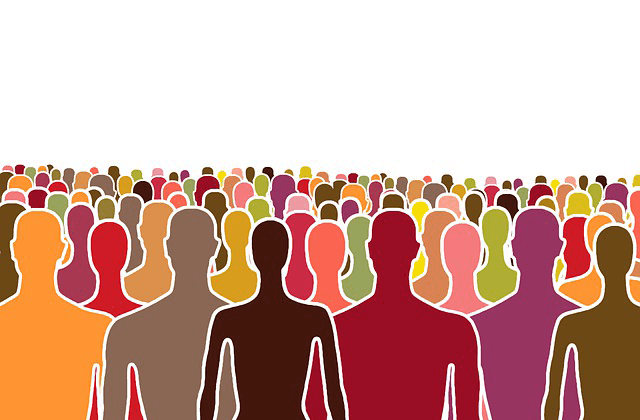
衝撃作『ソ連兵へ差し出された娘たち』揺さぶる既存の価値観
1945年夏。敗戦後の「満州国」に取り残された黒川開拓団(600名あまり)の中から、“娘たち”はソ連兵へ差し出され、「(性)接待」を強要されました。
“娘たち”が「接待」役に選ばれた条件は、(1)数え年で18歳以上、(2)未婚の女性――。それだけの理由で15、6名の“娘たち”は、集団内の支配関係上位者である“団幹部”に、ある意味で死よりも辛い宣告をされたのです。
ノンフィクション作家である平井美帆氏の著書『ソ連兵へ差し出された娘たち』は、被害者である“娘たち”だけでなく、当事者や関係者たちをほぼ実名で登場させながら、凄惨な史実を丹念に記しています。
そして“団幹部”は“娘たち”を集め、「このまま自決するようなことはできぬ。家族を残し出征されている方達になんと言って申し訳するのか。団の命を救うと思って、ウンと言ってほしい」と告げました。そのときのことを “娘たち”のリーダー的存在であった女性は、「それは死ねと言われるより悲しく辛いことであった」と綴っています。
これだけのやり取りからも、(1)“娘たち”を犠牲者として選択した背景に“出征されている方達”という言葉に含まれる不在であるが強力な“見えない力”が作用していること、(2)“見えない力”は男性原理であること(同じ女性であっても既婚という形で男性に紐付けられた段階で、コミュニティ内の最弱者ではなくなる)、(3)“娘たち”の逃れられない絶望――などを読み取ることができます。
さらに、回数の多寡が本質ではないことは大前提ではありますが、“団幹部”関係者の“娘たち”は「接待」の頻度が少なかったなど、「接待」の中にも差別の構造があったといいます。
“娘たち”のなかには、もう触れてほしくない者や「本当に辛かったことは記憶にない」と語る者もいれば、ことさらに言いはしないが秘め事にしたわけでもないのに誰にも想いを「受け止められなかった」と吐露する者もいました。
平井氏は“娘たち”一人ひとりに寄り添い、傾聴しながら、冷静な作家の視点を揺るがすことなく、静かな熱を帯びた筆致で「接待」の日から続く現在までの過酷な日々を、本書のなかで多層的に綴っています。
また、“娘たち”の魂からの訴えだけでなく、“娘たち”以外の関係者の責任不在や当事者意識の欠如、戦後補償における冷酷な仕打ち、侮辱的なレッテル貼りといったコミュニティからの差別、「接待」を歴史的に美化・正当化する過ちなど、今日まで続く負の課題を、本書のなかに浮かび上がらせていきます。
それらによって、本書は歴史に葬り去られる事実をすくいとった、貴重なノンフィクションになっています。
“娘たち”にとって「接待」がどれほど過酷で残酷な事実であっても、やむを得ずそれを促した“団幹部”ですら、安全な場所に戻り時間が経てば「減るものじゃないし」などという言葉が出てきます。また、不可抗力な点があったとはいえ見過ごしてきた“男たち”も、自分の恋人や妻がそうだったと自分事になった途端に嫌悪感をいだく自己を当然のごとく正当化して、“娘たち”を侮蔑します。また、“娘たち”とならなかった女性も、「非常時だから」と心ない言葉を投げつけられます。
そのたびに、極論すれば被害者以外にとっては他人事で深刻ではない事実だったのだと、さらに残酷な真実を突きつけられる“娘たち”。本来であれば、被害者は慰められ癒やされ、心身の被害に寄り添われる権利があります。しかし、“娘たち”はその権利さえも蹂躙され、二次的被害を受けてきたのです。
その事実は、“娘たち”以外に想像力や優しさが足りないといわれればそれまでですが、そもそもの価値観や切実感が違いすぎて自分事にできない“団幹部”や“男たち”をはじめ、“娘たち”とならなかった女性も含めた他者たちが、それほどの悪意がないことが状況をさらに悪くしているのではないかといった、悲しみや憤り以上のむなしさを感じさせるには十分です。
「自分ではない他者がされて嫌なことは何か」を考えるだけでは不十分であること。多様性が提唱される現代、事実の受け止め方や解釈も多様であること。社会の価値観や個人の自意識など、常に時代や周囲と対照されながらメンテナンスやアップデートが必要であること。さらに本質に立ち返り、弱者を犠牲者としなければなりたたない社会としないためにこそ行動が必要であることなどが、本書から立ち上がってきます。
しかし本書はそうなってはいません。だからこそでしょうか。本書は読む人や読むときによって心に響く箇所や読後感が変わってくるように思われます。同時に、そのことが本書の評価を高めていることにつながっていると実感します。
本書は第19回開高健ノンフィクション賞を受賞しています。同賞選考委員の田中優子氏(法政大学名誉教授)は「本書は、変わることのできなかった日本人の問題として悲しいことに全く色褪せていないのである」と評しています。
そういった評価や読後感からも、多様な読み方ができることが本書の価値であり、読むことによって既存の価値観が揺さぶられます。そして、その揺さぶりこそが実は本書が持つ大事な意味ではないでしょうか。
“娘たち”が「接待」役に選ばれた条件は、(1)数え年で18歳以上、(2)未婚の女性――。それだけの理由で15、6名の“娘たち”は、集団内の支配関係上位者である“団幹部”に、ある意味で死よりも辛い宣告をされたのです。
ノンフィクション作家である平井美帆氏の著書『ソ連兵へ差し出された娘たち』は、被害者である“娘たち”だけでなく、当事者や関係者たちをほぼ実名で登場させながら、凄惨な史実を丹念に記しています。
なぜ“娘たち”はソ連兵へ差し出されたのか
敗戦により崩壊した満州国とその混乱の最中で棄民された黒川開拓団の人びとは、暴徒化した先住民や侵攻するソ連兵の婦女暴行被害に悩むことになりました。そこで“団幹部”と新たに外部から加わった“男たち”は、ソ連兵に“娘たち”を差し出すことによって、これらの悩みを解決しようと考えます。そして“団幹部”は“娘たち”を集め、「このまま自決するようなことはできぬ。家族を残し出征されている方達になんと言って申し訳するのか。団の命を救うと思って、ウンと言ってほしい」と告げました。そのときのことを “娘たち”のリーダー的存在であった女性は、「それは死ねと言われるより悲しく辛いことであった」と綴っています。
これだけのやり取りからも、(1)“娘たち”を犠牲者として選択した背景に“出征されている方達”という言葉に含まれる不在であるが強力な“見えない力”が作用していること、(2)“見えない力”は男性原理であること(同じ女性であっても既婚という形で男性に紐付けられた段階で、コミュニティ内の最弱者ではなくなる)、(3)“娘たち”の逃れられない絶望――などを読み取ることができます。
さらに、回数の多寡が本質ではないことは大前提ではありますが、“団幹部”関係者の“娘たち”は「接待」の頻度が少なかったなど、「接待」の中にも差別の構造があったといいます。
「接待」後の“娘たち”を待ち受けていたもの
当然ながら、「接待」は、“娘たち”に深い悲しみと傷跡を残しました。ただし、“娘たち”一人ひとりが同じ悲しみや傷跡を記憶し抱えているわけではありません。“娘たち”はそれぞれが固有の悲しみ・傷跡・憤り・怒り・嘆きを抱え、引き上げ後も懸命に生き抜きました(なお、感染症に罹り現地で亡くなった者や帰国後早々に亡くなった者などもいます)。“娘たち”のなかには、もう触れてほしくない者や「本当に辛かったことは記憶にない」と語る者もいれば、ことさらに言いはしないが秘め事にしたわけでもないのに誰にも想いを「受け止められなかった」と吐露する者もいました。
平井氏は“娘たち”一人ひとりに寄り添い、傾聴しながら、冷静な作家の視点を揺るがすことなく、静かな熱を帯びた筆致で「接待」の日から続く現在までの過酷な日々を、本書のなかで多層的に綴っています。
また、“娘たち”の魂からの訴えだけでなく、“娘たち”以外の関係者の責任不在や当事者意識の欠如、戦後補償における冷酷な仕打ち、侮辱的なレッテル貼りといったコミュニティからの差別、「接待」を歴史的に美化・正当化する過ちなど、今日まで続く負の課題を、本書のなかに浮かび上がらせていきます。
それらによって、本書は歴史に葬り去られる事実をすくいとった、貴重なノンフィクションになっています。
“娘たち”をめぐる今日に続く課題とは
他方、本書の読みどころは、“娘たち”という被害者側からだけの視点にとどまっていない点にあります。読み進めていくうちに、「自分がされて嫌なことはしない」といった、普遍ともいえる基本的人権が尊重された社会での原則すらもかみ合っていないような、不気味な違和感を覚えます。“娘たち”にとって「接待」がどれほど過酷で残酷な事実であっても、やむを得ずそれを促した“団幹部”ですら、安全な場所に戻り時間が経てば「減るものじゃないし」などという言葉が出てきます。また、不可抗力な点があったとはいえ見過ごしてきた“男たち”も、自分の恋人や妻がそうだったと自分事になった途端に嫌悪感をいだく自己を当然のごとく正当化して、“娘たち”を侮蔑します。また、“娘たち”とならなかった女性も、「非常時だから」と心ない言葉を投げつけられます。
そのたびに、極論すれば被害者以外にとっては他人事で深刻ではない事実だったのだと、さらに残酷な真実を突きつけられる“娘たち”。本来であれば、被害者は慰められ癒やされ、心身の被害に寄り添われる権利があります。しかし、“娘たち”はその権利さえも蹂躙され、二次的被害を受けてきたのです。
その事実は、“娘たち”以外に想像力や優しさが足りないといわれればそれまでですが、そもそもの価値観や切実感が違いすぎて自分事にできない“団幹部”や“男たち”をはじめ、“娘たち”とならなかった女性も含めた他者たちが、それほどの悪意がないことが状況をさらに悪くしているのではないかといった、悲しみや憤り以上のむなしさを感じさせるには十分です。
「自分ではない他者がされて嫌なことは何か」を考えるだけでは不十分であること。多様性が提唱される現代、事実の受け止め方や解釈も多様であること。社会の価値観や個人の自意識など、常に時代や周囲と対照されながらメンテナンスやアップデートが必要であること。さらに本質に立ち返り、弱者を犠牲者としなければなりたたない社会としないためにこそ行動が必要であることなどが、本書から立ち上がってきます。
多様な読後感・既存の価値観を揺さぶる一冊
“娘たち”という被害者がはっきりとしていることで、たとえば今日的な人権論やジェンダー観をもって平井氏が書き進めれば、読者が一律の感想を持つように書ききることもできたと思います。しかし本書はそうなってはいません。だからこそでしょうか。本書は読む人や読むときによって心に響く箇所や読後感が変わってくるように思われます。同時に、そのことが本書の評価を高めていることにつながっていると実感します。
本書は第19回開高健ノンフィクション賞を受賞しています。同賞選考委員の田中優子氏(法政大学名誉教授)は「本書は、変わることのできなかった日本人の問題として悲しいことに全く色褪せていないのである」と評しています。
そういった評価や読後感からも、多様な読み方ができることが本書の価値であり、読むことによって既存の価値観が揺さぶられます。そして、その揺さぶりこそが実は本書が持つ大事な意味ではないでしょうか。
<参考文献>
『ソ連兵へ差し出された娘たち』(平井美帆著、集英社)
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-789015-0
<参考サイト>
平井美帆氏のサイト
http://hiraimiho.main.jp/index.html
『ソ連兵へ差し出された娘たち』(平井美帆著、集英社)
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-789015-0
<参考サイト>
平井美帆氏のサイト
http://hiraimiho.main.jp/index.html
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










