テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
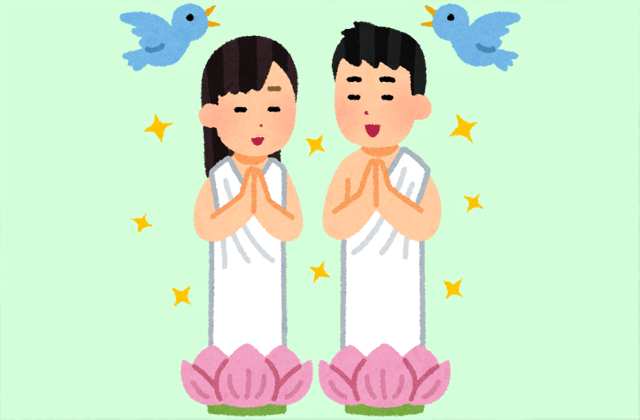
今を生きる20代「さとり世代」の特徴とは?
さとり世代にあてはまる人
「団塊世代」「バブル世代」「ゆとり世代」など、世代にはその時々の世情や人の生き様をあらわす名前がつけられてきました。そんな中、2013年に、流行語大賞にノミネートされた「さとり世代」をご存じでしょうか。何歳が対象になるか、という線引きは難しいところで、1987年から1996年生まれ、ゆとりの次、1990年代、と諸説あるようですが、おおむね今20代を過ごしている世代だと言われています。こうしてみると、ゆとり世代ともかぶっているようですね。若いうちから「さとる」理由
「悟る(さとる)」というと歳を重ねて、というイメージがありますが、まだ若いうちから世代の呼ばれ方としてこのようなネーミングをされるのはなぜでしょうか。さとり世代の最大の特徴は、欲がないことだといいます。昔は、昇進を夢見て、いい車を持って、いい家に住むという上昇志向の強い世代がありましたが、今ではできるだけひっそりと、日々を幸せに、というふうに、物よりも心の豊かさを求めるようになっているのだそうです。物の価値で競ったり、俗的な部分から少し離れた場所で価値を見いだそうとしたりする精神性が、まるで「悟った」ように見えるところから、さとり世代と呼ばれるようになったのですね。
「無理してでもやってみよう」でなく「調べてから一歩踏み出す」
さとり世代は、あまり外に出たがらず、お金も極力使おうとしません。無駄なことを嫌う合理的なところがあります。小さい頃からインターネット環境があり、家にいながらも多くの情報を手にできるだけに、世の中を俯瞰でみているところがあるのかもしれません。スタッフのなかにもさとり世代と近い者がいるので聞いてみると、そのスタッフは自分も含め周囲の同世代の人に共通しているのは、「調べてすぐわかること」にはトライせず、しかもやる前に想像だけでモノの良し悪しや自分にできることかどうかを判断してしまうところだといいます。もちろん、チャレンジ精神や冒険心のある人もいるけれども、スタッフの知る限りでは、「無理してでもとりあえずやってみよう」ではなく、どちらかというと「綿密に調べてから一歩踏み出す」という慎重派が良くも悪くも多いとのこと。
また、「正解かどうかがあらかじめわかってしまう(と本人が感じる)からこそ、臆病になってしまう」という話も聞きました。これらのことが世代の傾向としてどれくらいの割合でいるかはわかりませんが、検索すればなんでもすぐに調べられるというネット環境と関係がありそうですね。
あきらめの精神
原田曜平氏著の『さとり世代 ―盗んだバイクで走り出さない若者たち』では、さとり世代の行動理念について、「プラスになるかどうか」ではなく、「マイナスにならないか」という考え方で動いていると指摘しています。この、「別にどうしても上にいかなくても良い」という考え方は、世の中に格差が生まれたからではないか、と記されています。ソーシャルメディアが発達し、さまざまな人との交流ができるようになった今、それぞれの集まりごとに自分を少しずつ変えていく「空気を読む」ことがうまくなり、自分はこのへんであるという、ある種のあきらめにも似た感情が生まれてくるのかもしれません。それでいて、個々の幸せを重視するようになった結果、「無理に合わせなくても良い」となり、個人の自由が確立されるようになってきたということです。
「何でもあり」の良さと悪さ
こうして見ていくと、「さとり」とは言い得て妙ですね。現実を見据え、それでいて多くを求めず、日々の暮らしに満足する考え方はすばらしいと思います。しかしそれは必ずしも良いことばかりではないと思います。恋愛、お金、地位、これらへの執着を早くから捨て去り、「あがく」ことをしないために、打たれ弱くなることもあるかもしれません。焦りもがく苦しみがなくなるのは、人生のスパイスを失うことに他なりません。ただひとつ言えるのは、今の時代に合わせてみんな精一杯生きているということです。そんな「さとり世代」の生き方、その方法もまた、厳しい世の中を生き抜くための一つの処世術なのかもしれませんね。
<参考文献>
『さとり世代―盗んだバイクで走り出さない若者たち』(原田曜平著、KADOKAWA/角川書店)
『さとり世代―盗んだバイクで走り出さない若者たち』(原田曜平著、KADOKAWA/角川書店)
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










