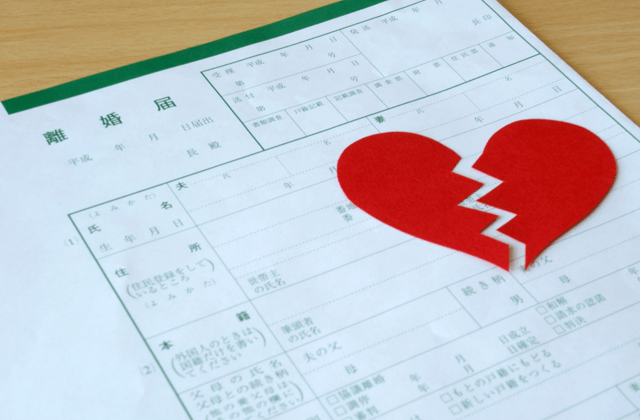
3人に1人が離婚する日本人の再婚率は?
日本では「3人に1人が離婚する」といわれています。確かに自分の周囲を考えてみると案外、当たっているのではないか、という気はしていますが、実際のところはどうなのでしょうか。まずは世界の数字から見てみましょう。
<離婚率>
1位:アメリカ/3.6
2位:スウェーデン/2.46
3位:韓国/2.3
4位:ドイツ/2.19
5位:イギリス/2.05
6位:フランス/1.97
7位:シンガポール/1.86
8位:日本/1.77
9位:イタリア/0.91
このなかではアメリカが1位、それにスウェーデン、韓国、ドイツと続いています。日本の離婚率は世界的にみれば比較的低いといえるのかもしれません。
さて、はじめに3人に1人は離婚すると示しました。これは、その年の婚姻率(人口1000人当たりの結婚数)に対する離婚率(人口1000人当たりの離婚数)の割合のことです。日本の場合、さきほど上げた厚労省の発表によると、婚姻率は5.2で、離婚率は1.77、つまり、およそ「3組に1組は離婚する」という言い方になるわけです。
ここで、「3組に1組が離婚」という言い方ですが、少し注意が必要です。日本では、婚姻件数は2011年から2013年まで約66万件台を保っていたのですが、2014年には約64万9千件に減少しています。一方、離婚件数は、2011年から2014年まで約22~23万件台となっています(毎年、少しずつ減っていますが)。ただ、離婚件数に該当するのはその年に結婚した夫婦だけではなく、それ以前に結婚した夫婦も含めた、さまざまな年代の夫婦です。つまり、分母の婚姻件数が少なくなっている状況ですから、実際よりは多い数値が出ていると考えてもいいかと思われます。
・「価値観の違い」(53.2%)
・「金銭感覚の違い」(46.2%)
・「性格の不一致」(43.8%)
・「夫婦の会話がない」(32.0%)
これらの項目では、夫婦間におけるコミュニケーションのズレなどが問題だと思われますが、具体的なところはややつかみにくいところはあります。
そこで、同サイトによると、さらに重要なのは、「相手が家事に協力的ではない」(女性27.2%)、「相手が育児に協力的ではない」(同26.2%)の項目だといいます。「この2つは女性と男性との間で20ポイント以上の開きがあり、男女で意識の隔たりがある」とのことです。
ここ数年で時代は大きく変わっています。スタッフの知人には、夫と同じくらいの給与をかせぐ妻がいたり、出産後も同じように働く女性が少なくありません。もはや「家計を支えるのは男性」という考えはもはや通用しなくなっており、男性側に柔軟な考えを持つことが求められているのではないでしょうか。
<全婚姻件数に対する再婚件数の割合>
1994(平成6)年:夫/12.9%、妻/11.4%
2004(平成16)年:夫/17.8%、妻/15.9%
2010(平成22)年:夫/18.5%、妻/16.2%
2011(平成23)年:夫/18.8%、妻/16.4%
2012(平成24)年:夫/19.0%、妻/16.4%
2013(平成25)年:夫/19.2%、妻/16.5%
2014(平成26)年:夫/19.3%、妻/16.6%
データから、離婚や再婚への偏見が減っているということがうかがえます。合理的に考えれば、たしかに個人がより幸福に生きていくためにパートナーを変えるということは自然なことといえるかもしれません。
ただ一方で、育児に関する問題も見逃せません。もし離婚してシングルになった場合、そのまま子育てをする親は非常に大変で、また仕事に関しても、時間的制約などから不遇を受ける可能性があることは否定できません。この点に関しては、周囲や企業の配慮だけでなく、国の政策に期待するところは少なくないでしょう。
主要国のなかでは離婚率の低い日本
離婚率とは、その年の離婚数を人口1000人当たりで割ったもの。2015年の厚生労働省発表によると、世界の主な国の離婚率は以下の順となっているそうです。<離婚率>
1位:アメリカ/3.6
2位:スウェーデン/2.46
3位:韓国/2.3
4位:ドイツ/2.19
5位:イギリス/2.05
6位:フランス/1.97
7位:シンガポール/1.86
8位:日本/1.77
9位:イタリア/0.91
このなかではアメリカが1位、それにスウェーデン、韓国、ドイツと続いています。日本の離婚率は世界的にみれば比較的低いといえるのかもしれません。
さて、はじめに3人に1人は離婚すると示しました。これは、その年の婚姻率(人口1000人当たりの結婚数)に対する離婚率(人口1000人当たりの離婚数)の割合のことです。日本の場合、さきほど上げた厚労省の発表によると、婚姻率は5.2で、離婚率は1.77、つまり、およそ「3組に1組は離婚する」という言い方になるわけです。
ここで、「3組に1組が離婚」という言い方ですが、少し注意が必要です。日本では、婚姻件数は2011年から2013年まで約66万件台を保っていたのですが、2014年には約64万9千件に減少しています。一方、離婚件数は、2011年から2014年まで約22~23万件台となっています(毎年、少しずつ減っていますが)。ただ、離婚件数に該当するのはその年に結婚した夫婦だけではなく、それ以前に結婚した夫婦も含めた、さまざまな年代の夫婦です。つまり、分母の婚姻件数が少なくなっている状況ですから、実際よりは多い数値が出ていると考えてもいいかと思われます。
離婚の理由
離婚の理由にはさまざまなものがあるかと思われますが、ダイヤモンドオンラインの調査によると、離婚にいたった女性側の理由は以下の通り(複数回答)。・「価値観の違い」(53.2%)
・「金銭感覚の違い」(46.2%)
・「性格の不一致」(43.8%)
・「夫婦の会話がない」(32.0%)
これらの項目では、夫婦間におけるコミュニケーションのズレなどが問題だと思われますが、具体的なところはややつかみにくいところはあります。
そこで、同サイトによると、さらに重要なのは、「相手が家事に協力的ではない」(女性27.2%)、「相手が育児に協力的ではない」(同26.2%)の項目だといいます。「この2つは女性と男性との間で20ポイント以上の開きがあり、男女で意識の隔たりがある」とのことです。
ここ数年で時代は大きく変わっています。スタッフの知人には、夫と同じくらいの給与をかせぐ妻がいたり、出産後も同じように働く女性が少なくありません。もはや「家計を支えるのは男性」という考えはもはや通用しなくなっており、男性側に柔軟な考えを持つことが求められているのではないでしょうか。
離婚してもしっかり子育てできる社会に
世界的な比較による日本の離婚率の低さは、もしかしたら「世間の目」というものも関係しているかもしれません。いわゆる「バツイチ」への偏見とでもいうべきものでしょうか。しかし、この意識はここ20年近くのあいだに柔軟な方向に変化しているようです。以下は厚生労働省の発表による再婚率(全婚姻件数に対する再婚件数の割合)ですが、夫も妻も20年間のあいだにおよそ5~6%ほど高い数値になっていることが分かります。<全婚姻件数に対する再婚件数の割合>
1994(平成6)年:夫/12.9%、妻/11.4%
2004(平成16)年:夫/17.8%、妻/15.9%
2010(平成22)年:夫/18.5%、妻/16.2%
2011(平成23)年:夫/18.8%、妻/16.4%
2012(平成24)年:夫/19.0%、妻/16.4%
2013(平成25)年:夫/19.2%、妻/16.5%
2014(平成26)年:夫/19.3%、妻/16.6%
データから、離婚や再婚への偏見が減っているということがうかがえます。合理的に考えれば、たしかに個人がより幸福に生きていくためにパートナーを変えるということは自然なことといえるかもしれません。
ただ一方で、育児に関する問題も見逃せません。もし離婚してシングルになった場合、そのまま子育てをする親は非常に大変で、また仕事に関しても、時間的制約などから不遇を受ける可能性があることは否定できません。この点に関しては、周囲や企業の配慮だけでなく、国の政策に期待するところは少なくないでしょう。
<参考サイト>
・厚生労働省ホームページ(平成26年人口動態統計の年間推計、平成26年人口動態統計月報年計(概数)の概況)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei14/dl/honbun.pdf
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai14/dl/gaikyou26.pdf
・DIAMOND online:離婚の理由、一発KOよりボディブローが効く2016/8/31
http://diamond.jp/articles/-/100359?page=2
・厚生労働省ホームページ(平成26年人口動態統計の年間推計、平成26年人口動態統計月報年計(概数)の概況)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei14/dl/honbun.pdf
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai14/dl/gaikyou26.pdf
・DIAMOND online:離婚の理由、一発KOよりボディブローが効く2016/8/31
http://diamond.jp/articles/-/100359?page=2
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子
毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング
長谷川眞理子







