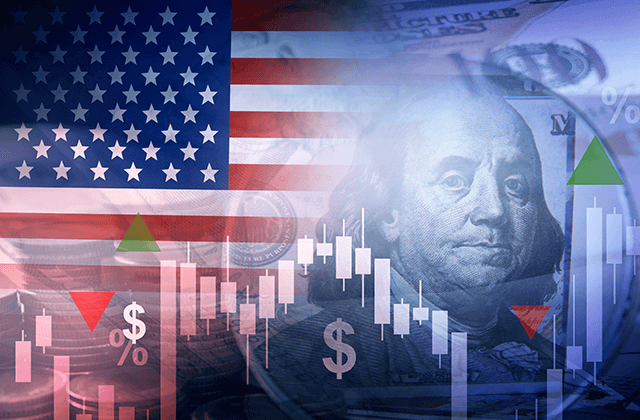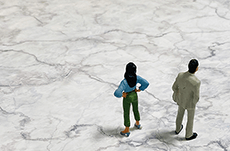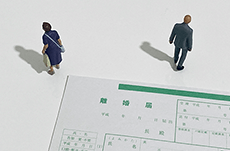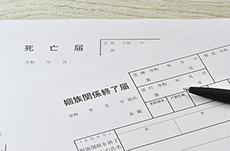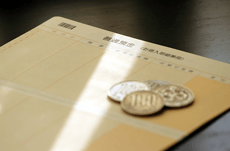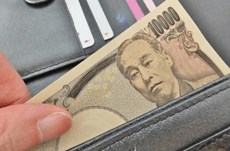社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

不動産バブル到来で注目される「マンション格差」
日本も不動産バブル到来か
近年、いわゆる中国バブルに対する懸念が強まっています。主な要因は、北京や上海、沿岸部の杭州やアモイなど20余りの大都市の不動産価格の急騰です。その一方で「主要な70都市の中でも北朝鮮国境に近い丹東やウイグル族が暮らすウルムチなど6都市は前月比で下落し、不動産市場の二極化が問題になっています。実は日本も同様の問題を抱えています。マイナス金利政策の影響を受け、住宅ローンは史上空前の低金利時代に突入しました。だぶついたマネーは不動産市場に集中し、不動産マネーはかつての「バブル時代」を超えています。中国と同様に、不動産価格が上昇しているのは、主に東京、大阪、名古屋といった大都市圏です。それゆえに、都心バブルとも言われています。一方、三大都市圏と札幌、仙台、広島、福岡を除いた地方では不動産価格の下落が続いており、不動産格差が深刻化しています。
日本人の新築信仰とマンションバブル
首都圏内おいては、金融政策とは別の理由も加わって不動産の価格格差が広がっています。2020年の東京オリンピックに向けた建設需要の影響で建築費が値上がりし、首都圏の新築マンションの平均価格がバブル期並みとなっているのです。これでは平均的な所得水準の購買者にはなかなか手が出ません。その一方で、中古マンションや戸建ては新築マンションに比べて割安感があり、投資ビジネスではなく居住目的の購買者から人気を集めています。一般の人が新築マンションに手を出すことができない現状はいびつな不動産格差が生じていると言えるでしょう。
とは言っても、住むならやっぱり新築が良いという方は少なくないと思います。日本人は非常に「新築好き」な国民です。他の先進国に比べて、住宅の建て替え頻度が高く、人口に対する新築住宅建設の割合も高いのです。住宅ジャーナリストの榊淳司氏はそれを神道の清浄観と結びつけて「新築信仰」と呼んでいます。「新築信仰」が都心の新築マンションバブルの遠因になっているとも考えられます。
たくさんのマンション格差
榊淳司氏には『マンション格差』(講談社)という著書があります。本の帯には「35年前に購入したマンションの売却査定額が3200万円と800万円。何が運命を分けたのか!?」とあり、具体的な事例を踏まえて「マンション格差」がどのようにして生じるのかを論じます。「マンション格差」と一口に言っても、様々な格差があります。たとえば、TBSドラマ「砂の塔~知りすぎた隣人」が2016年10月から12月にかけて放送されましたが、そこで描かれたタワーマンションのヒエラルキーをはじめ、前述のような新築と中古、あるいは分譲と賃貸の差、またマンションのブランド格差という切り口もあります。
本書によるとブランドでマンションを選ぶ人は実は多いそうです。それに対して榊氏は「マンションのブランドは幻想である」、「ブランドはあくまでも参考程度。格差の基準とはなりにくい」と主張しています。
マンションは「9割が立地」
本書の本題である分譲マンションの資産価値の格差はどのようにして生じるのでしょうか。榊氏は「9割が立地」と述べています。不動産を購入する上で当然の指摘と思われるかもしれませんが、立地が全体の「9割」もの重要度を占めているというのがポイントです。立地に対する見方は、本書とともに『23区格差』(池田利道著、中央公論新社)が参考になります。さて、残りの1割は何でしょう。その多くはデザインや施工精度などのハード部分です。中でももっとも重要なのがハードとソフトの間を担っているとも言える「管理」だそうです。建築に欠陥があれば資産価値は大きく下落します。それと同様に、管理に不正があるとマンションの格が一気に落ちるそうです。それだけではなく、管理の質が落ちればマンションの寿命も短くなります。「中古マンションは管理で買え」といわれるほどに管理は資産価値を左右するのです。
本書末には、三井不動産や三菱地所をはじめとする「デベロッパー大手12社をズバリ診断」が特別付録として掲載されています。前述の通り、マンションにブランド格差はないかもしれませんが、会社によってそれぞれ独自の開発姿勢や販売方針があります。マンションの購入を検討している方は一度チェックしてみるといいでしょう。
~最後までコラムを読んでくれた方へ~
「学ぶことが楽しい」方には 『テンミニッツTV』 がオススメです。
明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。
『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。
なぜ思春期は大事なのか?コホート研究10年の成果に迫る
今どきの若者たちのからだ、心、社会(1)ライフヒストリーからみた思春期
なぜ思春期に注目するのか。この十年来、10歳だった子どもたちのその後を10年追跡する「コホート研究」を行っている長谷川氏。離乳後の子どもが性成熟しておとなになるための準備期間にあたるこの時期が、ヒトという生物のライ...
収録日:2024/11/27
追加日:2025/07/05
フェデラリスト・ハミルトンの経済プログラム「4つの柱」
米国派経済学の礎…ハミルトンとクレイ(1)ハミルトンの経済プログラム
第2次トランプ政権において台頭する米国派経済学。実はこの保護主義的な経済学は、アメリカの成長と繁栄の土台を作っていた。その原点を振り返り解説する今シリーズ。まずはワシントン政権の財務長官でフェデラリストとして、連...
収録日:2025/05/15
追加日:2025/07/08
グリーンランドに米国の軍事拠点…北極圏の地政学的意味
地政学入門 ヨーロッパ編(10)グリーンランドと北極海
北極圏に位置する世界最大の島グリーンランド。ここはデンマークの領土なのだが、アメリカの軍事拠点でもあり、アメリカ、カナダとヨーロッパ、ロシアの間という地政学的にも重要な位置にある。また、気候変動によってその軍事...
収録日:2025/02/28
追加日:2025/07/07
スターバックスのコンセプトは「サードプレイス」
ストーリーとしての競争戦略(6)事例に見る経営者の戦略
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授の楠木建氏が、ホットペッパーとスターバックスを事例として、コンセプトの重要性を解説する。スターバックスやホットペッパーは、「第3の場所」・「狭域情報」といったコンセプトを的確に...
収録日:2017/05/25
追加日:2017/07/18
最悪のシナリオは?…しかしなぜ日本は報復すべきでないか
第2次トランプ政権の危険性と本質(8)反エリート主義と最悪のシナリオ
反エリート主義を基本線とするトランプ大統領は、金融政策の要であるFRBですらも敵対視し、圧力をかけている。このまま専門家軽視による経済政策が進めば、コロナ禍に匹敵する経済ショックが世界的に起こる可能性がある。最終話...
収録日:2025/04/07
追加日:2025/06/28