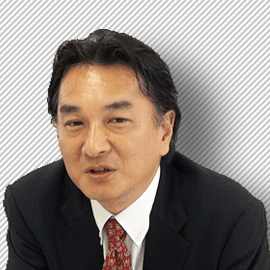●組織も人も、適度な不安感を持つことが大事だ
前回、「鬼に金棒」という話をしましたが、現場での鬼について考えていく、すなわち現場の意識におけるポイントを4つ紹介します。第1に、自分は95点だという認識が重要だと述べましたが、その際に、5点分不足しているのだという不安感を持つことが不可欠です。自分が大丈夫だと思っている人間に成長はありませんし、対応策も効きません。組織も同じことです。組織も人も、適度な不安感を持つことが大事です。ただし、不安感を持ちすぎても駄目ですから、適度という言い方をしています。
第2に、ヒューマンエラーや安全にとって、一番効く対策は、基本をしっかりこなすということです。これは、その会社が持っている歴史を踏まえるということに他なりません。会社が作り上げてきたマニュアル、いわゆる基本動作が肝心です。その会社で作り上げてきたマニュアルに勝るエラー対策、安全対策はありません。こうした基本動作をしっかりこなしていくならば、大きな事故はもちろんのこと、エラーもほとんど起こらないはずなのです。ただし、何度も申し上げるように、基本ができたから100点だとは思わせないような、意識教育も不可欠です。
●助けられた人が感謝を伝えられる環境づくりを目指せ
次の第3と第4のポイントは、自分に足りない残りの5点を補っていくときに役立つものです。第3に、エラー対策も含めて、1人でできることは、たかが知れているということです。そこでフォロワーシップ、つまり、いろんな人たちがどう助けていくのかを考えなければいけません。そのためには、みんなで声掛けをするといった、助け合うという精神が必要です。ただし、単純に助け合うといっても、声を掛けられたり助けられたりしたときに、助けられた人が「ありがとう」と感謝を伝えられる環境づくりを目指すべきです。
声掛けをする習慣が大切だということは、どこでも言われていますが、声を掛けてくれた人に「ありがとう」と言える部署がどれだけあるでしょうか。「ありがとう」と言ってもらえれば、次に効いてきます。特によくあるのが、自分が忘れていたときに声を掛けてもらえれば、素直に「ありがとう」と言えるけれど、忘れていない場合に声を掛けられると、つい迷惑そうな顔をしてしまうということです。しかし、これをされてしまうと、次からなかなか声を掛けにくくなります。...