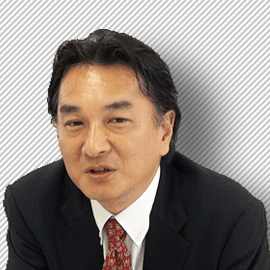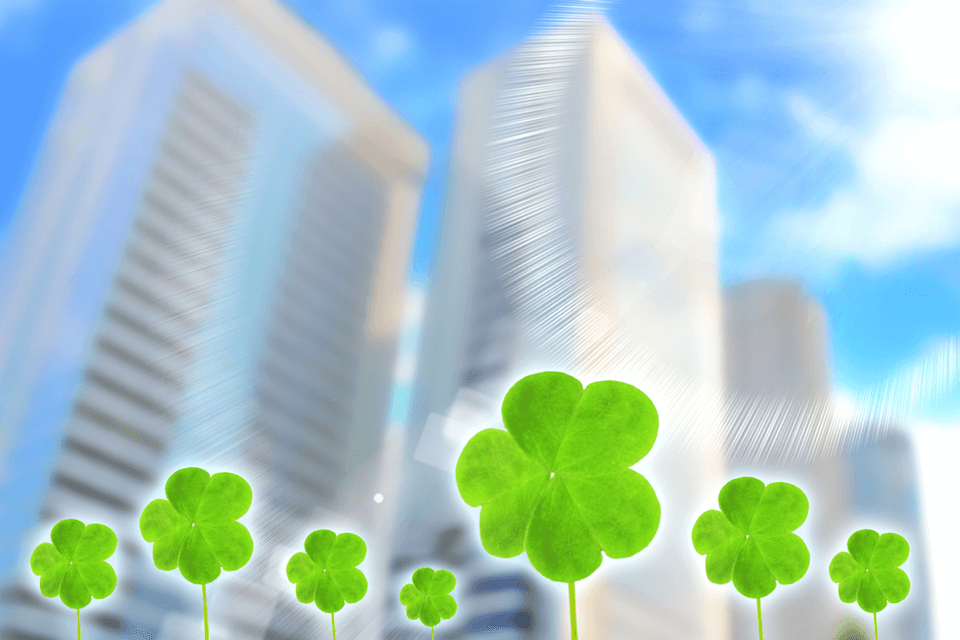●公共サービス的なレピュテーションを上げていく
質問 先生は以前、リスクを冒して三遊間のゴロを捕球する必要があるとおっしゃっていました。「良い仕事」をするためには、金銭ではないモチベーションとして、どのようなものがあるのでしょうか。
岡田 リスクを冒してでも、三遊間のゴロを取りに行くべきだとは、必ずしも思いません。これは、トップを含めて会社全体として、そういう社員と会社でありたいのか、それとも、下手なことをせずに堅実に商売をしたいのかによります。したがって、トップマネジメントの方針に沿うように、社員教育を考えていくべきでしょう。エラーについても、何をエラーと見るかは、その会社全体の考え方や立ち位置で決まってきます。
次に、「良い仕事」のモチベーションについてですが、正直に言えば、それをお金で見ても構いません。リスクを取りにいく会社のインセンティブは、お金でもいいと思います。というのも、リスクを取るのは、もうけるためですから。
しかし、リスクを取りにいけない、ある程度成熟した産業の中でどのように生き残っていくかを考えるなら、話は別です。確かに1960年代の高度成長期には、ちょっと先のゴロを取るだけで、給料が何倍にもなりました。今でもITベンチャーであれば、会社の成長と自分の給料がセットになっているので、おそらくここ5年ぐらいまでは、リスクを取りにいけば給料も上がるでしょう。ITベンチャーや戦略コンサルに勤める人のインセンティブは、金銭でも構わないわけです。
しかし、日本の8割の企業は、会社の売り上げもこれ以上上がらない中で、どれだけ現状の市場を維持していくかが問題になっています。だとすれば、そこでリスクを取りにいけと言っても、取りにいけません。取りにいった先に利益はなく、社員の給与上昇も見込めないからです。こうした状況では、金銭はインセンティブにはなり得ません。
特に今後考えなければいけないのは、公共サービスです。日本では、公共サービスが非常に重要な位置を占めています。これがなければ、産業は成り立ちません。しかし、公共サービスに対する評価は、極めて低くなっています。そこで働いている人たちがインセンティブを持つためには、お金ではない形で考えていく必要があります。ここで地域貢献や社会貢献が浮上するのです。
レピュテーションもその一環です。金がもうかる...