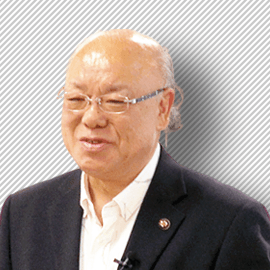●研究組織の運営により、都市政策につながる知見を得る
2009年(平成21年)に、健康をまちづくりの大黒柱として運営をしていくための研究組織を立ち上げました。スマートウエルネスシティを都市モデルにした「Smart Wellness City 首長研究会」です。当時は9市の市長によって組織されましたが、現在は37都道府県における74の自治体の首長が所属しています。私はその会長をずっと勤めており、それによってさまざまなデータや情報を得ることができます。非常にラッキーなポジションです。この中で、これからお話しするような都市政策にもつながる施策が、提案されていきました。
●自家用車の依存度と糖尿病患者数には関連がある
この研究会を続けていく中で、いろいろな学者にお話をいただいたり、研究発表を行っていただきました。その中で2つ、特に重要な発表がありました。
1つ目は為本浩至先生の発表で、生活習慣病の発症には、地域の環境因子も一定の影響があるというものです。左のグラフは、東京、大阪、愛知において自家用車に頼っている人の割合です。暮らしの中で一番、自家用車に頼っているのが愛知で、次が大阪、東京と続きます。東京は自家用車には不便な町だということが分かります。一方、右側のグラフは糖尿病の患者数です。一番多いのが愛知、次が大阪、一番少ないのが東京です。
●歩く効果は足し算可能である
2つ目は久野譜也先生が発表されたものです。昔は、20~30分間継続して運動しないと内臓脂肪が燃えないとされていました。久野先生は、これが間違っていることを明らかにしました。5分でも1分でも運動すれば、その効果は足し算されていくことが、エビデンスを伴って示されたのです。
このように考えると、東京を見習うことが重要であるということが分かります。とりわけこれは、歩数の問題です。見附市では、東京並みに歩くことを推奨しています。歩かざるをえないような都市設計を行い、歩いた方が楽しいということを打ち出し、歩いて暮らすまちを作っていくことが、スマートウエルネスシティの一番のポイントです。研究会では、そうした都市設計の背景となるデータが示されたのです。