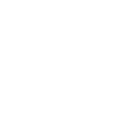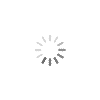執行草舟は小学生のころ、1行もわからないのに、岩波文庫のカントによる『純粋理性批判』を読み通したという。当時は、結局カントはわからなかったものの、他の本が易しく思えてしかたがないということを経験した。しかも、時が経つにつれて、当時はわからなかったことも、「わかる時期」が来るという。なにより読書を「当事者」として実践することが大切なのである。そうすれば、おのずと「行間」も読めるようになってくる。(全10話中第1話)
※インタビュアー:神藏孝之(10MTVオピニオン論説主幹)
読書と人生
どうすれば「行間」が読めるようになるか
読書と人生(1)「命懸けの読書」とは何か
時間:14分25秒
収録日:2019年5月14日
追加日:2019年8月16日
収録日:2019年5月14日
追加日:2019年8月16日
≪全文≫
●「必要性」で読む読書は、読書ではない
―― 「命がけの読書」というフレーズは社長らしいですね。
執行 僕自身が自慢としているのは、今の時代、少し忘れられていますが、読書そのものが僕にとって武士道なのです。僕は武士道が好きで、武士道を表明して生きてきました。もちろん今の時代にあって、これは「チャンバラしよう」という話ではありません。「何か1つのことに命を懸ける」ということです。僕の場合、それが小学校から「読書」なのです。僕の読書は命懸けで、単なる本が好きというレベルではありません。それが僕の大きな自慢です。
それが68歳になった今、日本中に僕ほど読んでいる人は一人もいません。これは驚くことです。本を「ものにしている」人も、一人もいません。僕は読書を「ものにしている」のも自慢です。少し威張って聞こえるかもしれませんが、「昔の教養人」を目指していたのです。何かの専門家や学者になるからではなく、読書によって人格を築き上げたかったのです。英国のジェントルマンもそうでした。若い頃そういう教養人に憧れ、なろうとして、ある程度なれていると思います。
ところが自分が大人になって世の中を見回してみると、そういう人はまったくいなくなりました。まったく読まないか、自分の専門など仕事などの必要性から読む人ばかりです。
昔の考えでは、「必要性で読む読書」は読書ではありません。これは私だけでなく、昔の読書家の考え方です。読書とは「読書そのもの」に価値があるのです。だから悪く言えば「現世離れ」もしています。ただ読書の思想とは、もともと現世離れしたもので、「現世から離れるために読書をする」という発想が根本にあります。
これはアメリカのアイビーリーグ、イギリスのオックスフォードやケンブリッジなど、昔の大学が全部、深山幽谷というか、森の中にあったことからもわかります。読書人をつくるには、現世と触れ合わないことが昔は条件だったのです。
僕も読書とは、そういうものだと思います。その意味で現代人に読書家はいないと思います。「役に立つものを読もう」と思うだけで、その人間は読書家ではないのです。
―― ハウツーになるのですね
執行「勉強家」かもしれませんが、勉強家と読書家は違います。読書家とはルネッサンスの頃から、モンテーニュなどモラリストになるような伝統があります。そうした教養...
●「必要性」で読む読書は、読書ではない
―― 「命がけの読書」というフレーズは社長らしいですね。
執行 僕自身が自慢としているのは、今の時代、少し忘れられていますが、読書そのものが僕にとって武士道なのです。僕は武士道が好きで、武士道を表明して生きてきました。もちろん今の時代にあって、これは「チャンバラしよう」という話ではありません。「何か1つのことに命を懸ける」ということです。僕の場合、それが小学校から「読書」なのです。僕の読書は命懸けで、単なる本が好きというレベルではありません。それが僕の大きな自慢です。
それが68歳になった今、日本中に僕ほど読んでいる人は一人もいません。これは驚くことです。本を「ものにしている」人も、一人もいません。僕は読書を「ものにしている」のも自慢です。少し威張って聞こえるかもしれませんが、「昔の教養人」を目指していたのです。何かの専門家や学者になるからではなく、読書によって人格を築き上げたかったのです。英国のジェントルマンもそうでした。若い頃そういう教養人に憧れ、なろうとして、ある程度なれていると思います。
ところが自分が大人になって世の中を見回してみると、そういう人はまったくいなくなりました。まったく読まないか、自分の専門など仕事などの必要性から読む人ばかりです。
昔の考えでは、「必要性で読む読書」は読書ではありません。これは私だけでなく、昔の読書家の考え方です。読書とは「読書そのもの」に価値があるのです。だから悪く言えば「現世離れ」もしています。ただ読書の思想とは、もともと現世離れしたもので、「現世から離れるために読書をする」という発想が根本にあります。
これはアメリカのアイビーリーグ、イギリスのオックスフォードやケンブリッジなど、昔の大学が全部、深山幽谷というか、森の中にあったことからもわかります。読書人をつくるには、現世と触れ合わないことが昔は条件だったのです。
僕も読書とは、そういうものだと思います。その意味で現代人に読書家はいないと思います。「役に立つものを読もう」と思うだけで、その人間は読書家ではないのです。
―― ハウツーになるのですね
執行「勉強家」かもしれませんが、勉強家と読書家は違います。読書家とはルネッサンスの頃から、モンテーニュなどモラリストになるような伝統があります。そうした教養...
人気の講義ランキングTOP10