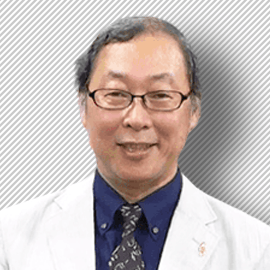●「幻想交響曲」が生んだ「恋人のメロディー」とは
―― もう一方で、先ほどの「六番」の流れもありましたね。
野本 (ベートーヴェンの)五番と六番で対抗して、どちらを取るかで争っていたロマン派ですが、六番の交響曲のように、自分でタイトルを付け、何を表現しているか字で書いちゃいましょう、という系列を「標題音楽」と言います。
これは「物語音楽」とはちょっと区別しなくてはいけなくて、音楽をどういうふうに書いたかを言葉で説明する。物語があって、それを音楽にするというよりは、音楽を言葉で説明するんですが、その最初の人がベルリオーズ。とりわけ「幻想交響曲」です。
この交響曲では、「このメロディーは、これを意味するというのを決めちゃえ」ということをしました。それが…。
<ピアノ演奏>
これを「恋人のメロディー」と呼んでいるんですね。このメロディーが出てきたら、常に恋人を表しています。つまり、意味とメロディーを一致させることをやったんです。これを「固定楽想」、フランス語で"idée fixe"(イデー・フィクス)と言います。そういうことをやって、これをアレンジしていくことで、「恋人がどんな姿になっているか」を想像させようということなんです。たとえば第5楽章になると…。
<ピアノ演奏>
こんな感じに変わってしまうんですが、なんかちょっと下品な感じがしますね。実は魔女になっちゃったんです。
―― これも、すごい話ですね。
野本 そうですね。彼氏に殺されてしまって、魔女になってしまったという様子を表している。そういうふうに、同じメロディーでもアレンジを変えるといろいろな感情表現ができるじゃないか、ということに気がついたのがベルリオーズだったわけです。
―― 人を象徴するメロディーをつくって、それをいろいろ変えることによって、象徴する人物が喜んでいるのか、悲しんでいるのかを表現した。
野本 どういう環境に置かれているのかなどが想像できる、ということをしたんですね。
●ワーグナーの発明した「ライトモチーフ」
野本 ベルリオーズの大親友だった人にワーグナーがいて、オペラが得意な方でした。彼は、「恋人だけじゃなく、もっといっぱいつくっちゃって、全部、意味を決めてしまえば」みたいにしたんです。たとえば…。
<ピアノ演奏>
これを「剣」のモチーフにしちゃえば? という具...