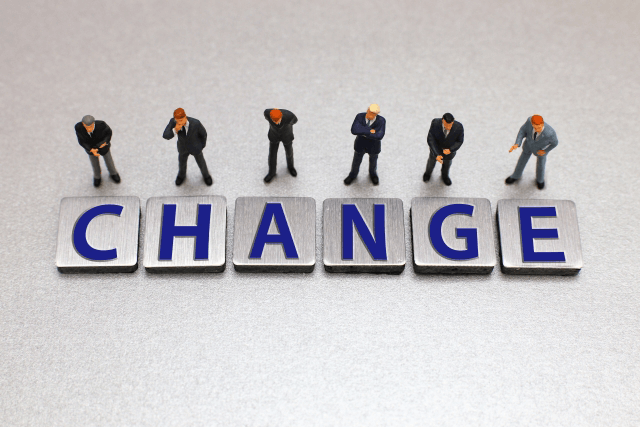●鎖国の中でモノを考える基礎をつくった江戸時代
長谷川 日本の政策を決めたりするときにも専門家が意見を述べますが、「どうしてそういう分析になったのか」ということはあまり問題にしないままなのか。有職者会議や専門家集団といったものが非常にたくさんあるにもかかわらず、それらは言っていることの「本質」をちゃんと説明してくれないような気がします。
小宮山 そうですね。あと私が思うのは、本当に社会を変えられると思っていないのではないかという気がします。例えば、グレタ・トゥーンベリさんですが、彼女はある種の天才と言っていいのではないかと思います。やはり変わると信じている。だって、確かに一人の力は小さいけれども、人類全体として未来を、例えば2050年に何度になるのか決めるのはやはり人間です。そうしたら、少し変わってくるのではないか。
そこで、私が思ったのはソビエトが崩壊した時のことで、あの頃に地球温暖化の問題が政治的に出てきました。本当かどうかは分からないけれども、ミッテランとサッチャーの2人が、「ソ連がなくなると敵がいなくなる」というので、まとまるための求心力を求めて温暖化問題を政治的イシューにしたのだと言う人がいます。
長谷川 次は環境問題だというふうにね。
小宮山 これは本当かもしれない。あの時、おそらく日本の政治家は「ソ連が駄目になって、これからどうなるのだろう」としか考えなかったと思う。「どうしよう。どうしていこうか」という思いには至っていないと思います。ここが、意外と日本の弱点というか。
明治維新のあと、「坂の上の雲」の時代があって素晴らしく前進した。戦後についての目的はもう明白で、だから奇跡の成長を遂げました。どちらも「なにをするか」の目的があった。だから、(日本は)力はあるけれども、自分でモデルを作っていない。
長谷川 そうですね。
明治維新の頃にどうやって日本が近代科学を取り入れたかということに関しては、JICA(国際協力機構)が留学生向けのコンテンツ(編注:シリーズ番組『日本の近代化を知る』)をつくった際に、だいぶ調べました。
明治維新より前の幕末の頃から、鎖国しているにもかかわらず西洋のものをずいぶん多量に取り入れています。日本のさまざまな地方(藩)で「これは大変なことだ」と思った人がたくさんいたわけです。例えば、細々と入ってくる蘭...