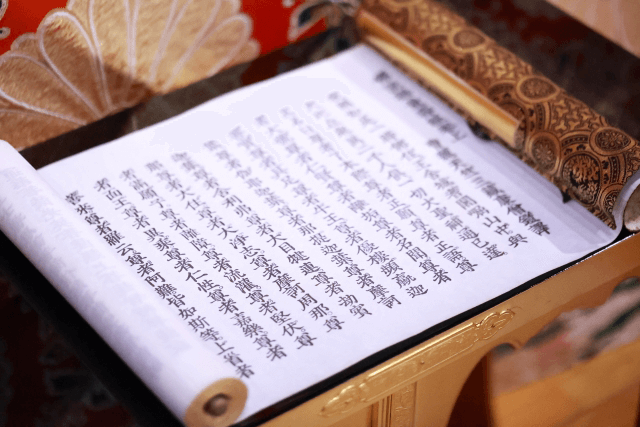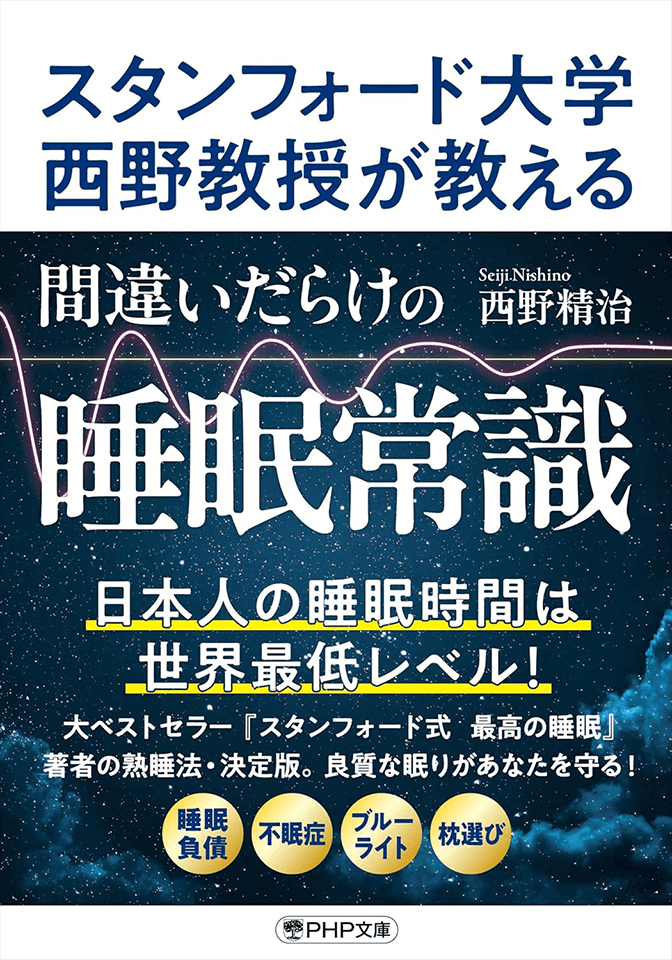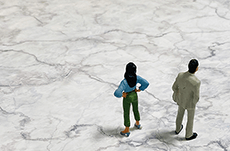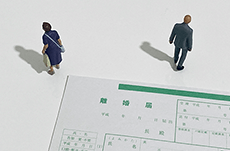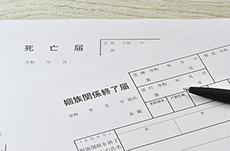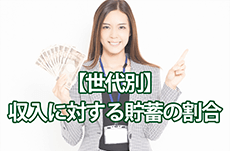社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

世の中の50代の平均貯蓄額は?
「人生100年時代」が現実化している現在、その折り返し地点である50歳という年齢に注目が集まっています。50歳といえば、『論語』では「知命」といわれる重要なマイルストーン。天が自分に与えた使命を自覚する年代と言われました。令和の現代、使命のあり方はきっと多様化していることでしょう。
同年代とはいえ、自分が生きて体験した時代状況によって預貯金に対する感覚が違うのは当然でしょう。しかも、非正規雇用の割合は、50歳台前半と重なる1968年~1972年生まれ以降の世代以降で高くなっています。
よくも悪くも世界や日本の景気動向に振り回されてきたのが50代のこれまでのようですが、りそな銀行のアンケートによると、すでに「老後を意識している」人が72%に上るといいます。さらに「老後資金を準備している」人も50%に達します。50代の貯蓄について、データを見てみましょう。
貯蓄額3,000万円以上というと、一部の富裕層だけでなく、早期退職金を支給された場合が考えられます。60代以降の世帯主を持つ家庭では、両端の数字が高く、真ん中が平らな傾向がより顕著になります。虎の子の退職金を大切に運用しようとする家庭と、いわゆる「高齢者貧困」の二極化です。その芽は50代ですでに明らかなことが分かります。
ちなみに、金融資産を保有する世帯に絞った50歳台世帯主の統計は、貯蓄の平均値が1,955万円、中央値が1,000万円となります。貯蓄額分布でも3,000万円以上が最多(15.9%)で、1,000~1,500万円未満(13.5%)が続きます。
2021年、日本全体で二人以上の世帯全体の貯蓄額は、平均値1,436万円、中央値650万円と発表されています。この数字を見て、「平均は1千万円以上でも、現実には600万円台の預貯金をしている世帯が多いようだ」と思われる方も多いでしょう。しかし、実際にはそうではありません。
全世代で最も多いのは金融資産を持たない「貯蓄ゼロ」世帯(16.1%)。ところが次に多いのが貯蓄3,000万円以上の世帯であるため、平均値は押し上げられているわけです。まさに、最近よく耳にする「貯蓄格差」が浮き彫りになった実態です。
実際、単身世帯の貯蓄はどうなっているでしょうか。まず、50代シングルで貯蓄ゼロの人は41%、20歳代シングルの43.2%につぐ多さです。この人たちも含めた50歳代シングルの貯蓄額は平均値924万円、中央値40万円となります。
単身世帯で貯蓄ゼロに続くのは貯蓄額100万円未満の層(10.4%)。ですが、その後に貯蓄額3,000万円以上の層(4.5%)がいるため、平均値が高くなるわけです。ちなみに、金融資産を保有する50代にしぼった統計は、貯蓄の平均値が1,601万円、中央値が622万円となっています。
ここで同年代の借入額も参照してみましょう。50歳台の世帯持ちで借入金があるのは56.1%、その平均額は1,316万円、中央値1,000万円です。一方、50歳台シングルで借入金があるのは19.7%。借入金の平均額は383万円、中央値は100万円ということで、借入額300万円未満が7割を占めています。
企業の定年は延長され、60代はもちろん70代になっても働ける職場も増えていますが、収入は50代で頭打ち。人生100年の折り返し地点で預貯金について見直してみるのも決して遅くありません。
バブル世代も就職氷河期もいる2021年の50代
2021年現在、50歳台といえば1960年代から1970年代初めに生まれた人々です。ひとくちに「50歳台」といっても60年代生まれは高度経済成長期を体験した「新人類」層。とくに1967~1970年生まれはバブル華やかな頃に就職した「バブル世代」。続く1970年代生まれは団塊ジュニア世代であるとともに、長く続く「就職氷河期世代」のはしりにも当たっています。同年代とはいえ、自分が生きて体験した時代状況によって預貯金に対する感覚が違うのは当然でしょう。しかも、非正規雇用の割合は、50歳台前半と重なる1968年~1972年生まれ以降の世代以降で高くなっています。
よくも悪くも世界や日本の景気動向に振り回されてきたのが50代のこれまでのようですが、りそな銀行のアンケートによると、すでに「老後を意識している」人が72%に上るといいます。さらに「老後資金を準備している」人も50%に達します。50代の貯蓄について、データを見てみましょう。
50代貯蓄の平均額1,684万円、中央値800万円の謎
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」(2020年)によれば、世帯主が50歳台の家庭では、貯蓄額の平均値1,684万円、中央値800万円となります。くわしく見ると、最も多い層は貯蓄額3,000万円以上の世帯(13.8%)、ついで貯蓄ゼロの世帯(13.3%)です。貯蓄額3,000万円以上というと、一部の富裕層だけでなく、早期退職金を支給された場合が考えられます。60代以降の世帯主を持つ家庭では、両端の数字が高く、真ん中が平らな傾向がより顕著になります。虎の子の退職金を大切に運用しようとする家庭と、いわゆる「高齢者貧困」の二極化です。その芽は50代ですでに明らかなことが分かります。
ちなみに、金融資産を保有する世帯に絞った50歳台世帯主の統計は、貯蓄の平均値が1,955万円、中央値が1,000万円となります。貯蓄額分布でも3,000万円以上が最多(15.9%)で、1,000~1,500万円未満(13.5%)が続きます。
2021年、日本全体で二人以上の世帯全体の貯蓄額は、平均値1,436万円、中央値650万円と発表されています。この数字を見て、「平均は1千万円以上でも、現実には600万円台の預貯金をしている世帯が多いようだ」と思われる方も多いでしょう。しかし、実際にはそうではありません。
全世代で最も多いのは金融資産を持たない「貯蓄ゼロ」世帯(16.1%)。ところが次に多いのが貯蓄3,000万円以上の世帯であるため、平均値は押し上げられているわけです。まさに、最近よく耳にする「貯蓄格差」が浮き彫りになった実態です。
50代シングルでは貯蓄ゼロが41%
人口統計資料集(2021)によると、1960年に男性1.26%女性1.88%だった「50歳時の未婚率」は、2015年に男性23.37%女性14.06%と急増しています。50歳時未婚は生涯シングルとも呼ばれますが、独身生活を謳歌するためには資金の後ろ盾がなくては始まりません。実際、単身世帯の貯蓄はどうなっているでしょうか。まず、50代シングルで貯蓄ゼロの人は41%、20歳代シングルの43.2%につぐ多さです。この人たちも含めた50歳代シングルの貯蓄額は平均値924万円、中央値40万円となります。
単身世帯で貯蓄ゼロに続くのは貯蓄額100万円未満の層(10.4%)。ですが、その後に貯蓄額3,000万円以上の層(4.5%)がいるため、平均値が高くなるわけです。ちなみに、金融資産を保有する50代にしぼった統計は、貯蓄の平均値が1,601万円、中央値が622万円となっています。
ここで同年代の借入額も参照してみましょう。50歳台の世帯持ちで借入金があるのは56.1%、その平均額は1,316万円、中央値1,000万円です。一方、50歳台シングルで借入金があるのは19.7%。借入金の平均額は383万円、中央値は100万円ということで、借入額300万円未満が7割を占めています。
企業の定年は延長され、60代はもちろん70代になっても働ける職場も増えていますが、収入は50代で頭打ち。人生100年の折り返し地点で預貯金について見直してみるのも決して遅くありません。
<参考サイト>
世の中の50代はいくら貯金している?老後の準備は?50代のお金事情│りそなグループ
https://www.resonabank.co.jp/kojin/shisan/column/kihon/column_0011.html
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和2年)│知るポルト
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/yoron/futari/2020/20bunruif001.html
人口統計資料集(2021)│国立社会保障・人口問題研究所
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2021.asp?fname=T06-23.htm
世の中の50代はいくら貯金している?老後の準備は?50代のお金事情│りそなグループ
https://www.resonabank.co.jp/kojin/shisan/column/kihon/column_0011.html
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和2年)│知るポルト
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/yoron/futari/2020/20bunruif001.html
人口統計資料集(2021)│国立社会保障・人口問題研究所
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2021.asp?fname=T06-23.htm
~最後までコラムを読んでくれた方へ~
雑学から一段上の「大人の教養」はいかがですか?
明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。
『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。
グリーンランドに米国の軍事拠点…北極圏の地政学的意味
地政学入門 ヨーロッパ編(10)グリーンランドと北極海
北極圏に位置する世界最大の島グリーンランド。ここはデンマークの領土なのだが、アメリカの軍事拠点でもあり、アメリカ、カナダとヨーロッパ、ロシアの間という地政学的にも重要な位置にある。また、気候変動によってその軍事...
収録日:2025/02/28
追加日:2025/07/07
陀羅尼品…あらゆるものが暗号であり、メタファーである
おもしろき『法華経』の世界(6)「陀羅尼品」とエニグマ
『法華経』下巻の「陀羅尼品」を読めば、それが真言宗の真言(=マントラ)と同様の構造を持っていることが分かる。天台教学における「諸法実相」や「本覚思想」という形而上学も、華厳経の「重々帝網」という次元世界も、全て...
収録日:2025/01/27
追加日:2025/07/06
なぜ思春期は大事なのか?コホート研究10年の成果に迫る
今どきの若者たちのからだ、心、社会(1)ライフヒストリーからみた思春期
なぜ思春期に注目するのか。この十年来、10歳だった子どもたちのその後を10年追跡する「コホート研究」を行っている長谷川氏。離乳後の子どもが性成熟しておとなになるための準備期間にあたるこの時期が、ヒトという生物のライ...
収録日:2024/11/27
追加日:2025/07/05
信用創造・預金創造とは?社会でお金が流通する仕組み
お金の回し方…日本の死蔵マネー活用法(1)銀行がお金を生む仕組み
日本経済が低迷する原因は何か。大きなポイントとして「お金が回っておらず、死蔵されてしまっていること」が挙げられる。そもそも、お金が市中にどのように流通し、どのような役割を果たしていくのかを理解しなければ、経済を...
収録日:2024/12/04
追加日:2025/02/22
昼寝が認知症予防に!?脳のグリンパティック・システムとは
睡眠と健康~その驚きの影響(3)グリンパティック・システムと脳の健康脳
近年の研究では睡眠に「脳の老廃物を除去する」働きがあることが分かってきた。脳に老廃物が溜まると、それが脳の神経組織に障害を与え、認知症(アルツハイマー)を発症するのだという。今回は、そうした「グリンパティック・...
収録日:2025/03/05
追加日:2025/06/19