テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
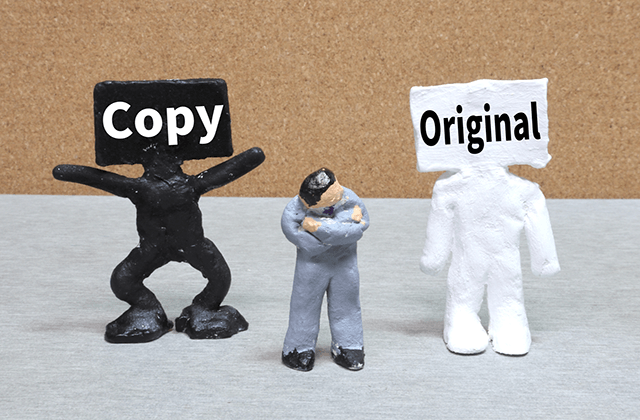
五輪エンブレム問題を考える
2020年東京オリンピック開催に向けて影がさすことになった「エンブレム騒動」。ベルギーのリエージュ劇場ロゴからの盗作との疑惑が浮上している今、盗作問題についての関心が高まっている。
「わかりやすさ」「つたわりやすさ」の観点から素朴な美しさを求められるロゴデザインの世界では、形に単純性が出れば出る程、丸や四角などの形のみで表現せざるを得なくなり、その分数多くのロゴのうちどれかと類似してしまうのは仕方のないことである。
今回問題となっている双方のデザインをみると、訴訟を起こされたとき、勝敗をどのように決められるのかが興味深い。そもそも、今回のデザインは「TOKYO」「TEAM」「TOMORROW」のTからイメージして作られたということで、あの図形全てをもってTとされる。
シアター・リエージュのTとLだけで説明がつくデザインに比例して一文字のみでLともとれる要素を入れてしまったというところも論点になりそうだ。
ではいったいどこからが盗作になりえるのだろうか。
音楽の領域では、旋律が似ている、リズムが似ているなどが判断材料となる。
ポップス・ロック・レゲエなど、ジャンルがあるものは、まず同ジャンル同士のものが似るのは当たり前のことだ。それでも違う曲ができるのは、似た要素の中から、どれだけのオリジナリティをだせるかというところだ。何小節まで同じだとアウト、というような、似ている部分の長さでも印象が大きく違ってくるだろう。
詩や小説など文芸の領域では、元にするものが同じだと似て来てしまう。神話、伝承といった古くから語り継がれているものから取ると、どれも同じ名前や設定になってしまうことがある。
しかし元となるものから作られた設定とさらに似ている場合、指摘される可能性がある。つまり、最近のものからとればとるほど、同じだと見なされてしまうのである。
詩は音楽の「作詞」の部分と同じでフレーズの持つ語感とリズムが争点となってくるだろう。
無意識に、どこかで聞いたことがあって、それが頭の中に残っていて作られてしまったため、「盗んだ」という意識がないという話はよくある。またこれと似ているだろうか、と様々な例を探し出したら枚挙にいとまがない。
このようなコラムも同じ、扱うニュース、源が同じならば同じような記事ができあがってしまうが、大切なのは人が不快に思わないための配慮と、自分の意見を少しでも取り入れることなのではないだろうか。
作り手としても似ているものをあらかじめ把握するのは至難の業だが、多くの「見る」人がこれは似ていると思う気持ちを止めることもできない。だとすれば、提供する側もこれを無視することはできないだろう。
「作る側」と「見る側」、双方が誠実さを持って対応することが大切なのではないだろうか。
「わかりやすさ」「つたわりやすさ」の観点から素朴な美しさを求められるロゴデザインの世界では、形に単純性が出れば出る程、丸や四角などの形のみで表現せざるを得なくなり、その分数多くのロゴのうちどれかと類似してしまうのは仕方のないことである。
今回問題となっている双方のデザインをみると、訴訟を起こされたとき、勝敗をどのように決められるのかが興味深い。そもそも、今回のデザインは「TOKYO」「TEAM」「TOMORROW」のTからイメージして作られたということで、あの図形全てをもってTとされる。
シアター・リエージュのTとLだけで説明がつくデザインに比例して一文字のみでLともとれる要素を入れてしまったというところも論点になりそうだ。
ではいったいどこからが盗作になりえるのだろうか。
音楽の領域では、旋律が似ている、リズムが似ているなどが判断材料となる。
ポップス・ロック・レゲエなど、ジャンルがあるものは、まず同ジャンル同士のものが似るのは当たり前のことだ。それでも違う曲ができるのは、似た要素の中から、どれだけのオリジナリティをだせるかというところだ。何小節まで同じだとアウト、というような、似ている部分の長さでも印象が大きく違ってくるだろう。
詩や小説など文芸の領域では、元にするものが同じだと似て来てしまう。神話、伝承といった古くから語り継がれているものから取ると、どれも同じ名前や設定になってしまうことがある。
しかし元となるものから作られた設定とさらに似ている場合、指摘される可能性がある。つまり、最近のものからとればとるほど、同じだと見なされてしまうのである。
詩は音楽の「作詞」の部分と同じでフレーズの持つ語感とリズムが争点となってくるだろう。
無意識に、どこかで聞いたことがあって、それが頭の中に残っていて作られてしまったため、「盗んだ」という意識がないという話はよくある。またこれと似ているだろうか、と様々な例を探し出したら枚挙にいとまがない。
このようなコラムも同じ、扱うニュース、源が同じならば同じような記事ができあがってしまうが、大切なのは人が不快に思わないための配慮と、自分の意見を少しでも取り入れることなのではないだろうか。
作り手としても似ているものをあらかじめ把握するのは至難の業だが、多くの「見る」人がこれは似ていると思う気持ちを止めることもできない。だとすれば、提供する側もこれを無視することはできないだろう。
「作る側」と「見る側」、双方が誠実さを持って対応することが大切なのではないだろうか。
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










