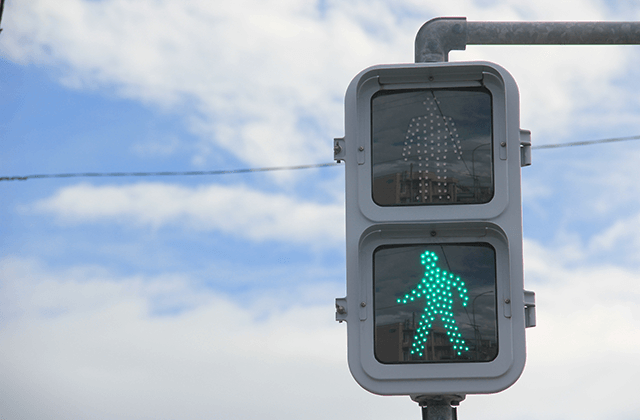
『かたちには理由がある』に学ぶデザインの「素敵な妥協」
歩くときにスマホの画面ばかり見ていると、見落としているものは思いの外たくさんあります。たとえば信号機の新しいデザインもその一つ。1994年以来LEDが使用されるようになり、現在、東京都の車両用LED信号機普及率は100%。このデザインに携わった秋田道夫氏の『かたちには理由がある』(早川書房)を読めば、何がどう変わったのかだけでなく、プロダクトデザイナーは何をどう考えているのかが手に取るように伝わってきます。本書全体で140ページという「薄型」のなかに詰まった発想のヒントの数々は、忙しいなかでも読書から何かを学びとりたい方にぜひお勧めしたい一冊です。
それまでデザインの手が入らなかった信号機の会社から秋田氏に声がかかったのは、信号機を見て子どものように目を輝かせていた姿が「信号好き」を印象づけ、さらにちょっとしたスケッチがソニー製品の匂いを残していたのがきっかけだといいます。
とはいえ、信号機はとても規制が多く、灯器の寸法もパネル部のサイズもあらかじめ決められていて、その間隔も決まっています。パッと見て「やりようがない」と感じた秋田氏は、逆に「やりようがないものをデザインする」のがプロダクトデザインの面白さだと一念発起。「要素を減らすこと」と「背面のデザイン」をポイントとして、デザインの力を最大限に発揮していきました。
完成した信号機は他社製のものと比べて明らかに違うというわけではありません。「なんでもない」のに「美しい」。その塩梅にかけるのが、秋田氏の美学です。
作品に共通しているのは、秋田氏の言う「研ぎ澄まされたふつうさ」。その秘密は、直線は直線、円は円という基本の「かたち」を大切にしているところにあるのが、本書の記述から伝わります。
秋田信夫氏は、1953年生まれ。トリオ(現JVCケンウッド)を振り出しにソニーのインハウスデザイナーを務め、今年(2023年)70歳になる現在はプロダクトデザイナーとしてフリーランスで活躍しています。2年前に始めたtwitter(現X)も好評で、フォロワーは10万人以上。たとえば「わたしが幸せなのは中途半端だからだと思っています」「一番大切な事は相手への敬意です」といったつぶやきが、現代人の気持ちに寄り添うのでしょう。著書の『機嫌のデザイン』(ダイヤモンド社)では、日常生活はもちろん機嫌も自分でデザインできるとして、専門外の方にも多くのファンを増やしています。
60代を超えると若い頃よりも頑固になりがちな方が多いなか、秋田氏の笑顔は肩の力がいいぐらいに抜けたように感じられて、いかにも「いいご機嫌」そのもの。かたちをめぐる思考を中心とした本書でも、「デザインとは『素敵な妥協』をすること」「大量に使われる商品は『研ぎ澄まされたふつう』でなければならない」などの名言が、デザインにこれまで興味のなかった人の気持ちをつかみ、次を読ませるページターナーになっています。
本書では、毎日使うスプーンやフォークなどのカトラリーのデザインを通して、「これは、本当にほしいか。長く使っていても飽きのこないかたちか」を追究すると、「最初に考えていた斬新なかたちでは耐えられない」と悟ったてんまつが書かれています。本気で使い勝手を比べることで、「すでにありそうな形状でありながら、そうでないもの」が生まれていくのだそうです。
日々使う大切な道具でありながら、カトラリー選びにデザインを第一優先する人は意外に少なく、「だれかにプレゼントされた」「ブランドが気になった」など、なんとなく選んでしまい、道具に慣れていく人が多いかもしれません。しかし、「美術館に飾ると美術品のようだし、家庭のキッチンに置くと道具である」ということで、“民藝”の創始者・柳宗悦の思想に通じる秋田氏のデザインを手に取ってみたくなる人も多いでしょう。
「ある程度鋭さを持ったデザインにしておく」ことで、使うときにも「少し緊張感が出る」という効果があり、ゆるいデザインだと逆に「雑に扱われて、危険が増すことも」ある、と秋田氏。それは日常のおしゃれにも応用できることです。「普段着とよそ行きを分けず」、いつも出会う人へのプレゼントとして日々のおしゃれを大切にする人こそ、相手にちょっとした緊張感を与え、結果的に相手から大切にしてもらえるのかもしれません。
同様の緊張感は、信号機など公共の機器にも必要。そこからこそ「素敵な妥協」に満ちた街の風景が広がっていくのではないでしょうか。
信号機が新しくなっている理由
LED薄型歩行者灯器(信号機の正式名称)は、著者の秋田氏の代名詞にもなっているものですが、信号機にもデザインがあったのかと驚かれた方も多いのではないでしょうか。じつはご本人も初めて信号機の製造会社を訪ねたとき、「日頃見慣れているはずの信号機が、間近に見るとこんなに大きいものか」と単純に驚き、感動を覚えたと打ち明けています。それまでデザインの手が入らなかった信号機の会社から秋田氏に声がかかったのは、信号機を見て子どものように目を輝かせていた姿が「信号好き」を印象づけ、さらにちょっとしたスケッチがソニー製品の匂いを残していたのがきっかけだといいます。
とはいえ、信号機はとても規制が多く、灯器の寸法もパネル部のサイズもあらかじめ決められていて、その間隔も決まっています。パッと見て「やりようがない」と感じた秋田氏は、逆に「やりようがないものをデザインする」のがプロダクトデザインの面白さだと一念発起。「要素を減らすこと」と「背面のデザイン」をポイントとして、デザインの力を最大限に発揮していきました。
完成した信号機は他社製のものと比べて明らかに違うというわけではありません。「なんでもない」のに「美しい」。その塩梅にかけるのが、秋田氏の美学です。
「機嫌」もデザイン!フォロワー10万人以上の秋田氏
本書を開くと、最初に目に飛び込んでくるのは8ページにわたるグラビア。そこで、秋田氏の作品が出迎えてくれます。作品はもちろん信号機だけではなく、交通系カードチャージ機や虎ノ門ヒルズなどのセキュリティゲートといった公共機器から「一本用ワインセラー」「革製トートバッグ」などの日用品も幅広く手掛けています。作品に共通しているのは、秋田氏の言う「研ぎ澄まされたふつうさ」。その秘密は、直線は直線、円は円という基本の「かたち」を大切にしているところにあるのが、本書の記述から伝わります。
秋田信夫氏は、1953年生まれ。トリオ(現JVCケンウッド)を振り出しにソニーのインハウスデザイナーを務め、今年(2023年)70歳になる現在はプロダクトデザイナーとしてフリーランスで活躍しています。2年前に始めたtwitter(現X)も好評で、フォロワーは10万人以上。たとえば「わたしが幸せなのは中途半端だからだと思っています」「一番大切な事は相手への敬意です」といったつぶやきが、現代人の気持ちに寄り添うのでしょう。著書の『機嫌のデザイン』(ダイヤモンド社)では、日常生活はもちろん機嫌も自分でデザインできるとして、専門外の方にも多くのファンを増やしています。
60代を超えると若い頃よりも頑固になりがちな方が多いなか、秋田氏の笑顔は肩の力がいいぐらいに抜けたように感じられて、いかにも「いいご機嫌」そのもの。かたちをめぐる思考を中心とした本書でも、「デザインとは『素敵な妥協』をすること」「大量に使われる商品は『研ぎ澄まされたふつう』でなければならない」などの名言が、デザインにこれまで興味のなかった人の気持ちをつかみ、次を読ませるページターナーになっています。
毎日使うものに必要な条件とは
秋田氏が自分の機嫌までデザインできるようになったのは、インハウスデザイナーとして二社を経験した後、独立したという経歴にも関係があります。プロダクトデザイナーが直面するのは、素材の「わがまま」やメーカーによる製造工程やコストの「しばり」、さらに機能性や時代の流行など、さまざまの制約です。それらに対して「素敵な妥協」をすることで、むしろ素材の長所を活かせたり、時代の特徴を際立たせたりしてきた経験が、秋田氏のデザインを「研ぎ澄まされたふつう」に成長させてきました。本書では、毎日使うスプーンやフォークなどのカトラリーのデザインを通して、「これは、本当にほしいか。長く使っていても飽きのこないかたちか」を追究すると、「最初に考えていた斬新なかたちでは耐えられない」と悟ったてんまつが書かれています。本気で使い勝手を比べることで、「すでにありそうな形状でありながら、そうでないもの」が生まれていくのだそうです。
日々使う大切な道具でありながら、カトラリー選びにデザインを第一優先する人は意外に少なく、「だれかにプレゼントされた」「ブランドが気になった」など、なんとなく選んでしまい、道具に慣れていく人が多いかもしれません。しかし、「美術館に飾ると美術品のようだし、家庭のキッチンに置くと道具である」ということで、“民藝”の創始者・柳宗悦の思想に通じる秋田氏のデザインを手に取ってみたくなる人も多いでしょう。
だから「かたち」には理由がある
秋田氏は、「観察はデザインに勝る」という持論を説明するのに、〈「なぜ、これはこういうかたちなんだろう?」「こういうかたちにするには難しい事情が何かあるのかな?」と観察してみれば、日常の風景がこれまでとは違って見えるに違いない。それは感性を磨きながら日々を過ごすための有効な楽しみになる〉と語りかけます。「ある程度鋭さを持ったデザインにしておく」ことで、使うときにも「少し緊張感が出る」という効果があり、ゆるいデザインだと逆に「雑に扱われて、危険が増すことも」ある、と秋田氏。それは日常のおしゃれにも応用できることです。「普段着とよそ行きを分けず」、いつも出会う人へのプレゼントとして日々のおしゃれを大切にする人こそ、相手にちょっとした緊張感を与え、結果的に相手から大切にしてもらえるのかもしれません。
同様の緊張感は、信号機など公共の機器にも必要。そこからこそ「素敵な妥協」に満ちた街の風景が広がっていくのではないでしょうか。
<参考文献>
『かたちには理由がある』(秋田道夫著、早川書房)
https://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000015535/
<参考サイト>
秋田道夫氏のツイッター
https://twitter.com/kotobakatachi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
『かたちには理由がある』(秋田道夫著、早川書房)
https://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000015535/
<参考サイト>
秋田道夫氏のツイッター
https://twitter.com/kotobakatachi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子







