テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
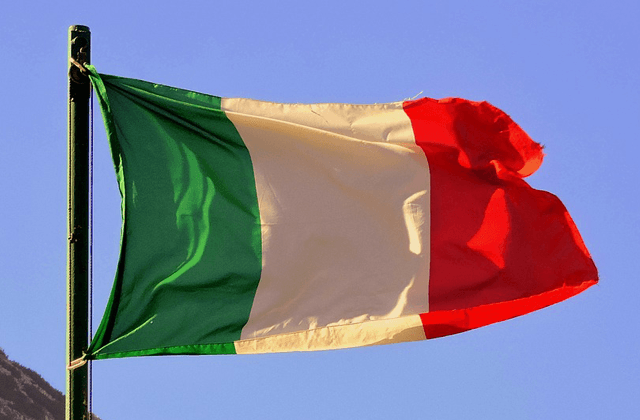
イタリアの国民投票から日本は何を学ぶか
2016年12月4日のイタリア国民投票は、憲法改正に対する反対票が賛成票を上回り、否決されました。マッテオ・レンツィ首相(当時)は、その結果を受けて引責辞任するという幕切れになったのです。イタリア国民投票では、なぜレンツィ氏は「政権を賭ける」必要があったのでしょうか。その点を疑問視しながらも、政権と無関係のものとして淡々と行えるほど国民投票は甘くないと論じるのが政治学者で慶應義塾大学大学院教授の曽根泰教氏です。
曽根氏がまず指摘するのは、国民投票という手法の怖さです。憲法改正の論議に長く関わってきた中山太郎氏(元衆議院議員)は、その怖さを猛獣にたとえ、「猛獣使いはまだ出ていない」と言ったほど。日本では、2015年に「大阪維新の会」代表の橋下徹大阪市長(当時)が「大阪都構想」について住民投票を行った前例がある程度なので、そのハードルの高さについて誰も認識できていないのでしょう。
国民投票の怖さとは、「国論を二分」してしまうところです。これはアメリカの大統領選挙にも通じます。イギリスのBREXITが労働党にも保守党にも多大なダメージを与えたように、トランプ大統領の選出は民主党と共和党の両方を破壊したと曽根氏は見ています。
これは、日本にも参考になることの多い「統治構造改革」です。他にも「州・県・市町村」と3段階になっている地方政治を、「州・市町村」にスリム化する案が盛り込まれた憲法改正案は、上下両院で認められていました。ところが、国民投票では「NO」という答えを付きつけられました。それはなぜだったのでしょうか。
原因は政治や政権に対する不満が、国民投票に影を落としたことだと曽根氏は言います。厳しい国内の経済情勢に加え、ヨーロッパ全体が抱える「移民・難民」の問題。そして、EUとの関係。今、イタリア国内では既存政治への不信感が爆発寸前の状態といえるのかもしれません。
金融システム不安がイタリアからヨーロッパ全体に増幅されていけば、欧州危機再燃の危険にさらされます。イギリスのEU離脱決定で経済の先行き不透明感が強まっているヨーロッパ。今年2017年にはフランスやドイツの大型選挙も控えています。憲法改正をめぐるイタリア国民投票によって一気に明るみに出されたグローバル時代の政治基盤の危うさを、見極める年になりそうです。
イタリア国民投票で政権崩壊、その怖さとは
この問題はイタリア固有の政治問題にとどまらない。ヨーロッパはもちろん日本にも影響のある重要な政治イシューだ、と考える曽根氏は、イタリア国民投票を四つの階層で分析します。国民投票そのものの問題点、憲法改正の内容、イタリアの現在の政治状況、さらにヨーロッパ政治への影響です。曽根氏がまず指摘するのは、国民投票という手法の怖さです。憲法改正の論議に長く関わってきた中山太郎氏(元衆議院議員)は、その怖さを猛獣にたとえ、「猛獣使いはまだ出ていない」と言ったほど。日本では、2015年に「大阪維新の会」代表の橋下徹大阪市長(当時)が「大阪都構想」について住民投票を行った前例がある程度なので、そのハードルの高さについて誰も認識できていないのでしょう。
国民投票の怖さとは、「国論を二分」してしまうところです。これはアメリカの大統領選挙にも通じます。イギリスのBREXITが労働党にも保守党にも多大なダメージを与えたように、トランプ大統領の選出は民主党と共和党の両方を破壊したと曽根氏は見ています。
日本が学ぶべきなのは、「憲法改正」の内容である
では、イタリア国民投票が問うた「憲法改正」の内容とはどんなものだったのでしょうか。レンツィ政権が目指したのは、イタリアが苦しんできた「決められない政治」からの脱却です。そのため、ほぼ対等の立場にある二院制のうち上院の権限を減らし、議決権を下院に集中させようとするのが、今回の憲法改正案の主旨でした。これは、日本にも参考になることの多い「統治構造改革」です。他にも「州・県・市町村」と3段階になっている地方政治を、「州・市町村」にスリム化する案が盛り込まれた憲法改正案は、上下両院で認められていました。ところが、国民投票では「NO」という答えを付きつけられました。それはなぜだったのでしょうか。
原因は政治や政権に対する不満が、国民投票に影を落としたことだと曽根氏は言います。厳しい国内の経済情勢に加え、ヨーロッパ全体が抱える「移民・難民」の問題。そして、EUとの関係。今、イタリア国内では既存政治への不信感が爆発寸前の状態といえるのかもしれません。
政治不信のイタリア国内、激動するヨーロッパ政治
イタリア国内では、元コメディアンのベッペ・グリッロ氏が立ち上げた「五つ星運動」が人気を集め、既存政党を圧迫しています。さらに、EUとの関係をどう保つかについても、レンツィ政権はほぼ孤立した状態に置かれていたのは事実です。しかし、レンツィ氏が進めてきた構造改革路線がストップすることは、銀行の不良債権問題にも飛び火しかねません。パオロ・ジェンティローニ新首相にとっても頭の痛いところですが、この問題はイタリア一国では収まりそうにありません。金融システム不安がイタリアからヨーロッパ全体に増幅されていけば、欧州危機再燃の危険にさらされます。イギリスのEU離脱決定で経済の先行き不透明感が強まっているヨーロッパ。今年2017年にはフランスやドイツの大型選挙も控えています。憲法改正をめぐるイタリア国民投票によって一気に明るみに出されたグローバル時代の政治基盤の危うさを、見極める年になりそうです。
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子










