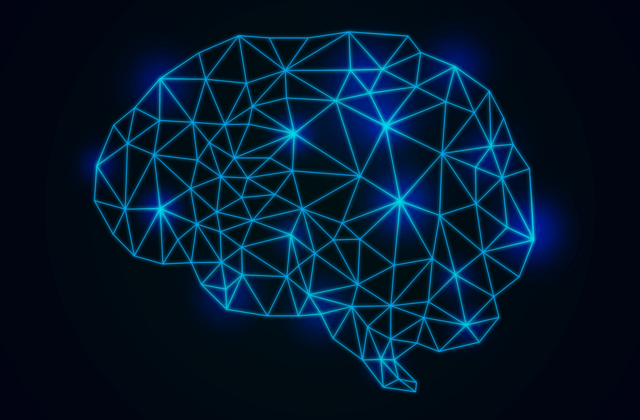
目を持ったロボットのビジネスが日本企業に有利な理由
今のAI(人工知能)ブームのなかでも、特に注目を集めているのが「ディープラーニング」です。ディープラーニングとは、コンピューターが自らどんどん学習を深めていく技術で、今後のAIには欠かせないものです。日本において、そのAI研究の第一人者が東京大学大学院特任准教授・松尾豊氏です。
松尾氏によれば、現在はディープラーニングによって、画像認識の性能が急速に伸びており、ほどなく「目を持った機械・ロボット」ができると言います。この機械・ロボットは、目の前の物体がどのように移動するかを予測したり、自分の行動によって何がどのように移動・変化するかを予測したりします。たとえば、現在の工業用の機械・ロボットは目がありませんから、ある場所に固定され、一定の作業を行うにとどまっていますが、目のついた機械・ロボットなら、自ら移動してさまざまな作業をこなせるようになります。目を持った機械・ロボットには、大きな可能性があるのです。
松尾氏は、こうした目を持った機械・ロボットのビジネスは、日本企業に有利だと言います。いったいなぜでしょうか?
次の段階として、「機械・ロボットが一度普及すれば、機能やサービスに対して課金していくビジネスモデルにすぐ移行できます」と松尾氏は語ります。たとえば、トマト収穫ロボットなら、トマトのサイズ・品質・病気の有無などを判別する機能、自動溶接機械なら溶接面のチェック機能、皿洗いロボットなら皿の枚数を数える機能や残飯処理機能などに課金していくのです。
さらに次は、「ロボットでトマト畑全体の栽培管理ができるようになるでしょう。トマト畑全体を担うロボットプラットフォームが少しずつ実現されてくるはずです。建設業界でも、溶接だけでなく、コンクリートの流し込みといったさまざまな工程をロボットが行えるようになるでしょうし、食品加工の現場でも、お皿の管理から食材の管理、そしていずれは調理までロボットが担当するようになり、最終的には飲食店のバックヤードは全て機械が行うでしょう」と、松尾氏は言います。
つまり、最終的には、農業や建設業や食品加工業の全工程を機械・ロボットが行うようになるということです。もちろん、それ以外の業界でも、目を持った機械・ロボットが普及していくでしょう。
しかし一方で、日本には労働人口の減少という大問題があります。農業・建設業・食品加工業を中心に、すでに人材不足が顕著になってきているのです。その証拠に、農業では耕作放棄地が全国でどんどん増えていますし、建設業では人手不足のために工期遅れや費用高騰などの問題が起こっています。食品加工業や飲食業では、従業員が少ないために店舗を閉める企業が出てきています。目を持った機械・ロボットは、こうした問題を一気に解決できるかもしれないのです。
雇用の問題さえ解決できれば、目を持った機械・ロボットは、日本にとってさまざまな意味でポジティブな成果をもたらす可能性があります。今後、注目し続けたい分野の1つです。
松尾氏によれば、現在はディープラーニングによって、画像認識の性能が急速に伸びており、ほどなく「目を持った機械・ロボット」ができると言います。この機械・ロボットは、目の前の物体がどのように移動するかを予測したり、自分の行動によって何がどのように移動・変化するかを予測したりします。たとえば、現在の工業用の機械・ロボットは目がありませんから、ある場所に固定され、一定の作業を行うにとどまっていますが、目のついた機械・ロボットなら、自ら移動してさまざまな作業をこなせるようになります。目を持った機械・ロボットには、大きな可能性があるのです。
松尾氏は、こうした目を持った機械・ロボットのビジネスは、日本企業に有利だと言います。いったいなぜでしょうか?
日本が世界のプラットフォームを握ることができるかもしれない
目を持った機械・ロボットのビジネスがなぜ日本企業に有利かといえば、それは簡単に言えば、ものづくりが知識集約型ビジネスだからです。ものづくりは、ITビジネスなどとは違って物流の問題がありますから、工場や研究所をある程度近いところにまとめたほうがいろいろと便利なのです。そのため、ものづくりが強い日本には、今も数多くの工場や研究所が集まっています。日本の機械・ロボットメーカーには、それらの工場や研究所にいち早く最新型の機械・ロボットを導入し、発展させていく大きなチャンスがあるのです。このチャンスを生かせば、日本の機械・ロボットメーカーが世界のライバルよりも早く技術力を高め、日本発の技術をグローバルに展開していき、最終的には「ものを起点にして、日本が世界のプラットフォームを握ることができるかもしれません」(松尾氏)。農業・建設業・食品加工業の自動化が進むだろう
ところで、目を持った機械・ロボットができたら、いったいどのような変化が起こるのでしょうか。松尾氏は、「僕の予想では、農業や建設業や食品加工業向けの機械・ロボットが次々に生まれると思っています」と語っています。もう少し具体的にいえば、農業ならトマト収穫ロボット、建設業なら自動溶接機械、食品加工業なら食洗器にお皿を入れる作業を行うロボットが最初にできるのではないかと、松尾氏は予測しています。いずれも目がついたからこそできる作業です。次の段階として、「機械・ロボットが一度普及すれば、機能やサービスに対して課金していくビジネスモデルにすぐ移行できます」と松尾氏は語ります。たとえば、トマト収穫ロボットなら、トマトのサイズ・品質・病気の有無などを判別する機能、自動溶接機械なら溶接面のチェック機能、皿洗いロボットなら皿の枚数を数える機能や残飯処理機能などに課金していくのです。
さらに次は、「ロボットでトマト畑全体の栽培管理ができるようになるでしょう。トマト畑全体を担うロボットプラットフォームが少しずつ実現されてくるはずです。建設業界でも、溶接だけでなく、コンクリートの流し込みといったさまざまな工程をロボットが行えるようになるでしょうし、食品加工の現場でも、お皿の管理から食材の管理、そしていずれは調理までロボットが担当するようになり、最終的には飲食店のバックヤードは全て機械が行うでしょう」と、松尾氏は言います。
つまり、最終的には、農業や建設業や食品加工業の全工程を機械・ロボットが行うようになるということです。もちろん、それ以外の業界でも、目を持った機械・ロボットが普及していくでしょう。
目を持った機械・ロボットが日本の労働人口減少問題を解決するかもしれない
こうした話をすると、「いよいよ本当に、ロボットに仕事が奪われるのではないか」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。確かに、一面ではその予測は間違っていません。目を持った機械・ロボットが本格的に普及すれば、数多くの仕事がなくなるでしょう。この問題を解決する必要は確かにあります。しかし一方で、日本には労働人口の減少という大問題があります。農業・建設業・食品加工業を中心に、すでに人材不足が顕著になってきているのです。その証拠に、農業では耕作放棄地が全国でどんどん増えていますし、建設業では人手不足のために工期遅れや費用高騰などの問題が起こっています。食品加工業や飲食業では、従業員が少ないために店舗を閉める企業が出てきています。目を持った機械・ロボットは、こうした問題を一気に解決できるかもしれないのです。
雇用の問題さえ解決できれば、目を持った機械・ロボットは、日本にとってさまざまな意味でポジティブな成果をもたらす可能性があります。今後、注目し続けたい分野の1つです。
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







