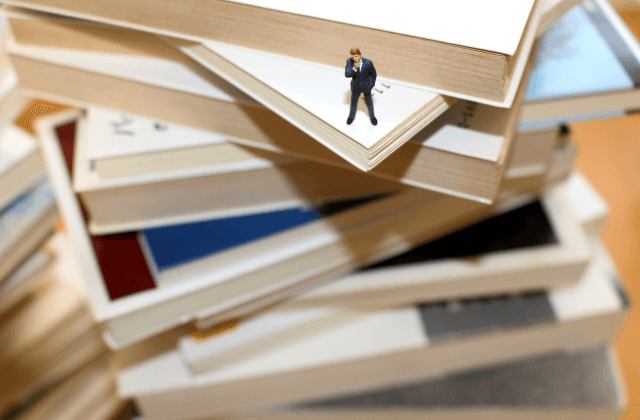
「教養」を身につけるための3つのポイント
人生100年時代と言われる今、生涯教育、つまり一生を通して学び続けることの意味が問われる機会も増えてきました。生涯教育といっても、それはなにも専門性をもった分野を追究することとは限りません。いわゆる「教養」と言われるものを身につけるのも、その第一歩と言えるのではないでしょうか。
しかし、改めて「教養を身につけるには」と考えるとどうしたらよいのか迷ってしまいます。そのような疑問に、東京大学名誉教授の本村凌二氏がアドバイスを送ります。
「教養」と深く関わってきた本村氏が、教養を身につけるために一番大切と考えるポイントは三つ。その一つ目が世界史です。高校の授業では、世界史、日本史と区別しているかもしれませんが、ここで本村氏が「世界史」というのは、日本史も含めた人類の歴史全体のこと、人類が経験してきたことの集積としての歴史です。
一人の人間が自分の経験として実感できることは、親世代の経験を多少含んだとしてもたかだか100年程度。しかし、歴史に学べば5000年以上にわたる文明から数限りない知恵を手にすることができます。いわば、歴史は人類の偉大な教科書というわけで、その意味において、世界史は教養の非常に重要なファクターだと本村氏は断言します。
また、古典とは文学作品に限るものではなく、その一例として本村氏はマルクスの『資本論』を挙げます。そのすべての主張に賛成するわけではないが、資本主義社会の構造分析をするにあたって、古典的名著であることに違いないと言います。そのように考えると、国民国家のあり方を考えるうえで欠かせないホッブスの『リヴァイアサン』、戦争を政治的戦略の観点から論じたクラウゼヴィッツの『戦争論』なども、文学とは毛色の異なる「古典」的名著と言えそうです。
実は本村氏は専門の古代ローマ史関連の著作だけではなく、昭和の大スター石原裕次郎や趣味である競馬を素材に『裕次郎』『馬の世界史』といった本も書いています。いずれも歴史家の目を通して綴ったもので、単に知識として「へぇ、そんなこともあったんだ」と感心させるレベルで終わらせない、まさに雑学の王道の一つのあり方だと思います。
こうしてみると、歴史や古典を通して学んだことが、さまざまな分野で結びつき、意外な関係線をひいて新たな知的発見につながるのではないかと思います。いわば、知識を真の教養に高めてくれるのが、世界史、古典、雑学だと言えるのではないでしょうか。生涯教育の醍醐味を味わうためにも、この三つを心にとめておきましょう。
しかし、改めて「教養を身につけるには」と考えるとどうしたらよいのか迷ってしまいます。そのような疑問に、東京大学名誉教授の本村凌二氏がアドバイスを送ります。
一つ目のポイントは「世界史を学ぶ」
2018年3月で定年退職された本村氏は、35年近く古代ローマ史を専門として、大学で教鞭をとってきましたが、今まで勤めてきた大学では、いずれも「教養学部」と名前のつくところで教えてきたそうです。「教養」と深く関わってきた本村氏が、教養を身につけるために一番大切と考えるポイントは三つ。その一つ目が世界史です。高校の授業では、世界史、日本史と区別しているかもしれませんが、ここで本村氏が「世界史」というのは、日本史も含めた人類の歴史全体のこと、人類が経験してきたことの集積としての歴史です。
一人の人間が自分の経験として実感できることは、親世代の経験を多少含んだとしてもたかだか100年程度。しかし、歴史に学べば5000年以上にわたる文明から数限りない知恵を手にすることができます。いわば、歴史は人類の偉大な教科書というわけで、その意味において、世界史は教養の非常に重要なファクターだと本村氏は断言します。
古今東西、さまざまな古典を読む
二つ目のポイントは古典を読むこと。古典というと、ギリシャ、ローマの哲学者や歴史家の書物や中国の『史記』『三国志』、あるいは平安時代の王朝文学を思い浮かべるかもしれません。しかし、本村氏は20世紀には20世紀なりの、19世紀には19世紀の古典があると言います。古代ギリシャの一大叙事詩『オデュッセイア』やイギリス・ルネサンスを代表する16世紀のシェイクスピア作品だけでなく、19世紀の『戦争と平和』や『カラマーゾフの兄弟』のように、多くの人によって長いこと読み継がれてきたものは、どれも「古典」としての価値を持っているのです。また、古典とは文学作品に限るものではなく、その一例として本村氏はマルクスの『資本論』を挙げます。そのすべての主張に賛成するわけではないが、資本主義社会の構造分析をするにあたって、古典的名著であることに違いないと言います。そのように考えると、国民国家のあり方を考えるうえで欠かせないホッブスの『リヴァイアサン』、戦争を政治的戦略の観点から論じたクラウゼヴィッツの『戦争論』なども、文学とは毛色の異なる「古典」的名著と言えそうです。
仕上げは「雑学のすすめ」
生涯教育を目指し、教養を身につけるための最後のポイントとして本村氏が示すのは「雑学」のすすめ。何度も同じことを繰り返してレベルアップしていく運動や楽器の練習とは違って、こと学びに関しては視野を広げないと山の高みには登れないというわけです。私たちは、学問をしようという時、えてして特定の分野に限ってそこだけに集中すればよいと考えがちです。ですが、本村氏は知的作業のすそ野を広げて、関連した学問や教養を雑学的に身につけることこそが、高みにのぼっていく秘訣なのだと言います。実は本村氏は専門の古代ローマ史関連の著作だけではなく、昭和の大スター石原裕次郎や趣味である競馬を素材に『裕次郎』『馬の世界史』といった本も書いています。いずれも歴史家の目を通して綴ったもので、単に知識として「へぇ、そんなこともあったんだ」と感心させるレベルで終わらせない、まさに雑学の王道の一つのあり方だと思います。
こうしてみると、歴史や古典を通して学んだことが、さまざまな分野で結びつき、意外な関係線をひいて新たな知的発見につながるのではないかと思います。いわば、知識を真の教養に高めてくれるのが、世界史、古典、雑学だと言えるのではないでしょうか。生涯教育の醍醐味を味わうためにも、この三つを心にとめておきましょう。
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







