テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
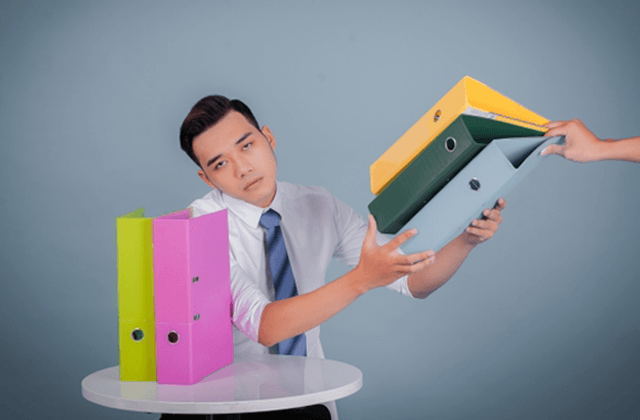
アジアでの日本人の出世意欲が「最低」な理由
2019年8月、総合人材サービスを展開するパーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームのパーソル総合研究所が、アジア太平洋地域(APAC)14の国・地域のビジネスパーソンを対象に実施した、就業実態・成長意識についてのインターネット調査結果「APACの就業実態・成長意識調査(2019年)」(以下「調査」)を発表しました。
そのうえでパーソル総合研究所は、いくつかのトピックスにおける各国の比較分析の実施と公表をもって、「日本だけ“一人負け”といってよい特異な数字が出た調査結果となった」と、極めて厳しい分析コメントを発表しています。
では日本のビジネスパーソンは、アジアにおいてどのようなトピックスで“一人負け”を喫し、どんな状況に陥っているのでしょうか。調査結果を見ながら、考察してみたいと思います。
なお調査対象の詳細は、1)中国(北京、上海、広州)、2)韓国(ソウル)、3)台湾(台北)、4)香港、5)タイ(バンコク)、6)フィリピン(メトロマニラ)、7)インドネシア(ジャカルタ)、8)マレーシア(クアラルンプール)、9)シンガポール、10)ベトナム(ハノイ、ホーチミンシティ)、11)インド(デリー、ムンバイ)、12)オーストラリア(シドニー、メルボルン)、13)ニュージーランド、14)日本(東京・大阪・愛知)――の14の国・地域における主要都市のビジネスパーソンです。
まずは“管理職志向・出世意欲”に関する質問で、「Q.あなたは、現在の会社で管理職になりたいと感じますか」に対して、以下は「管理職になりたいと思っている人の割合」の結果です(※5段階尺度で、スコアは「そう思う」「ややそう思う」の合算値)。
【管理職になりたいと思っている人の割合】
順位:国・地域名(回答者数)全体(%)
1位:インド(94)86.2%
2位:ベトナム(360)86.1%
3位:フィリピン(402)82.6%
4位:タイ(417)76.5%
5位:インドネシア(361)75.6%
6位:中国(383)74.2%
7位:マレーシア(294)69.0%
8位:韓国(410)60.2%
9位:台湾(580)52.2%
10位:香港(577)51.3%
11位:シンガポール(419)49.6%
12位:オーストラリア(487)44.8%
13位:ニュージーランド(549)41.2%
14位:日本(387)21.4%
また、「Q.仕事に関する意識としてあなたの考えに最も近いものを各ひとつお選びください」に対して、「会社で出世したい」と回答した結果が以下となっています(※5段階尺度)。
【会社で出世したいと回答】
国・地域名:平均値
タイ:4.7
フィリピン:4.6
インド:4.5
ベトナム:4.5
マレーシア:4.3
インドネシア:4.3
シンガポール:4.1
中国:4.0
台湾:3.9
オーストラリア:3.9
香港:3.8
ニュージーランド:3.7
韓国:3.7
日本:2.9
これらの結果からは、日本の上昇志向が14の国・地域のうち最も弱く、出世意欲も最も低いことが見えてきます。
「Q.あなたが自分の成長を目的として行っている勤務先以外での学習や自己啓発活動についてお知らせください」に対して、「とくに何も行っていない」と回答した結果が以下となっています(※複数回答/「とくに何も行っていない」は選択肢11項目中の1項目)。
【(勤務先以外での学習や自己啓発活動を)とくに何も行っていない】
国・地域名:平均(%)
ベトナム:2.0%
インドネシア:2.3%
インド:4.9%
タイ:5.7%
中国:6.3%
フィリピン:6.4%
マレーシア:7.4%
韓国:12.3%
台湾:13.0%
シンガポール:18.3%
香港:18.3%
オーストラリア:21.5%
ニュージーランド:22.1%
日本:46.3%
日本はワースト2位のニュージーランドと比べても、倍以上の24.2ポイントも差があり、群を抜いて自己啓発や自己研鑽をしていないことが見えてきます。
一方、シンガポール以外の東南アジアやインド、中国では「とくに何も行っていない」割合は1割未満であり、自己啓発や自己研鑽に意欲的な傾向がうかがえます。なお、14の国・地域の平均は13.3%でした。
ただし、現代の日本におけるいわゆる出世意欲は、戦後の長期雇用保証制度とそれに伴う年功的賃金制度と深く関わってきたように思います。
経済学博士で慶応義塾大学教授の太田聰一氏は、「日本企業はこれまで、長期雇用を保障する中で従業員にいろいろな経験をさせ、経営幹部に引き上げてきた。それは社内で出世できるという従業員のインセンティブにもつながっている。日本企業の強みは、しっかりとした従業員教育によって、分厚い現場の力ができたことだ」と述べています。
太田氏の発言からは以下の3点のような、長期雇用保証制度を担保していた日本企業における、特異な“出世観”が見えてきます。
1)従来の日本企業型の長期雇用保証制度における出世とは狭い意味での“社内での出世”であり、かつ出世は年功的制度に組み込まれている(個人的な意欲や成果が“社内での出世”に反映されにくい)
2)“社内での出世”が従業員のインセンティブ(やる気を起こさせるような刺激・動機付け)を高めることにつながるが、そのためにはまず経営幹部等上司に引き上げられる必要がある(引き上げられないと発生しないため受動的である)
3)ビジネスパーソンとしての教育やスキルアップ等も従業員教育の一環として組み込まれているため、自己研鑽をしなくても社内では通用する(自己啓発よりも社内教育での評価を上げることが重要となる)
しかし、1990年代の経済低迷期の「失われた20年」+αによって、日本でも多数の企業で成果主義的な賃金制度が導入され、ある程度定着していきます。結果として現在は、年功賃金的制度と成果主義的賃金制度が合わさった企業が増え、「賃金カーブ(年齢階層別の賃金の変化)がフラット化」してきています。
つまり、多くの企業が一概に職業的地位に応じて賃金が増える経済状況ではなくなってきました。このことは、出世意欲を損なうことにつながります。同時に、社会の変化によって多くの企業で長期雇用保証制度だけでなく、それに伴う充実した従業員教育制度を維持することが難しくなってきました。
これらの要因が渾然となって、現在の日本人の出世意欲を低下させているように思います。
他方、太田氏が「これまでの日本では自己投資が評価されなかった。だが、仕事に求められるスキルの水準がはっきりすれば、自分のレベルアップが賃金アップにつながりやすくなり、仕事へのやる気にもつながる。自分次第で賃金は上がるという側面が強くなるだろう」と提言しているように、これまでと違う賃金制度の広がりは、主体性をもつ人にこそ、あらたなビジネスチャンスをもたらす可能性も秘めています。
社会が急速に変化し経済状況も混沌としている現在こそが、日本人の出世意欲の転換点となるのかもしれません。
次なる「失われた時代」とならないためにも、従来型の日本における“社内での出世”に意欲を燃やすのではなく、未来志向と幅広い視野で自身の出世を意欲的に構築し運用することが、今を生きるビジネスパーソンに求められています。
そのうえでパーソル総合研究所は、いくつかのトピックスにおける各国の比較分析の実施と公表をもって、「日本だけ“一人負け”といってよい特異な数字が出た調査結果となった」と、極めて厳しい分析コメントを発表しています。
では日本のビジネスパーソンは、アジアにおいてどのようなトピックスで“一人負け”を喫し、どんな状況に陥っているのでしょうか。調査結果を見ながら、考察してみたいと思います。
なお調査対象の詳細は、1)中国(北京、上海、広州)、2)韓国(ソウル)、3)台湾(台北)、4)香港、5)タイ(バンコク)、6)フィリピン(メトロマニラ)、7)インドネシア(ジャカルタ)、8)マレーシア(クアラルンプール)、9)シンガポール、10)ベトナム(ハノイ、ホーチミンシティ)、11)インド(デリー、ムンバイ)、12)オーストラリア(シドニー、メルボルン)、13)ニュージーランド、14)日本(東京・大阪・愛知)――の14の国・地域における主要都市のビジネスパーソンです。
日本のジネスパーソンは上昇志向が低い!?
さっそく、日本が“一人負け”したトピックスを見ていきましょう。まずは“管理職志向・出世意欲”に関する質問で、「Q.あなたは、現在の会社で管理職になりたいと感じますか」に対して、以下は「管理職になりたいと思っている人の割合」の結果です(※5段階尺度で、スコアは「そう思う」「ややそう思う」の合算値)。
【管理職になりたいと思っている人の割合】
順位:国・地域名(回答者数)全体(%)
1位:インド(94)86.2%
2位:ベトナム(360)86.1%
3位:フィリピン(402)82.6%
4位:タイ(417)76.5%
5位:インドネシア(361)75.6%
6位:中国(383)74.2%
7位:マレーシア(294)69.0%
8位:韓国(410)60.2%
9位:台湾(580)52.2%
10位:香港(577)51.3%
11位:シンガポール(419)49.6%
12位:オーストラリア(487)44.8%
13位:ニュージーランド(549)41.2%
14位:日本(387)21.4%
また、「Q.仕事に関する意識としてあなたの考えに最も近いものを各ひとつお選びください」に対して、「会社で出世したい」と回答した結果が以下となっています(※5段階尺度)。
【会社で出世したいと回答】
国・地域名:平均値
タイ:4.7
フィリピン:4.6
インド:4.5
ベトナム:4.5
マレーシア:4.3
インドネシア:4.3
シンガポール:4.1
中国:4.0
台湾:3.9
オーストラリア:3.9
香港:3.8
ニュージーランド:3.7
韓国:3.7
日本:2.9
これらの結果からは、日本の上昇志向が14の国・地域のうち最も弱く、出世意欲も最も低いことが見えてきます。
日本人の自己研鑽も怠っている!?
さらに“自己研鑽・自己啓発”に関する質問の結果も見てみましょう。「Q.あなたが自分の成長を目的として行っている勤務先以外での学習や自己啓発活動についてお知らせください」に対して、「とくに何も行っていない」と回答した結果が以下となっています(※複数回答/「とくに何も行っていない」は選択肢11項目中の1項目)。
【(勤務先以外での学習や自己啓発活動を)とくに何も行っていない】
国・地域名:平均(%)
ベトナム:2.0%
インドネシア:2.3%
インド:4.9%
タイ:5.7%
中国:6.3%
フィリピン:6.4%
マレーシア:7.4%
韓国:12.3%
台湾:13.0%
シンガポール:18.3%
香港:18.3%
オーストラリア:21.5%
ニュージーランド:22.1%
日本:46.3%
日本はワースト2位のニュージーランドと比べても、倍以上の24.2ポイントも差があり、群を抜いて自己啓発や自己研鑽をしていないことが見えてきます。
一方、シンガポール以外の東南アジアやインド、中国では「とくに何も行っていない」割合は1割未満であり、自己啓発や自己研鑽に意欲的な傾向がうかがえます。なお、14の国・地域の平均は13.3%でした。
日本人の“出世意欲”観は変化の過程にある?
ではなぜ、日本人の出世意欲はこれほど低いのでしょうか。しかし、考えてみると「立身出世」などの観念が広く根付いているように、もともと日本人にも出世意欲がないわけではなく、とくに明治維新後の近代化においては一種のスローガンとしても発展的に機能してきました。ただし、現代の日本におけるいわゆる出世意欲は、戦後の長期雇用保証制度とそれに伴う年功的賃金制度と深く関わってきたように思います。
経済学博士で慶応義塾大学教授の太田聰一氏は、「日本企業はこれまで、長期雇用を保障する中で従業員にいろいろな経験をさせ、経営幹部に引き上げてきた。それは社内で出世できるという従業員のインセンティブにもつながっている。日本企業の強みは、しっかりとした従業員教育によって、分厚い現場の力ができたことだ」と述べています。
太田氏の発言からは以下の3点のような、長期雇用保証制度を担保していた日本企業における、特異な“出世観”が見えてきます。
1)従来の日本企業型の長期雇用保証制度における出世とは狭い意味での“社内での出世”であり、かつ出世は年功的制度に組み込まれている(個人的な意欲や成果が“社内での出世”に反映されにくい)
2)“社内での出世”が従業員のインセンティブ(やる気を起こさせるような刺激・動機付け)を高めることにつながるが、そのためにはまず経営幹部等上司に引き上げられる必要がある(引き上げられないと発生しないため受動的である)
3)ビジネスパーソンとしての教育やスキルアップ等も従業員教育の一環として組み込まれているため、自己研鑽をしなくても社内では通用する(自己啓発よりも社内教育での評価を上げることが重要となる)
しかし、1990年代の経済低迷期の「失われた20年」+αによって、日本でも多数の企業で成果主義的な賃金制度が導入され、ある程度定着していきます。結果として現在は、年功賃金的制度と成果主義的賃金制度が合わさった企業が増え、「賃金カーブ(年齢階層別の賃金の変化)がフラット化」してきています。
つまり、多くの企業が一概に職業的地位に応じて賃金が増える経済状況ではなくなってきました。このことは、出世意欲を損なうことにつながります。同時に、社会の変化によって多くの企業で長期雇用保証制度だけでなく、それに伴う充実した従業員教育制度を維持することが難しくなってきました。
これらの要因が渾然となって、現在の日本人の出世意欲を低下させているように思います。
他方、太田氏が「これまでの日本では自己投資が評価されなかった。だが、仕事に求められるスキルの水準がはっきりすれば、自分のレベルアップが賃金アップにつながりやすくなり、仕事へのやる気にもつながる。自分次第で賃金は上がるという側面が強くなるだろう」と提言しているように、これまでと違う賃金制度の広がりは、主体性をもつ人にこそ、あらたなビジネスチャンスをもたらす可能性も秘めています。
社会が急速に変化し経済状況も混沌としている現在こそが、日本人の出世意欲の転換点となるのかもしれません。
次なる「失われた時代」とならないためにも、従来型の日本における“社内での出世”に意欲を燃やすのではなく、未来志向と幅広い視野で自身の出世を意欲的に構築し運用することが、今を生きるビジネスパーソンに求められています。
<参考文献・参考サイト>
・パーソル総合研究所、日本の「はたらく意識」の特徴を国際比較調査で明らかに
国際競争力低下の懸念。日本で働く人の46.3%が社外で自己研鑽せず
https://rc.persol-group.co.jp/news/201908270001.html
・「立身出世」、『日本大百科全書』(麻生誠著、小学館)
・「インタビュー 太田聰一・慶應義塾大学経済学部教授 自分次第で賃金は上がる 非正社員増で強まる成果主義 (増える給料)」、『エコノミスト』(2018年6月12日号、毎日新聞出版)
・「インセンティブ」、『デジタル大辞泉』(小学館)
・パーソル総合研究所、日本の「はたらく意識」の特徴を国際比較調査で明らかに
国際競争力低下の懸念。日本で働く人の46.3%が社外で自己研鑽せず
https://rc.persol-group.co.jp/news/201908270001.html
・「立身出世」、『日本大百科全書』(麻生誠著、小学館)
・「インタビュー 太田聰一・慶應義塾大学経済学部教授 自分次第で賃金は上がる 非正社員増で強まる成果主義 (増える給料)」、『エコノミスト』(2018年6月12日号、毎日新聞出版)
・「インセンティブ」、『デジタル大辞泉』(小学館)
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










