テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
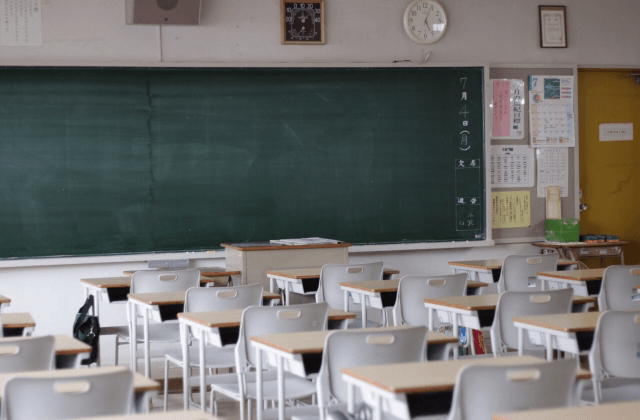
教育改革が実施される背景にある社会の変化とは?
大学入学共通テストの記述式問題導入をめぐって議論が重ねられています。実際の導入となると、採点のばらつきやミスが懸念されるなど多くの問題点が指摘されているため、ひとまず2021年1月の実施は見送られました。
しかし今、学生には知識の量ではなく、知識をもとに自分で考え判断し論旨をまとめて他者に伝える能力が求められているのは事実であり、そうした観点から新たな教育改革が進みつつあるのです。
この生きる力とは現行の学習指導要領によれば、「変化の激しい社会で生きる子どもたちに身につけさせるべき力」とされ、「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」の3要素で構成されています。
このうち「確かな学力」に必要な要素は、1.十分な知識・技能、2.それらを基盤にして自分で解を見出していくための思考力・判断力・表現力、3.以上のもととなる主体性・多様性・協働性の3つとされ、こうした学力を身につけさせるために教育改革が推進されているのです。
このような学力は、大学入試に勝ちぬくための短期目標達成的な勉強方法では身につきません。高校進学率はほぼ100パーセントに近く、大学進学率は50パーセント以上。専門学校も含めると約80パーセントが高等教育科に進むという状況も踏まえ、教育改革は「高大接続改革」を基軸に行われています。本来、密接に関係しあう高等学校教育と大学教育、そして高等学校から大学への入口となる大学入学者選抜を三位一体で捉え、一貫した方針で改革していこうというのです。
戦後の高度経済成長期までは、いわゆる工業化社会でベビーブームの影響もあり生産年齢人口は十分なものがありました。経済成長が促される人口ボーナス期で、日本中が欧米の社会モデルに追いつこう、追い抜こうと必死だった時代です。一生懸命働けば結果にすぐ結びつくとされ、熾烈な競争社会で勝ち残るために、早く効率的に1つの正解を導きだす力、つまり知識技能の習得と再生を中心とする情報処理力が大いに求められました。企業での就労形態も年功序列、終身雇用が当然であり、横並び一線の状況からいかにキャリアを積み上げて抜きん出ていくかで、その人の力量がはかられました。
しかし、高齢化、出生率の低下に伴い日本の生産年齢人口は減少傾向に入ります。人口構成の変化が経済成長に歯止めをかける人口オーナス期で、より少ない人口で社会を支えていくために一人一人の負担は増加しています。
かたや、大学進学率は50パーセントを超えユニバーサル化(大衆化)し、大学教育で得た知識や技能の多寡で優劣を語ることが難しくなってきました。持てる知識をいかに活用し、多様な価値観に対応すべく1つの正解より複数の納得解を創出する力、情報編集力が求められているのです。
また、社会環境の変化に伴い、減少する労働人口を補うためにIT技術やロボット、AIによる技術革新が進展しましたが、多くの作業が自動化されることで、近い将来、多くの職業が消滅する、雇用者削減の可能性も出てきました。オックスフォード大学マイケル・A・オズボーン准教授が、あと10年~20年で現在の約半数の職業が機械に取って替わるだろうとする論文を発表して、世界に衝撃を与えたのも記憶に新しいところです。
明治維新以来といわれる大規模かつ抜本的な教育改革です。私たちも「教育は学校で行なうもの」と決めつけずに、社会や家庭で、全方位で考えないといけない時代になっているのかもしれません。何と言っても「生きる力」を育むのに必要な教育なのですから。
しかし今、学生には知識の量ではなく、知識をもとに自分で考え判断し論旨をまとめて他者に伝える能力が求められているのは事実であり、そうした観点から新たな教育改革が進みつつあるのです。
「生きる力」と「確かな学力」のために
そもそも教育とは、「人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として心身ともに健康な国民の育成を期する」ことを目的として行われるもの、と文部科学省では定義しています。社会の一員として活躍できる「生きる力」を育むのが、教育の基本理念であるといえるでしょう。この生きる力とは現行の学習指導要領によれば、「変化の激しい社会で生きる子どもたちに身につけさせるべき力」とされ、「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」の3要素で構成されています。
このうち「確かな学力」に必要な要素は、1.十分な知識・技能、2.それらを基盤にして自分で解を見出していくための思考力・判断力・表現力、3.以上のもととなる主体性・多様性・協働性の3つとされ、こうした学力を身につけさせるために教育改革が推進されているのです。
このような学力は、大学入試に勝ちぬくための短期目標達成的な勉強方法では身につきません。高校進学率はほぼ100パーセントに近く、大学進学率は50パーセント以上。専門学校も含めると約80パーセントが高等教育科に進むという状況も踏まえ、教育改革は「高大接続改革」を基軸に行われています。本来、密接に関係しあう高等学校教育と大学教育、そして高等学校から大学への入口となる大学入学者選抜を三位一体で捉え、一貫した方針で改革していこうというのです。
教育改革の背景となる社会の変化
このような教育改革が実施される背景には大きな社会変化がある、とリクルート進学総研所長小林浩氏は論じています。戦後の高度経済成長期までは、いわゆる工業化社会でベビーブームの影響もあり生産年齢人口は十分なものがありました。経済成長が促される人口ボーナス期で、日本中が欧米の社会モデルに追いつこう、追い抜こうと必死だった時代です。一生懸命働けば結果にすぐ結びつくとされ、熾烈な競争社会で勝ち残るために、早く効率的に1つの正解を導きだす力、つまり知識技能の習得と再生を中心とする情報処理力が大いに求められました。企業での就労形態も年功序列、終身雇用が当然であり、横並び一線の状況からいかにキャリアを積み上げて抜きん出ていくかで、その人の力量がはかられました。
しかし、高齢化、出生率の低下に伴い日本の生産年齢人口は減少傾向に入ります。人口構成の変化が経済成長に歯止めをかける人口オーナス期で、より少ない人口で社会を支えていくために一人一人の負担は増加しています。
かたや、大学進学率は50パーセントを超えユニバーサル化(大衆化)し、大学教育で得た知識や技能の多寡で優劣を語ることが難しくなってきました。持てる知識をいかに活用し、多様な価値観に対応すべく1つの正解より複数の納得解を創出する力、情報編集力が求められているのです。
また、社会環境の変化に伴い、減少する労働人口を補うためにIT技術やロボット、AIによる技術革新が進展しましたが、多くの作業が自動化されることで、近い将来、多くの職業が消滅する、雇用者削減の可能性も出てきました。オックスフォード大学マイケル・A・オズボーン准教授が、あと10年~20年で現在の約半数の職業が機械に取って替わるだろうとする論文を発表して、世界に衝撃を与えたのも記憶に新しいところです。
明治維新以来といわれる大規模かつ抜本的な教育改革です。私たちも「教育は学校で行なうもの」と決めつけずに、社会や家庭で、全方位で考えないといけない時代になっているのかもしれません。何と言っても「生きる力」を育むのに必要な教育なのですから。
人気の講義ランキングTOP20










