テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
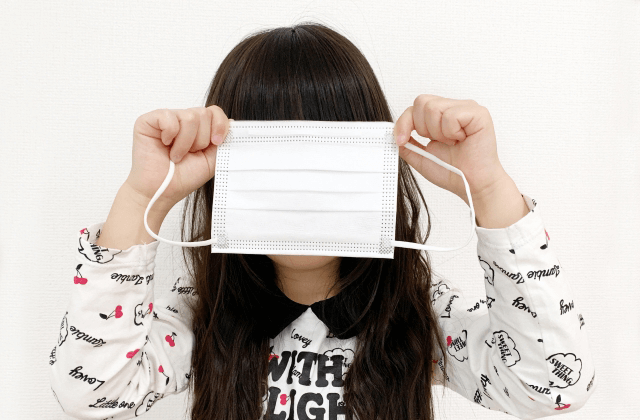
『マスク社会が危ない』――子どもの発達と未来のための警鐘
「子どもの脳は、大人のミニチュア版、小型版ではない」――だからこそ、子どもたちの立場に寄り添った議論が必要であるとの強い信念と喫緊の問題意識から、京都大学大学院教育学研究科教授の明和政子先生は『マスク社会が危ない 子どもの発達に「毎日マスク」はどう影響するか?』(宝島社新書)を上梓されました。
本書において明和先生は、「新しい生活様式」の象徴ともいえるマスク社会が、子どもの脳に、ひいては子どもの発達に多大な悪影響を及ぼす危険性に、大いなる警鐘を鳴らしています。
まずヒトにとって子どもである時期は、脳の発達の特別な時期にあたります。子どもの脳内ネットワークは、環境の影響を大きく受けながら発達していきます。
その際、他者の多様な表情に接することによって得られる個人的な経験が、その個人が生涯持つこととなる特性の土台となります。しかし、コロナ禍以降に生まれた子どもはマスク社会のあおりを受けて、他者の多様な表情に接する機会が激減しています。
より具体的には、生後6カ月くらいから、コミュニケーション相手の目よりも口元のほうを長く見ることが研究によってわかっているそうです。しかし、マスク社会では、乳児を取り巻く他者の口元は完全に覆い隠されています。
例えば、目の前の人がニコッと笑顔を浮かべると、生後数カ月の乳児であっても喜怒哀楽の区別ができるといいます。ここには「ミラーニューロン」という神経ネット-ワークが関与しているとみられています。
相手の笑顔を「サル真似」するという身体経験によって、乳児は笑うことの心地よさを体感します。そのような経験を通して相手も自分と同じように心地よいと感じるようになり、他者理解が可能となっていきます。このように、ヒトは言葉を話し始める前から、他者の表情や行為を真似る「サル真似」によって、心身を育んでいきます。
さらに子どもは、ある表情(シグナル)はこういう意味を持っている(シンボル)という理解は、両親やごく身近な人たちだけにとどまることなく、多様な他者にも当てはめて広げていく“「般化」学習”をする必要があります。「般化」学習は社会性を育むためには必要となる重要なプロセスですが、マスク社会では阻害されているといわざるを得ません。
前頭前野の働きは、ヒト特有の社会性にも深く関与しているといわれています。例えば、ヒトは、他者との関係のなかで、たとえ「いま・ここ」が嫌な気持ちであったとしても、未来の良いイメージを描いて我慢できたりするなど想像力によって自己コントロールができますが、これらは前頭前野の働きによって可能となっています。
しかし、前頭前野の完成には、25年以上の年月が必要といわれています。つまり、学童期はもちろん思春期の子どもの時期、そして成人後、数年間ほど前頭前野はまだ未成熟であり、大脳辺縁系の活動を制御することが難しいとされています。
そしてこの時期は、相手の視点や立場にたてる「視点変換」と呼ばれる、社会生活に欠かすことのできない重要な認知能力を育む期間でもあります。
以上のような貴重な脳部位の感受性期に、マスク社会によってストレスを与え続け、他者との交流やふれあいを奪うことは、大人本位の政策によって子どもの未来を阻害しているといえるのではないでしょうか。
ただし、安易に一斉にマスクを外す指導をしたらコロナ禍以前に戻るのかといえば、そのような楽観論は難しいと思われます。
本書では、卒業アルバムを作るために初めてクラスメートのマスクをしていない顔を見た、中学3年生の話を取り上げています。その生徒は、クラスメートに対して「こんな顔をしていたんだ」ととても驚くと同時に、「早く撮影が終わってほしい、マスクをしたい」と思ったそうです。そして、自分もクラスメートから「あんな顔だったのか」と見られることが不安だったと述べています。
よって、コロナ禍である「いま・ここ」だけの議論をするのではなく、子どもの心身、その発達と未来という長期的な視点になった議論をすることの必要性が喫緊の課題であることが伺えます。
本書の第3章では、ジャーナリストの鳥集徹氏と「パンデミックで浮き彫りになった『子どもファースト』からかけ離れた日本の実態」と題した特別対談をされています。現状、「日本社会は、大人にとって『便利、楽、心地よい』といった価値観だけで推し進められていると感じます」と明和先生が述べているように、「子どもファースト」視点が抜け落ちています。そこで、明和先生と鳥集氏は、大人の都合や視点のみで「いま・ここ」に対処するのではなく、未来を担う子どもの立場に立った議論や政策を実行することの必要性を語り合っています。
当然ながら、明和先生も鳥集氏も、一方的に「マスク社会が危ない」「今すぐみんなマスクを外そう」と言っているわけではありません。科学的・医学的な根拠を示しつつ、哲学や生命倫理学といった人文社会学の意見も尊重するなど、さまざまな立場から出し合った論理的な意見にもとづいて議論を深め、さらに一人ひとりが当事者として行動する必要性を説きながら、マスク社会の弊害を減らし、子どもの未来を守るための行動を提唱されているのです。
ということで本書は、コロナ禍における子どもの未来を心配する方、一律に押しつけられているような「新しい生活様式」やマスク社会に違和感を覚え疑問を持つ方、さらには、子どもの健やかな成長の延長線上にある、多様性を尊重した持続可能な社会の実現を願う全ての方にぜひ読んでほしい、「アフターコロナの羅針盤」ともいえる一冊です。
本書において明和先生は、「新しい生活様式」の象徴ともいえるマスク社会が、子どもの脳に、ひいては子どもの発達に多大な悪影響を及ぼす危険性に、大いなる警鐘を鳴らしています。
目よりも重要な“口元”を覆うマスクの影響
ではなぜマスク社会は子どもの脳に悪影響を及ぼすのでしょうか。まずヒトにとって子どもである時期は、脳の発達の特別な時期にあたります。子どもの脳内ネットワークは、環境の影響を大きく受けながら発達していきます。
その際、他者の多様な表情に接することによって得られる個人的な経験が、その個人が生涯持つこととなる特性の土台となります。しかし、コロナ禍以降に生まれた子どもはマスク社会のあおりを受けて、他者の多様な表情に接する機会が激減しています。
より具体的には、生後6カ月くらいから、コミュニケーション相手の目よりも口元のほうを長く見ることが研究によってわかっているそうです。しかし、マスク社会では、乳児を取り巻く他者の口元は完全に覆い隠されています。
「サル真似」や「般化」学習を阻害するマスク社会
さらに明和先生によると、「脳発達の感受性期(環境に適応して生存可能性を高めるために必要となる脳内ネットワークの選択が急激に進む時期)」のうち、大脳皮質中の「視覚野」と「聴覚野」の発達は1歳前後でピークを迎え、その後7~8歳頃まで続き、就学を迎える頃には環境の影響を受けにくくなって成熟に達するということです。例えば、目の前の人がニコッと笑顔を浮かべると、生後数カ月の乳児であっても喜怒哀楽の区別ができるといいます。ここには「ミラーニューロン」という神経ネット-ワークが関与しているとみられています。
相手の笑顔を「サル真似」するという身体経験によって、乳児は笑うことの心地よさを体感します。そのような経験を通して相手も自分と同じように心地よいと感じるようになり、他者理解が可能となっていきます。このように、ヒトは言葉を話し始める前から、他者の表情や行為を真似る「サル真似」によって、心身を育んでいきます。
さらに子どもは、ある表情(シグナル)はこういう意味を持っている(シンボル)という理解は、両親やごく身近な人たちだけにとどまることなく、多様な他者にも当てはめて広げていく“「般化」学習”をする必要があります。「般化」学習は社会性を育むためには必要となる重要なプロセスですが、マスク社会では阻害されているといわざるを得ません。
マスク社会のストレスと未成熟な子どもの脳
また明和先生は、学童期頃から始まる脳部位の感受性期、特に前頭前野の感受性期における、マスク社会の弊害も述べています。前頭前野の働きは、ヒト特有の社会性にも深く関与しているといわれています。例えば、ヒトは、他者との関係のなかで、たとえ「いま・ここ」が嫌な気持ちであったとしても、未来の良いイメージを描いて我慢できたりするなど想像力によって自己コントロールができますが、これらは前頭前野の働きによって可能となっています。
しかし、前頭前野の完成には、25年以上の年月が必要といわれています。つまり、学童期はもちろん思春期の子どもの時期、そして成人後、数年間ほど前頭前野はまだ未成熟であり、大脳辺縁系の活動を制御することが難しいとされています。
そしてこの時期は、相手の視点や立場にたてる「視点変換」と呼ばれる、社会生活に欠かすことのできない重要な認知能力を育む期間でもあります。
以上のような貴重な脳部位の感受性期に、マスク社会によってストレスを与え続け、他者との交流やふれあいを奪うことは、大人本位の政策によって子どもの未来を阻害しているといえるのではないでしょうか。
ただし、安易に一斉にマスクを外す指導をしたらコロナ禍以前に戻るのかといえば、そのような楽観論は難しいと思われます。
本書では、卒業アルバムを作るために初めてクラスメートのマスクをしていない顔を見た、中学3年生の話を取り上げています。その生徒は、クラスメートに対して「こんな顔をしていたんだ」ととても驚くと同時に、「早く撮影が終わってほしい、マスクをしたい」と思ったそうです。そして、自分もクラスメートから「あんな顔だったのか」と見られることが不安だったと述べています。
よって、コロナ禍である「いま・ここ」だけの議論をするのではなく、子どもの心身、その発達と未来という長期的な視点になった議論をすることの必要性が喫緊の課題であることが伺えます。
「子どもファースト」視点の持続可能な社会へ
多様性とともに重要な今日的な課題に、持続可能性があります。多様性を尊重した持続可能な社会を実現するためにも、子ども視点に立つこと、つまり「子どもファースト」視点が必要です。本書の第3章では、ジャーナリストの鳥集徹氏と「パンデミックで浮き彫りになった『子どもファースト』からかけ離れた日本の実態」と題した特別対談をされています。現状、「日本社会は、大人にとって『便利、楽、心地よい』といった価値観だけで推し進められていると感じます」と明和先生が述べているように、「子どもファースト」視点が抜け落ちています。そこで、明和先生と鳥集氏は、大人の都合や視点のみで「いま・ここ」に対処するのではなく、未来を担う子どもの立場に立った議論や政策を実行することの必要性を語り合っています。
当然ながら、明和先生も鳥集氏も、一方的に「マスク社会が危ない」「今すぐみんなマスクを外そう」と言っているわけではありません。科学的・医学的な根拠を示しつつ、哲学や生命倫理学といった人文社会学の意見も尊重するなど、さまざまな立場から出し合った論理的な意見にもとづいて議論を深め、さらに一人ひとりが当事者として行動する必要性を説きながら、マスク社会の弊害を減らし、子どもの未来を守るための行動を提唱されているのです。
ということで本書は、コロナ禍における子どもの未来を心配する方、一律に押しつけられているような「新しい生活様式」やマスク社会に違和感を覚え疑問を持つ方、さらには、子どもの健やかな成長の延長線上にある、多様性を尊重した持続可能な社会の実現を願う全ての方にぜひ読んでほしい、「アフターコロナの羅針盤」ともいえる一冊です。
<参考文献>
『マスク社会が危ない 子どもの発達に「毎日マスク」はどう影響するか?』(明和政子著、宝島社新書)
https://tkj.jp/book/?cd=TD033727
<参考サイト>
京都大学大学院教育学研究科 明和政子研究室
https://myowa.educ.kyoto-u.ac.jp/
『マスク社会が危ない 子どもの発達に「毎日マスク」はどう影響するか?』(明和政子著、宝島社新書)
https://tkj.jp/book/?cd=TD033727
<参考サイト>
京都大学大学院教育学研究科 明和政子研究室
https://myowa.educ.kyoto-u.ac.jp/
人気の講義ランキングTOP20










