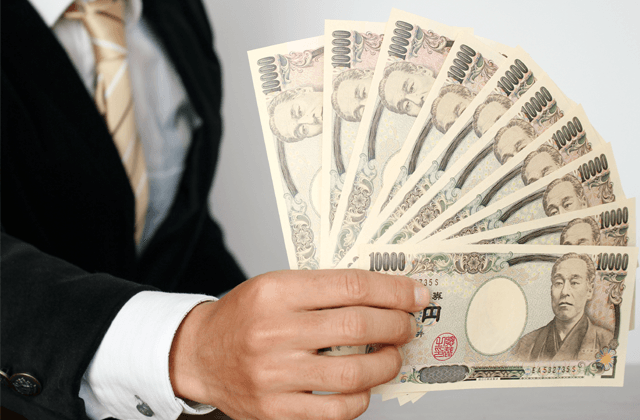
お金をばらまく?「ヘリコプター・マネー」とは
5月26、27日に開催された伊勢志摩サミットで、日本は議長国としての存在感を発揮しました。安倍首相の「リーマン前発言」には批判も集まりましたが、「世界経済の回復は継続しているが、見通しに対する下方リスクが高まっている」ことは、各国の共通認識。G7の首脳は「新たな危機に陥ることを回避するため、すべての政策対応を行う」ことで合意しています。
「すべての政策対応」のなかでも、日本が近々導入に踏み切るのではないかと世界が注目しているのが、「ヘリコプター・マネー」です。
もちろん実際に空からお金を降らせるわけではありません。現実的には、財政支出や中央銀行による国債の引き受け、減税、国民に対する直接給付などを行います。それらを通じて、政府が本当に望んでいるのは消費市場の活発化です。
サミット後、実施予定が2年半後に繰り延べられた「消費税10ペーセント増税」にしても、「税金が増えれば、国民は消費を控えるだろう」というシンプルな読みにもとづくものです。
「中央銀行は空から、現金が枯渇している下界に向けて、新規にお札をばらまくことができるので、通貨供給量を押し上げ続けることができる」というのが、その主張。ただし、これは1929年の大恐慌の原因を分析した研究であり、「市場の失敗ではなく、不適切な金融引き締めが主要な原因だったのだ」とするものでした。
プリンストン大学で経済学部教授を務めていた彼は、2002年、フリードマン氏の90歳の誕生パーティ席上で恩師への忠誠を明らかにするためか、「FRBは同じ過ちは繰り返しません」と誓い、「デフレ克服のためには、ヘリコプターからお札をばらまけばよい」と発言。「ヘリコプター・ベン」のあだ名と共に就任したFRBでは、サブプライムローンに端を発した世界金融危機を受けて、ゼロ金利政策や量的緩和政策を実行に移しました。
バーナンキ氏は日本のデフレ対策としてもヘリコプター・マネーを推奨しているようですが、経済学者はそのあたりをどう見ているのでしょうか。
と10MTVオピニオンの中で話すのは、日本銀行政策委員会の審議委員を歴任し、東京大学大学院経済学研究科でマクロ経済学や金融論を教える植田和男教授です。
日本の場合、かつて第二次大戦続行のために巨額の国債を発行し、日銀が途中から買い支えに入った時期がありました。これがインフレにつながり、戦後の物資不足と呼応して「ハイパーインフレ」現象を引き起こしています。日銀の調査によれば、1934ー1936年の消費者物価指数を1とした場合、1954年は301.8。8年間で物価が約300倍になったのです。
植田教授は、戦争末期の国債とGDPの比率が約200パーセントで、現在の水準とほぼ等しいことを、「警戒信号であると指摘したい」とも語っています。
仮にインフレ率がものすごく上がったとします。内閣や日本銀行の思惑である2パーセントではなく、10パーセント上がった場合、2020年代の半ばごろまでは、目に見えて国債とGDP比率が下がっていくでしょう。さらに、もしインフレ率が20パーセントになったら、2050年ごろまではあまり財政のことを心配しないでいいということになります。
つまり、ヘリコプターマネーを大規模に行い、インフレ率がものすごく上がれば、財政は一応楽になるという計算もできなくはない、ということです。ただこれは、その過程で金利がインフレ率ぐらいしか上がらないという前提を置いており、もし金利が先んじて上がってしまえば、この計算は成り立たなくなるということです。
いずれにせよ、財政が苦しいときにヘリコプターマネーを行い、非常に効率のいいインフレーションを出すというインセンティブがあるということなのです。
「すべての政策対応」のなかでも、日本が近々導入に踏み切るのではないかと世界が注目しているのが、「ヘリコプター・マネー」です。
消費増税先送りも、ささやかヘリコプター・マネーか?
ヘリコプター・マネーは、文字通り、ヘリコプターで上空からお金をばらまくこと。わたしたちにとっては「空からお金が降ってくる」わけで、夢のような話ですね。もちろん実際に空からお金を降らせるわけではありません。現実的には、財政支出や中央銀行による国債の引き受け、減税、国民に対する直接給付などを行います。それらを通じて、政府が本当に望んでいるのは消費市場の活発化です。
サミット後、実施予定が2年半後に繰り延べられた「消費税10ペーセント増税」にしても、「税金が増えれば、国民は消費を控えるだろう」というシンプルな読みにもとづくものです。
「大恐慌」の原因分析から出てきたヘリコプター・マネー
これをデフレ対策の特効薬として、真剣に考慮したのは米国の経済学者ミルトン・フリードマン氏でした。フリードマン氏は、著書『貨幣の悪戯』の中でこの手法についてふれています。「中央銀行は空から、現金が枯渇している下界に向けて、新規にお札をばらまくことができるので、通貨供給量を押し上げ続けることができる」というのが、その主張。ただし、これは1929年の大恐慌の原因を分析した研究であり、「市場の失敗ではなく、不適切な金融引き締めが主要な原因だったのだ」とするものでした。
フリードマン説を引きずり出した「ヘリコプター・ベン」
一見現実味がなくデタラメに思える「ヘリコプター・マネー」案を現実レベルで達成したのは、2006年から2014年にかけて米連邦準備制度理事会(FRB)議長を務めたベン・バーナンキ氏です。プリンストン大学で経済学部教授を務めていた彼は、2002年、フリードマン氏の90歳の誕生パーティ席上で恩師への忠誠を明らかにするためか、「FRBは同じ過ちは繰り返しません」と誓い、「デフレ克服のためには、ヘリコプターからお札をばらまけばよい」と発言。「ヘリコプター・ベン」のあだ名と共に就任したFRBでは、サブプライムローンに端を発した世界金融危機を受けて、ゼロ金利政策や量的緩和政策を実行に移しました。
バーナンキ氏は日本のデフレ対策としてもヘリコプター・マネーを推奨しているようですが、経済学者はそのあたりをどう見ているのでしょうか。
なぜヘリコプター・マネーは禁止されているのか
「多くの国で、ヘリコプター・マネーは『やってはいけない』政策と考えられ、法律で禁止されています。その最大の理由は、ヘリコプター・マネーによって引き起こされるインフレが、『デフレよりも悪い』という認識があるからです」と10MTVオピニオンの中で話すのは、日本銀行政策委員会の審議委員を歴任し、東京大学大学院経済学研究科でマクロ経済学や金融論を教える植田和男教授です。
日本の場合、かつて第二次大戦続行のために巨額の国債を発行し、日銀が途中から買い支えに入った時期がありました。これがインフレにつながり、戦後の物資不足と呼応して「ハイパーインフレ」現象を引き起こしています。日銀の調査によれば、1934ー1936年の消費者物価指数を1とした場合、1954年は301.8。8年間で物価が約300倍になったのです。
植田教授は、戦争末期の国債とGDPの比率が約200パーセントで、現在の水準とほぼ等しいことを、「警戒信号であると指摘したい」とも語っています。
2050年の日本経済はどうなる?
植田教授はこうも語っています。仮にインフレ率がものすごく上がったとします。内閣や日本銀行の思惑である2パーセントではなく、10パーセント上がった場合、2020年代の半ばごろまでは、目に見えて国債とGDP比率が下がっていくでしょう。さらに、もしインフレ率が20パーセントになったら、2050年ごろまではあまり財政のことを心配しないでいいということになります。
つまり、ヘリコプターマネーを大規模に行い、インフレ率がものすごく上がれば、財政は一応楽になるという計算もできなくはない、ということです。ただこれは、その過程で金利がインフレ率ぐらいしか上がらないという前提を置いており、もし金利が先んじて上がってしまえば、この計算は成り立たなくなるということです。
いずれにせよ、財政が苦しいときにヘリコプターマネーを行い、非常に効率のいいインフレーションを出すというインセンティブがあるということなのです。
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







