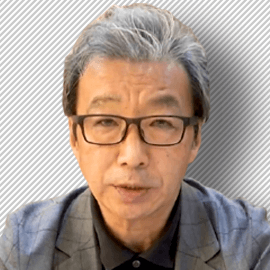●武士を誕生させた中世は、お手本なき時代だった
こんにちは。初めまして。日本大学の関幸彦と申します。
今日は皆さまに、武士の誕生ということで、武士の登場のプロセスをお話ししようと思います。
武士というと、武的領有者の代名詞として、日本の歴史における中世の主役と考えられています。ただし、中世の時代についてはいろいろと議論があり、近年では院政期である11世紀の末ぐらいから中世の時代へと突入したといわれています。そして、その主役が武士です。そもそも武士は院政期を含めて、その前の時代から日本国の胎内でどのように成立したのかについては非常に大きな議論があります。
大きな議論を考える上で、大陸情勢、また東アジア情勢という外からの視点と、日本国内部の事情という胎内的な視点の両様を重ね合わせながら議論していくことが最も近道であると思われます。
ちなみに、武士を育み生み出していった中世の時代は、「お手本がない時代」であると考えられています。
「お手本がない」とはどういう意味か。7世紀から始まる古代の時代は中国の律令制を1つのお手本にしました。古代の国家は、お手本をしっかりと見つめながら国家デザインやモデルをつくっていったのです。
日本の歴史を考えたときに、お手本がある時代の一つに先ほど挙げた古代があります。そしてもう一つ、日本が近代へと突入していく幕末から明治維新の時期もまた、欧米というお手本がありました。
われわれが主題としている武家の時代は、およそ700年の長きにわたって続きます。その700年の長き間に三つの幕府を設定できます。ご承知のように、鎌倉幕府、室町幕府、そして江戸幕府です。
それぞれの幕府の主役、すなわち武家政権の主役を成したのが、いうまでもなく武士です。武士は700年にわたる大きな時代の主役を成しましたが、そこにはお手本がありません。
主役となる最初の段階に鎌倉幕府が登場します。この登場の主役を成す武士が、平安時代の400年にわたる時期に、どのような流れの中で育っていったのかについて、いくつかポイントを挙げて議論していきたいと思います。
●「有力農民が武士化した」という理解は是正されつつある
皆さんたちの多くが中学や高等学校で習った昔の記憶をひも解いていただくと分かるかもしれませんが、「武士は農民のチャンピオンであった。農民が...