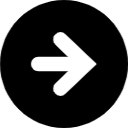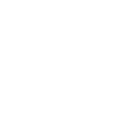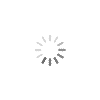この講義シリーズは第2話まで
登録不要で無料視聴できます!
本当のことがわかる昭和史《1》誰が東アジアに戦乱を呼び込んだのか
張作霖は日本軍のスパイとしても活躍した男だった
本当のことがわかる昭和史《1》誰が東アジアに戦乱を呼び込んだのか(3)張作霖はソ連にとっての大いなる邪魔者
渡部昇一(上智大学名誉教授)
1928年の張作霖爆殺事件は、果たして日本陸軍の陰謀だったのか? その背後にでは1917年のロシア革命で成立したソビエト連邦のコミンテルンが暗躍していた形跡がある。上智大学名誉教授・渡部昇一氏によるシリーズ「本当のことがわかる昭和史」第一章・第3話。
時間:2分06秒
収録日:2014年11月17日
追加日:2015年8月10日
収録日:2014年11月17日
追加日:2015年8月10日
カテゴリー:
≪全文≫
われわれが忘れてはならないのは、すでに大正11年(1922)にはロシアに共産党政権ができていて、共産主義を世界に広げるべく活発な活動を行なっていたことだ。
大正6年(1917)のロシア革命で成立したソビエト連邦は、さらに革命を世界に広めていくことを真剣に模索した。そのための機関がコミンテルン(共産主義インターナショナル〈第三インターナショナル〉)である。当初、コミンテルンが目指したのはヨーロッパ、とくにドイツにおける共産革命であった。だが、第一次大戦後、ドイツで共産革命を目指したスパルタクス団が暴動を起こすものの失敗し(1919年)、指導者のカール・リープクネヒトやローザ・ルクセンブルクが殺害されるに至って、この路線は完全に失敗する。1924年にレーニンが死去し、スターリンの時代になると、スターリンは「一国社会主義」(ソ連だけで社会主義国家を建設していく)という方針を打ち出しつつ、矛先を東アジアにおける主要な仮想敵である日本に向けるようになっていく。
コミンテルンの手法は、敵の政権内部に共産主義者を浸透させて内部から攪乱・崩壊を狙うことである。現実に、ソ連のシンパが、日本陸軍や外務省など政権中枢に入り込んでいた形跡もある。
そしてソ連の対日戦略において、重要な場となったのがシナであった(ちなみに本書ではいわゆる「中国」のことを「シナ」と表記することを標準とする。それは本来、「中国」という言葉が「自分にとって一番大切な国」という意味であって、日本でも幕末に至るまで自国〈=日本〉を「中国」と記す例があったからだ。しかも「中国」という場合、華夷思想に基づいて、周辺国は「蛮族」だという認識も付随する。翻って「シナ」という言葉は英語の「China」と同義であり、なんら差別的意味合いはない。「中国」は中華民国 、あるいは中華人民共和国の略称、あるいは現在のシナ大陸の政権を指すのに用いる)。ソ連は中国共産党と国民党にそれぞれ援助を与えつつ、両党を合作(国共合作)させ、反日運動を煽っていた。
その際、ソ連にとっての大いなる邪魔者の一人が、軍閥として満洲から華北を支配していた張作霖であった。
もともと張作霖は満洲の馬賊(盗賊などへの自衛のために結成された非合法の軍事集団、匪賊〈ひぞく〉)に加入してめきめき頭角を現わし、日露戦争では日本軍のスパイとしても...
われわれが忘れてはならないのは、すでに大正11年(1922)にはロシアに共産党政権ができていて、共産主義を世界に広げるべく活発な活動を行なっていたことだ。
大正6年(1917)のロシア革命で成立したソビエト連邦は、さらに革命を世界に広めていくことを真剣に模索した。そのための機関がコミンテルン(共産主義インターナショナル〈第三インターナショナル〉)である。当初、コミンテルンが目指したのはヨーロッパ、とくにドイツにおける共産革命であった。だが、第一次大戦後、ドイツで共産革命を目指したスパルタクス団が暴動を起こすものの失敗し(1919年)、指導者のカール・リープクネヒトやローザ・ルクセンブルクが殺害されるに至って、この路線は完全に失敗する。1924年にレーニンが死去し、スターリンの時代になると、スターリンは「一国社会主義」(ソ連だけで社会主義国家を建設していく)という方針を打ち出しつつ、矛先を東アジアにおける主要な仮想敵である日本に向けるようになっていく。
コミンテルンの手法は、敵の政権内部に共産主義者を浸透させて内部から攪乱・崩壊を狙うことである。現実に、ソ連のシンパが、日本陸軍や外務省など政権中枢に入り込んでいた形跡もある。
そしてソ連の対日戦略において、重要な場となったのがシナであった(ちなみに本書ではいわゆる「中国」のことを「シナ」と表記することを標準とする。それは本来、「中国」という言葉が「自分にとって一番大切な国」という意味であって、日本でも幕末に至るまで自国〈=日本〉を「中国」と記す例があったからだ。しかも「中国」という場合、華夷思想に基づいて、周辺国は「蛮族」だという認識も付随する。翻って「シナ」という言葉は英語の「China」と同義であり、なんら差別的意味合いはない。「中国」は中華民国 、あるいは中華人民共和国の略称、あるいは現在のシナ大陸の政権を指すのに用いる)。ソ連は中国共産党と国民党にそれぞれ援助を与えつつ、両党を合作(国共合作)させ、反日運動を煽っていた。
その際、ソ連にとっての大いなる邪魔者の一人が、軍閥として満洲から華北を支配していた張作霖であった。
もともと張作霖は満洲の馬賊(盗賊などへの自衛のために結成された非合法の軍事集団、匪賊〈ひぞく〉)に加入してめきめき頭角を現わし、日露戦争では日本軍のスパイとしても...