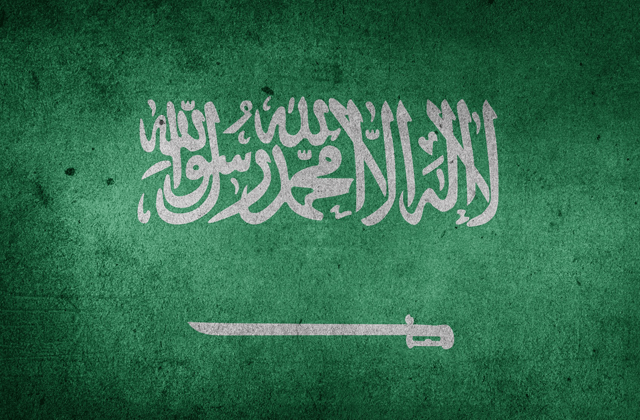
「世界一裕福な国」サウジアラビアが抱える問題点
2017年3月にサウジアラビアのサルマン国王が来日しました。サウジ国王の来日は46年ぶりということに加え、王族一族を引き連れての旅が話題となりました。その豪勢な様子にさまざまな業界の「特需」が噂されたほどなのですが、実際には「世界一裕福な国サウジアラビア」の神話は崩れつつあるのです。
もともとサウジアラビアは石油をはじめとする地下資源が豊富な国。労働の対価で稼ぐことなく、地下から湧きあがってくる資源で国家収入を得てきました。このような非稼得性の収入で成り立っている国を「レンティア国家」と呼びます。石油という天然の恵みから得た利益は国民に再配分され、教育や医療を無料にしたり、福利厚生を手厚くして日常生活においても高い支出をしなくて済むようにするなどして、国家が人々の生活を支えてくれます。働き蜂国家日本から見れば、夢のような国がサウジアラビアだったのです。
しかし、2016年に入り原油価格は急激に下落しました。このことが国家収入を石油に依存していたサウジアラビアの財政を直撃し、今や「世界一裕福な国」は財政赤字に息もたえだえの国になったのです。
サウジアラビアの国教は、イスラムスンナ派の厳格化を求めた流れにあるワッハーブ派で、シーア派盟主国であるイランとの対立は、歴史的にも長く根深いものがあります。また、復古的な禁欲主義であるワッハーブ派を国教とし、市民に対しても厳格なイスラム法を適用する一方で、サウジアラビアの王族やエリートは海外で享楽主義的な消費行動をとることで知られています。こうしたサウジアラビアが見せる建前と本音、いわば二重基準を、イランは厳しく批判してきました。
イランが、原油安であるにもかかわらず増産を打ち出し、サウジアラビアに低価格での消耗戦争を挑んでいる背景には、こうした積年の対立関係があるのです。
サウジアラビアとイランの関係を注視しつつ、「国民があくせく働かなくても暮らしていける国」などという幻想は抱かずに、日本は日本らしく真面目にコツコツ働くのが一番のようです。
原油価格の下落でレンティア国家存続の危機
サウジアラビアは今、多くの問題点、不安材料を抱えており、巨額の財政赤字に陥っている、と歴史学者の山内昌之氏は語ります。その最大の要因となっているのが原油安です。もともとサウジアラビアは石油をはじめとする地下資源が豊富な国。労働の対価で稼ぐことなく、地下から湧きあがってくる資源で国家収入を得てきました。このような非稼得性の収入で成り立っている国を「レンティア国家」と呼びます。石油という天然の恵みから得た利益は国民に再配分され、教育や医療を無料にしたり、福利厚生を手厚くして日常生活においても高い支出をしなくて済むようにするなどして、国家が人々の生活を支えてくれます。働き蜂国家日本から見れば、夢のような国がサウジアラビアだったのです。
しかし、2016年に入り原油価格は急激に下落しました。このことが国家収入を石油に依存していたサウジアラビアの財政を直撃し、今や「世界一裕福な国」は財政赤字に息もたえだえの国になったのです。
サウジアラビア国内の不安材料
もはやレンティア国家として存続できなくなっているサウジアラビアの不安材料は、国内外で増しています。国内の不安要因の第一は、人口約3000万人の70パーセントが30歳以下の若年層であること。少子高齢化社会・日本とまったく逆の人口バルジ(厚み)を見せるこの人口構成は、近い将来に大量の不完全雇用、失業状態を生むということを意味しています。職を失い不満を抱える若者が、イスラム国やアルカイダにひかれていくことも懸念され、すでにその兆候は表れているといわれています。さらに、主に重労働、肉体労働を担っている800万人におよぶ外国人労働者の不満も募ってきており、国内秩序、国政の安定に影をおとしているのです。国外からはイランの脅威
国内でこれだけの不安要素を抱えるサウジアラビアですが、対外的な問題も多く、そのなかでもイランによる圧力、軋轢が最も大きい、と山内氏は語ります。サウジアラビアの国教は、イスラムスンナ派の厳格化を求めた流れにあるワッハーブ派で、シーア派盟主国であるイランとの対立は、歴史的にも長く根深いものがあります。また、復古的な禁欲主義であるワッハーブ派を国教とし、市民に対しても厳格なイスラム法を適用する一方で、サウジアラビアの王族やエリートは海外で享楽主義的な消費行動をとることで知られています。こうしたサウジアラビアが見せる建前と本音、いわば二重基準を、イランは厳しく批判してきました。
イランが、原油安であるにもかかわらず増産を打ち出し、サウジアラビアに低価格での消耗戦争を挑んでいる背景には、こうした積年の対立関係があるのです。
レンティア国家という幻想
サウジアラビアが音頭を取って結成したGCC(湾岸協力会議)は元来、イランの脅威に対抗してつくられたものですが、今、サウジアラビアをはじめとするクウェート、バーレーン、カタールなどのGCC諸国は、その多くが原油安の影響で、国家財政の見直しを迫られているのが実情です。サウジアラビアとイランの関係を注視しつつ、「国民があくせく働かなくても暮らしていける国」などという幻想は抱かずに、日本は日本らしく真面目にコツコツ働くのが一番のようです。
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







