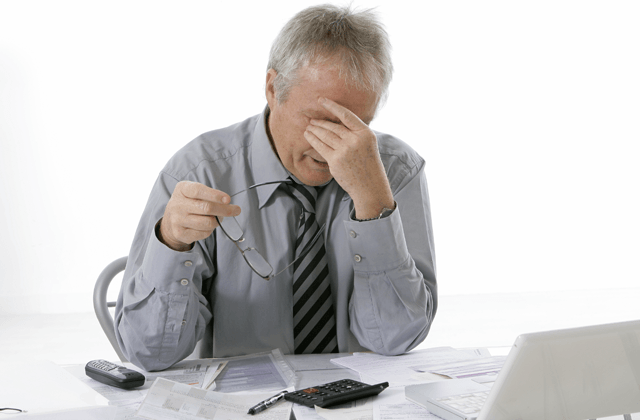
作業能率は起床後15時間で「飲酒運転」と同じ?
起床後長時間経過の怖い話
みなさん、睡眠をしっかりとっていますか。寝る時間が遅くなりすぎたりしていないですか。多忙な日々を送る社会人の中には、就業時間を過ぎていてもずっと残って作業を続けている、という方もいると思います。以前にTwitterで、以下のツイートが話題となりました。
「人間が十分に覚醒して作業を行うことが可能なのは起床後12~13時間が限界であり、起床後15時間以上では酒気帯び運転と同じ程度の作業能率まで低下する」(情報産業労働組合連合会のツイートより)
酒気帯びと同じとは、衝撃的ですね。近年相次いだバス事故や自動車の事故も過酷な労働環境によるものだという指摘がありました。
このツイートの情報元は厚生労働省から出されている、『健康づくりのための睡眠指針2014』です。さらにそこが参考としている科学誌Natureの論文(1997年に発表)によると、さらに時間がたち17時間起きていた場合、アルコール血中濃度が0.05%の状態と同じになるといいます。
さらに怖いのが、作業能率が著しく落ちているにもかかわらず、自分はそれに気づかないこと。強い眠気を感じないので大丈夫だと思い込んでしまうのですが、実際はものすごくパフォーマンスが悪くなっているのです。
「やっていけるかも」が実は危ない
一方、どうしても過酷な環境で働かなくてはならない場合、対処法として「寝だめ」をしようと考える人があります。例えば、平日に十分寝られない分、休日にまとめて長時間の睡眠をとるといった方法です。これについて『健康づくりのための睡眠指針2014』によると、作業能率の改善には効果があるとしながら、夜間の睡眠を妨げて、疲労を蓄積する原因になるかもしれないということです。こうしてたまった疲れは、簡単には取り除けないといいます。
そして、一番やっかいなのは、「なんとなくやっていけてしまう」というところ。もうだめだ、と限界を感じるよりも少し手前、あるいはギリギリの状態で頑張っている人が、疲労の蓄積によって体調を崩してしまうというケースが多いのではないでしょうか。
睡眠のしかたが鍵を握る
先述のツイートで問題となっていたのは、長時間労働による作業能率低下と、ヒューマンエラー、そして事故のリスクが高まる危険性ですが、『健康づくりのための睡眠指針2014』では、睡眠の質もまた重要視されています。たとえば、心身ともに心地よく目覚めさせるため、朝食をとること、寝酒や就寝前のカフェイン摂取・喫煙を避けること、定期的な運動をすることなどを勧めているのですが、それは、そうした生活の改善による良質な睡眠が重要だということです。この中で、意外と守れていないこともあるのではないでしょうか。やはり規則正しい生活が一番なんですね。
それでも、「この日までに終わらせなくては」の仕事の連続だという人も少なくないかもしれません。どうしても夜間に十分な睡眠をとれない場合、「午後の早い時刻に30 分以内の短い昼寝をすることが、眠気による作業能率の改善に効果的」とのこと。簡単ではないかもしれませんが、意識してみてはいかがでしょう。
ちょっとした手違いやミスで、大きな事故やトラブルにつながることもあります。そうならないためにも、無理をしない生活を心がけたいものですね。
<参考サイト>
・情報産業労働組合連合会(情報労連)公式Twitter
https://twitter.com/infoictj/status/808476571258396672
・厚生労働省ホームページ(健康づくりのための睡眠指針2014)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
・情報産業労働組合連合会(情報労連)公式Twitter
https://twitter.com/infoictj/status/808476571258396672
・厚生労働省ホームページ(健康づくりのための睡眠指針2014)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子
毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング
長谷川眞理子







