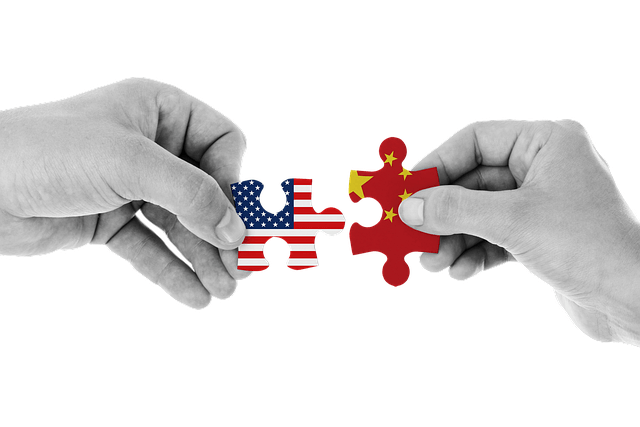●トランプ政権4高官演説に見る「新冷戦」の影
小原 前回お伝えしましたポンペオ国務長官の演説は、この資料に書いたシリーズで行われた4番目の演説でした。
―― はい。
小原 彼自身は、先ほど言ったように、ニクソン大統領以来の関与政策をやめるということを、外交の責任者である国務長官として宣言したわけです。この演説はニクソン大統領記念図書館で行われましたが、まさにそうしたことを頭に置きながら、この場所を選んだということです。
最初の大統領補佐官から始まって、FBI長官、司法長官など、みんなが一緒になって、「ターゲットは中国共産党」だと言っています。つまり、中国という国家というよりも共産党というものをターゲットにして、4氏が演説をしているわけです。一つのポイントとして頭においていただきたいのは、まさにイデオロギーがそこに出てきているということです。
これがまず、「新冷戦」だと言われる理由の一つだと思います。つまり、冷戦というのは一体何だったかというと、いろいろな特徴があるわけですが、一つの特徴がイデオロギー闘争です。今まで貿易戦争など、いろいろなことがあったけれど、米中では必ずしもそこまでいっていませんでした。ところが今、新冷戦が出てきはじめました。「新冷戦は本当に新冷戦なのか」という議論が今までありましたが、新冷戦の影がここにもう出てきているということです。
―― ポンペオ氏などは、言ってみれば完全に「敵認定」のような、かなり激しい言葉を使っていますよね。
小原 そうですね。
●米中間の勢力均衡の鍵を握るのはシーレーン
小原 米中間の問題でもう一つ気をつけないといけないのは地政学であり、パワーシフトやパワーバランスともいわれる「勢力均衡」です。この地図では太平洋や東アジアを軸に、中国がどのような姿勢を押し出しているか、それに対してアメリカがどう食い止めようとしているかを図示しました。
この資料を見る一つのポイントは、「第1列島線」「第2列島線」「第3列島線」という概念です。
1950年、当時の国務長官だったアチソン氏は、アメリカが責任を持つ防衛ラインとして、フィリピン-沖縄-日本-アリューシャン列島を結ぶ「アチソンライン」を表明しました。ここに韓国が入ってい...