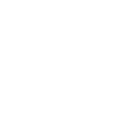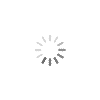本当のことがわかる昭和史《7》歴史を愛する日本人の崇高な使命
真珠湾攻撃…なぜ日本の宣戦布告が遅れたのか?
本当のことがわかる昭和史《7》歴史を愛する日本人の崇高な使命(1)真珠湾攻撃を「騙し討ち」にした大失態
渡部昇一(上智大学名誉教授)
国の名誉ということを考えた場合、どうしても許してはいけないことが起きてしまった。それは、対米戦争開始時、真珠湾攻撃を「日本の卑怯な騙し討ち」にしてしまった、許すべからざる外務省の出先機関の業務遅滞である。上智大学名誉教授・渡部昇一氏によるシリーズ「本当のことがわかる昭和史」第七章・第1回。
時間:6分11秒
収録日:2015年2月2日
追加日:2015年9月21日
収録日:2015年2月2日
追加日:2015年9月21日
カテゴリー:
≪全文≫
これまでの章で、大東亜戦争に至る歴史の大きな流れを概説してきた。あの時代、さまざまな思惑により激動していく国際情勢の中で、日本人が何を考え、どう行動したかということに着目して、歴史を物語のように記述することを試みた。
単純なる東京裁判史観ではけっして語れぬ部分があることを、おわかりいただけたのではないかと思う。そして日本人の正義、日本人のガッツの源がどこにあったのかも。
しかし、国の名誉ということを考えた場合、どうしても許してはいけないことが起きてしまった。
対米戦争開始時のこと──つまり、真珠湾攻撃を「日本の卑怯な騙し討ち」にしてしまった、許すべからざる外務省の出先機関の業務遅滞である。
御前会議で対米戦が決定したあと、天皇陛下は東條英機首相に開戦手続きをきちんと行なうように伝え、山本五十六連合艦隊司令長官も、対米最後通告が間違いなく真珠湾攻撃前に届く手筈になっているかどうかを、何度も確認していた。
現地時間で昭和16年(1941)12月6日の朝、東郷茂徳外務大臣からワシントンDCの駐米日本大使館に宛てて、「対米覚書を発信するので明日、本国からの訓令十四部が届き次第、アメリカ政府にいつでも手渡せるよう準備するように」と命じるパイロット電報が届いた。
ところが6日夜は、戦後に『昭和天皇独白録』を書いたことでも知られる寺崎英成一等書記官の送別会があり、大使館員たちは出払っていた。翌朝7時に最後の十四部が届いたが、大使館員は出勤しておらず、大使館に膨大な電報が届いているのを見つけた海軍の実松譲駐在武官補佐官が大使館員に連絡したという。
日本大使館には、最後通告をワシントン時間の12月7日午後零時半(日本時間の12月8日午前2時半、ハワイ時間の7日午前7時)にアメリカ政府に渡すよう命令があったが、そのあと30分繰り下げてワシントン時間の午後1時にアメリカ政府に渡すように指示された。そこでハル長官に1時に会ってもらうことにしたが、暗号解読とタイプが間に合わない。そこで、なんと彼らは、とんでもない判断を下した。ハル長官に電話をかけて、独断で「面会時間を延ばしてほしい」と頼んだのだ。結局、野村吉三郎大使と来栖三郎特命全権大使が最後通告をハル長官に手渡したのは1時間20分遅れの2時20分で、真珠湾攻撃後すでに50分が経っていた。
これは...
これまでの章で、大東亜戦争に至る歴史の大きな流れを概説してきた。あの時代、さまざまな思惑により激動していく国際情勢の中で、日本人が何を考え、どう行動したかということに着目して、歴史を物語のように記述することを試みた。
単純なる東京裁判史観ではけっして語れぬ部分があることを、おわかりいただけたのではないかと思う。そして日本人の正義、日本人のガッツの源がどこにあったのかも。
しかし、国の名誉ということを考えた場合、どうしても許してはいけないことが起きてしまった。
対米戦争開始時のこと──つまり、真珠湾攻撃を「日本の卑怯な騙し討ち」にしてしまった、許すべからざる外務省の出先機関の業務遅滞である。
御前会議で対米戦が決定したあと、天皇陛下は東條英機首相に開戦手続きをきちんと行なうように伝え、山本五十六連合艦隊司令長官も、対米最後通告が間違いなく真珠湾攻撃前に届く手筈になっているかどうかを、何度も確認していた。
現地時間で昭和16年(1941)12月6日の朝、東郷茂徳外務大臣からワシントンDCの駐米日本大使館に宛てて、「対米覚書を発信するので明日、本国からの訓令十四部が届き次第、アメリカ政府にいつでも手渡せるよう準備するように」と命じるパイロット電報が届いた。
ところが6日夜は、戦後に『昭和天皇独白録』を書いたことでも知られる寺崎英成一等書記官の送別会があり、大使館員たちは出払っていた。翌朝7時に最後の十四部が届いたが、大使館員は出勤しておらず、大使館に膨大な電報が届いているのを見つけた海軍の実松譲駐在武官補佐官が大使館員に連絡したという。
日本大使館には、最後通告をワシントン時間の12月7日午後零時半(日本時間の12月8日午前2時半、ハワイ時間の7日午前7時)にアメリカ政府に渡すよう命令があったが、そのあと30分繰り下げてワシントン時間の午後1時にアメリカ政府に渡すように指示された。そこでハル長官に1時に会ってもらうことにしたが、暗号解読とタイプが間に合わない。そこで、なんと彼らは、とんでもない判断を下した。ハル長官に電話をかけて、独断で「面会時間を延ばしてほしい」と頼んだのだ。結局、野村吉三郎大使と来栖三郎特命全権大使が最後通告をハル長官に手渡したのは1時間20分遅れの2時20分で、真珠湾攻撃後すでに50分が経っていた。
これは...