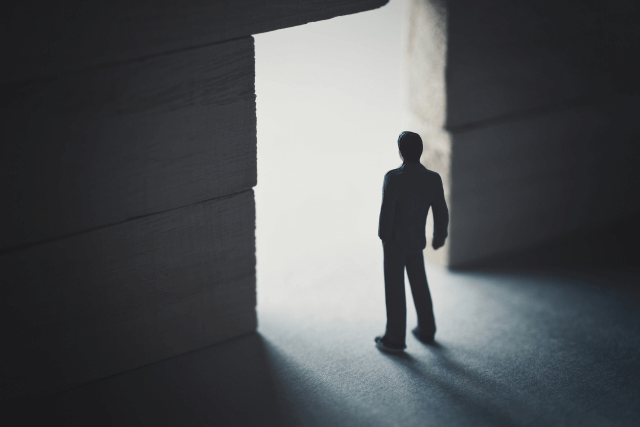●全ての根源にある「善のイデア」を求めて
理想の国家を実現するためには、哲人統治が唯一の、しかも可能な手段であるという提案を受けて、哲学者がどうやって政治に関わるのか、いったい哲学者がどうやってこれを実現するのかということが、もう一歩(踏み込んで)語られていきます。
「哲学者はイデアを見る者。真理を見る者である」と言われるときに、最終的にそのような哲学者となるために学ばれるべきものは「善のイデア」であるといわれます。
イデアにはおそらくいろいろな種類があるのでしょう。正義のイデア、美のイデア、勇気のイデアなどが存在するのだと思います。そういった諸々のイデアではなく、さらに究極にある「善い」ということの本質を見なくてはいけない。これが、学ぶべき最大のものといわれる「善のイデア」であり、これをめぐって3つの比喩が語られていきます。これを簡単に見ていきたいと思います。
「善い」というのは、いったいどういうことなのか。「正しい」ということでも十分にすごいものですが、ソクラテスは「『正しい』ということを本当に言い切るためには、さらに究極の『善い』ということを把握しなくてはいけない」「『善い』ということは、『正しい』とか『美しい』といったことを超えた、より根源的なものなのだ」という見通しを述べます。ソクラテスはこのことを「知っている」とは言いません。「私ももちろんよく分からないのだが、そうだと予感している」という言い方をします。
「善い」とは、例えば私の体にとって善いのは善い食事や適度の運動などというように、普通は相対的に使われます。しかし、その原理は何なのか。私の体にとって善いとはどういうことか。体が善ければいいのか。生きるとはどういうことなのか。こういうことを突き詰めていくときに、「善い」とは何かということを判断する。これを見極めることが、哲人統治する哲学者の最終目標であり、かつその前提になるわけです。
そんなに簡単に「『善い』とは、こういうことです。はい、勉強してください」というわけにはいかない。そこでソクラテスは、「自分は予感だけしているけれども、あえて比喩のような形で、『善のイデア』とはこういうものではないか、ということは提示できる」と言います。
●善のイデアに向かうための3つの比喩
これは何か不思議ですね。知っていないのだけれ...