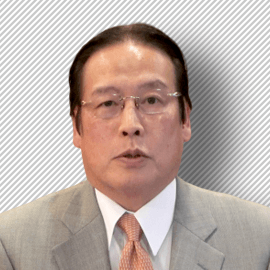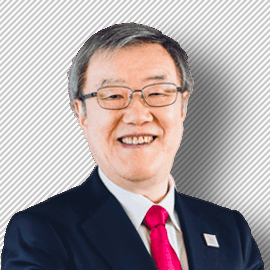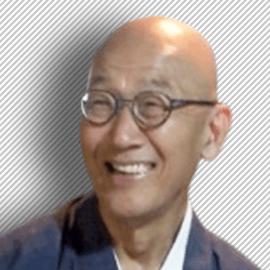仕事の標準・単純・専門化が労働を苦役化した
労働寿命と健康寿命の延伸(2)日本人の労働観
第1話では、健康長寿を保つための社会参画、とりわけそれが日本人にとっては「働く」ことの大切さにつながることを説いた。今回は、「働く」という言葉を手がかりにして、一般財団法人日本予防医学協会理事長の神代雅晴氏が、日...
収録日:2018/02/22
追加日:2018/04/28
思春期は何歳まで?前頭前野が司る大人になるための仕組み
ヒトはなぜ罪を犯すのか(2)脳の構造と働き
脳の構造と情動・認知の進化はつながっている。脳内にある進化的に古い「大脳辺縁系」は何をしたらいいかという「動機づけ」に関与しているところで、そことその上にある「新皮質」の中の前頭連合野(前頭前野)が密接に関連し...
収録日:2023/12/11
追加日:2024/03/03
「脳のしわが多いと頭がいい」は誤解…ヒトの脳の特異点
知られざる「脳」の仕組み~脳研究の最前線(4)脳の構造と特徴
マウスを使った脳研究の成果は、ヒトの脳へすぐに応用できるわけではないという。それでは、ヒトの脳と他の動物の脳には、具体的にどのような違いがあるのだろうか。脳の画像を見比べると、ヒトの脳の明らかな特異点が見えてく...
収録日:2022/10/21
追加日:2023/07/24
脳科学的に大人は30歳!? 脳の奥にある人間の特色
心と感情の進化(2)「知情意」と脳の関係
日本には昔から「知情意」という言葉があり、知にあたる認知・認識だけではなく、情にあたる感情・情動や、意にあたる意志も尊重される文化が育まれてきた。このことは、現代の脳科学によって感覚器と脳の関係、脳の構造が明ら...
収録日:2022/04/21
追加日:2022/08/07
本を買って書棚に並べれば、読まなくても知性は高まる
渡部昇一に学ぶ教養と明朗(9)本は自分で所有する
渡部昇一先生の書籍に対する根本的態度は、「本は自分で所有する」ということだった。電子書籍よりも、紙の本がいい。自分が必要だと思ったら、自分の本なのだから、赤線を引いたり、書き込んだりすることをためらわない。そう...
収録日:2020/09/09
追加日:2020/12/04
認知症にも影響する睡眠…グリンパティック・システムとは
「最高の睡眠」へ~知っておくべき睡眠常識(2)なぜ睡眠が必要なのか
睡眠はそもそもなぜ必要なのか。「最高の睡眠」シリーズの第2話では、1950年代以降という睡眠医学の歴史を振り返りつつ、睡眠が人間にとって不可欠である理由をたずねていく。とりわけ重要な「グリンパティック・システム」とは...
収録日:2021/06/23
追加日:2021/10/28
「なぜ売れないのか」は追及せず、今と将来だけを考える
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(7)幸せの正体とは
キリンビールの東海地区の営業責任者だった時代には、毎週月曜日に全員にメールを出し、今週やる仕事の意味と「使命が果たされた現場」の様子を伝えた。これによりどう動けばいいかがわかり、情報を共有することで刺激を得られ...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/09/26
抗ヒスタミン薬が効かないかゆみは、どう対処する?
かゆみのメカニズム(2)かゆみの分類と伝達経路
誰もが味わう“かゆみ”には、いまだ解明されていないことが多い。今回はかゆみがどのように起きるのか。かゆみの二つのタイプとそれぞれの刺激が伝えられるメカニズムについて、順天堂大学名誉教授で同大学院皮膚科学特任教授の...
収録日:2015/11/12
追加日:2016/02/11
人類史における科学・技術の原動力は「欲求」
知性の進化と科学技術文明の未来(2)科学と技術は別物か
現在の科学技術文明があまりにも急激に進んできたことに、人類学の立場から疑問を覚えているのが、総合研究大学院大学長の長谷川眞理子氏である。今回は、科学の考え方はどこでどのように始まり、どう発展してきたのかを振り返...
収録日:2017/10/18
追加日:2018/01/20
知られざるデカルトの科学者としての功績
デカルトの科学論に学ぶ(2)デカルトの功績と科学革命
17世紀は「科学革命」の時代であるとも言われる。ガリレオやニュートンによる科学的発見など、実験や観察による進展が多くの分野で見られたが、デカルトもまた、物理学、医学や天文学において多くの科学的な発見をした人物であ...
収録日:2018/09/27
追加日:2019/03/28
生涯にわたる口腔ケアは人類に健康・幸福をもたらす
「噛める」ことこそ、健康維持の要点(2)脳の活性化
噛んで食べ、咀嚼することは、脳に良い影響をもたらすことが最新の研究で分かってきた。物をよく噛むことで、さまざまな脳神経が活性化し、認知症の予防にもなる。さらには、高齢化で増大する医療費問題に歯止めをかける手段に...
収録日:2019/11/14
追加日:2020/06/29
赤ちゃんの脳を人間の脳にする「リリーシング」とは
98歳の医師が明かす「生物学的教育論」(3)「リリーシング」としつけ
生物学的な観点から教育を見ると、年齢に応じて必要な教育は異なる。赤ちゃんに必要なのは、人間としての脳にするために重要な「リリーシング」という働きかけである。赤ちゃんは親の表情や行動などから非常に多くの影響を受け...
収録日:2020/01/11
追加日:2020/07/09
家族の対話は問題解決型ではなく、「心の対話」をすべし
黒川伊保子先生に学ぶ「子育てのトリセツ」(5)心の対話と問題解決の対話
男性脳と女性脳の違いを踏まえたうえで、家族でうまくコミュニケーションを取るにはどうすればいいか。黒川伊保子氏によると、家族での対話はおしなべて「心の対話」をすべきだという。多くの男性が苦手とする「心の対話」をす...
収録日:2021/06/28
追加日:2021/09/20
ガッツ、群集心理…人間の認知能力と情動の自己制御の方法
心と感情の進化(3)脳の進化とこれからの課題
人間の行動には、自己制御によって認知が強く作用するものから情動的なものまでさまざまで、そこにはグラデーションがある。また、人間には生存や繁殖には直接関わらないように見えるが、高度な能力がある。それは抽象化・一般...
収録日:2022/04/21
追加日:2022/08/14
頭が良い人ほど脳がスカスカ!? 鍵を握るのはアストロサイト
知られざる「脳」の仕組み~脳研究の最前線(8)「頭の良さ」とアストロサイト
「頭が良い人」とはどのような人のことをいうのだろうか。脳研究の結果、衝撃的な事実が報告されている。IQが高い人はIQが低い人に比べて「脳がスカスカしている」というのだ。一体どういうことなのか。実はそこには「アストロ...
収録日:2022/10/21
追加日:2023/08/21
うつの「見える化」に有効な光トポグラフィー検査とは
うつ病治療最前線(4)目に見える精神医療
ひもろぎGROUP理事長・東邦大学薬学部客員教授の渡部芳德氏は、「見えない」難しさを持つ精神医療にいち早く光トポグラフィーの機械を導入、検査を実施してきた。「見えない」ものを「見える」ようにした効果は絶大! 精...
収録日:2015/09/03
追加日:2015/11/26
「行動分析学」という心理学の面白いポイントとは
人の行動の「なぜ」を読み解く行動分析学(3)時空間分析
行動分析学という心理学の面白いポイントは、どんな行動でも「ABC分析」など同じ方法論でほとんど全てにアプローチできるところだと島宗理氏は言う。今回、そのことを「時空間分析」によって示しているが、はたしてそれはどのよ...
収録日:2019/02/21
追加日:2019/08/29
AIがどうしても人間に敵わないのが「混沌」
読書と人生(7)人間は、「混沌」を持つ存在である
第5回で、「読書の根本は、神秘に対面すること」と説いたが、この「神秘」はすなわち「混沌」でもある。「混沌」とは、「理論では解明できない1つの持続した思考」である。そのような「混沌」があることが、人間の人生が尊い唯...
収録日:2019/05/14
追加日:2019/09/27
子離れ、親離れで大事なのは、「心を離さない」ということ
98歳の医師が明かす「生物学的教育論」(5)10歳からの子育て
子どもは10歳になると、大脳が発達し始め自立して行動するようになる。この段階ではこれまでの我慢のしつけを抑えて、子どもが意欲的に物事に取り組むことを後押しするように切り替える必要があるという。そこで重要となるのが...
収録日:2020/01/11
追加日:2020/07/23
ゆとり教育の間違いは幼年期と青年期の教育の違いにある
98歳の医師が明かす「生物学的教育論」(6)幼年期と青年期の教育の違い
しつけと同様に、教育の方法も幼年期と青年期では異なる。幼年期の教育は、パターン認識としてひたすら知識を蓄えていき、中学から高校にかけての青年期は、そうした知識を論理的に理解していく教育が望まれる。この違いにゆと...
収録日:2020/01/11
追加日:2020/07/30
世界共通なのは、「年功序列」ではなく「成果序列」
『還暦からの底力』に学ぶ人生100年時代の生き方(3)「年齢フリー」の社会にする
人間にとって一番怖いのは、分からないということだ。若いときは分からないことも多いが、人生を半分走ってきた60歳はその分、世の中のことが分かっているから、何事にも上手に対応できるだろうし、チャレンジもしやすい。そこ...
収録日:2020/06/30
追加日:2020/08/15
青年期の暴走には脳の変化と感情面の実行機能に関係がある
「自分をコントロールする力」の仕組み(4)実行機能発達のメカニズム
なぜ実行機能は幼児期に著しく発達するのか。3歳から5歳にかけての子どもを対象とした研究で、実行機能の発達は脳の成長と密接な関係があることが分かった。実行機能は幼児期に著しく発達した後、思考面は緩やかに発達していく...
収録日:2020/12/08
追加日:2021/03/21
「私が世界で、世界が私」…禅で体感する「縁起」の感覚
禅とは何か~禅と仏教の心(4)与格への変容と関係論的世界観
欲望を軸とした根本構造の誤りに気づいて坐禅を組んでいると、私が主格から与格へ変容するという。私へのとらわれがなくなると、仏教の大きな教えである「縁起」のしくみもおのずと判然する。それは全てが関係の網の目の中で起...
収録日:2024/08/09
追加日:2025/02/03