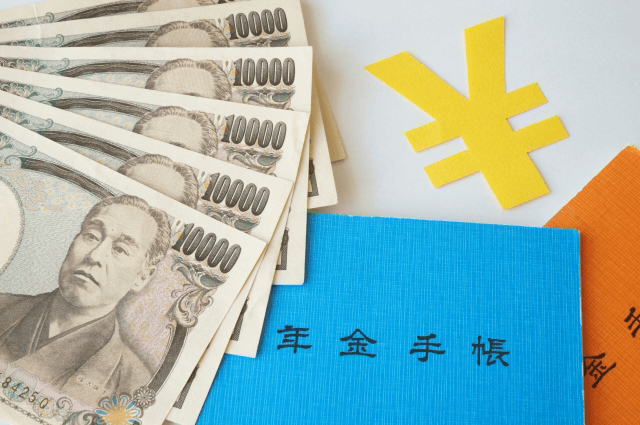●「年金村」の社会的影響力は極めて大きい
財政や社会保障の仕組みを、国民に対して意図的に分かりにくいものにしているメカニズムの2つ目が「年金村」です。年金についても、「国債村」と似た政治社会集団が存在しているのです。ただし、「年金村」は「国債村」のように、それなりに制度化され、参加者も知られ、議事録もあるというような、目に見える存在ではありません。「年金村」の参加者が誰かは、当事者が部分的に知るだけで、参加の程度も人それぞれで、全貌は不透明です。議事録どころか記録も、全くありません。しかし、その社会的影響力は、実は極めて大きいといわざるを得ないと思います。
なぜなら、年金制度に象徴される社会保障の諸制度は、国民各層の生活と人生を支え、できるだけの安定を保障する制度だからです。その制度が設計され、機能する社会は、しかし常に変動します。制度の受給者もさまざまですし、歳を重ねていけば、体力も能力も変化します。病気や障害のある人々も多い。そうした国民各層の個人の全生涯にわたって、一定の生活保障を提供するという仕組みですから、必然的にそれは膨大かつ複雑なものになるのです。
実際、社会保障制度は、社会経済や国民全員の年々の変化に応じて改定され、時機に応じて大規模な改革が必要となるシステムです。その改変や改革は、政府の担当部局である厚生労働省の担当責任者が常に構想し、準備します。改変や改革のプロセスには、当然、内閣や政党、政治家、労働組合、経営者、メディアや世論などが深く関わります。システムの改革は、そうしたプレーヤーたちの政治的な相互作用の結果として、ようやく結実するものです。
●1980年代、旧厚生省の幹部が大改革に取り組んだ
日本の年金制度は、第二次大戦中に戦費調達の一環として発足しましたが、戦後には再構成されて、経済発展の過程で、勤労者そして一般国民の老後生活の一定の保障を提供する制度として発展してきました。日本経済の発展過程では、拠出基金の蓄積も少なく、経済社会も激しく変化したので、さまざまな制度がその都度、必要に応じて設定され、またその都度、修正されてきており、全体としては統合性のない煩雑な制度になっています。
ところが、高度成長期が終焉に向かう1980年代に入ると、年金行政を司る旧厚生省の幹部たちが、歴史的画期となる大改革に取り組むことになり...