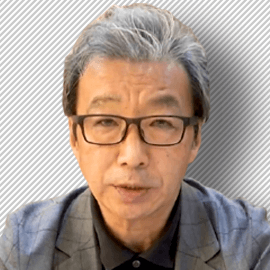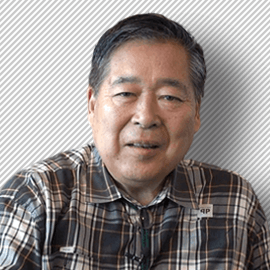欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
「進化」への誤解…本当は何か?(6)木村資生の中立説
ダーウィンの進化論以降、生物の進化に関する議論はどのように発展してきているのか。重要な議論として、木村資生(国立遺伝学研究所名誉教授)の中立説がある。生物の生存と繁殖に必ずしも関連しない、分子レベルでの変異を計...
収録日:2025/05/17
追加日:2026/01/20
質疑編…司馬遼太郎の「史料読解」をどう評価する?
歴史の探り方、活かし方(7)史料の真贋を見極めるために
歴史上の出来事の本質を知るには、その真贋を見定めなければいけない。そのためにはどうすればいいのか。記述の異なる複数の本がある場合、いかにして真実を見極めるか。また、司馬遼太郎の作品が「歴史事実」として認識されて...
収録日:2025/04/26
追加日:2025/12/02
史料読解法…江戸時代の「全国の藩校ランキング」を探る
歴史の探り方、活かし方(6)江戸時代の藩校レベルを分析
江戸時代の藩校に関する研究は多いが、当時は藩ごとに小国家を形成していたため、学力水準を全国で比較したものは見当たらない。では、あえて「全国藩校ランキング」を考えるとすると、どの藩の藩校が「トップ校」になるのだろ...
収録日:2025/04/26
追加日:2025/11/29
『武功夜話』は偽書か?…疑われた理由と執筆動機の評価
歴史の探り方、活かし方(5)史実・史料分析:秀吉と秀次編〈下〉
豊臣秀次事件に対する見方を変えた『武功夜話』だが、実は偽書疑惑もある。今回は、そのことに鋭く迫っていく。『武功夜話』は、豊臣秀吉に仕えて大名まで上り詰めた前野長康の功績を中心に記された史料だが、その発表・出版の...
収録日:2025/04/26
追加日:2025/11/28
歴史作家・中村彰彦先生に学ぶ歴史の探り方、活かし方
編集部ラジオ2025(29)歴史作家の舞台裏を学べる
この人生を生きていくうえで、「歴史」をひもとくと貴重なヒントにいくつも出会えます。では、実際にはどのように歴史をひもといていけばいいのか。
今回の編集部ラジオでは、歴史作家の中村彰彦先生がご自身の方法論をわかり...
収録日:2025/10/17
追加日:2025/11/27
史料読解法…豊臣秀吉による秀次粛清の本当の理由とは?
歴史の探り方、活かし方(4)史実・史料分析:秀吉と秀次編〈上〉
実際に史料をどうやって読み解いていけばいいのか。今回から具体的な史料の読み解き方をケース・スタディしていく。最初は『太閤記』に関する参考資料を用いて、太閤・豊臣秀吉と関白・秀次の関係を考える。そもそも『太閤記』...
収録日:2025/04/26
追加日:2025/11/22
ネット古書店で便利に買える時代…「歴史探索」の意義とは
歴史の探り方、活かし方(3)古書店巡りからネット書店へ
古本のインターネット書店が充実し、史料探しはずいぶん楽になった現在だが、地方にある書店の地元出版コーナーも見逃せない。新書などの文献目録を参考にするという手もあると中村氏は言う。ではそうして歴史を調べ、たどって...
収録日:2025/04/26
追加日:2025/11/21
図書館の便利な活用法…全国の図書館からの「お取り寄せ」
歴史の探り方、活かし方(2)図書館「レファレンス」の活用
公共図書館では質の高い「レファレンス」サービスを提供しているが、活用する人は限られている。だが、実は全国の図書館ネットワークを縦横無尽に活用できる、驚くほどに便利な仕組みなのだ。今回は図書館のレファレンスで何が...
収録日:2025/04/26
追加日:2025/11/15
日本は素晴らしい歴史史料の宝庫…よい史料の見つけ方とは
歴史の探り方、活かし方(1)歴史小説と史料探索の基本
「歴史を探索していく」とは、どういうことなのだろうか。また、「歴史を活かしていく」とはどういうことなのだろうか。歴史作家の中村彰彦氏に、歴史を探り、活かしていく方法論を、具体的に教えてもらう本講義。第一話は、歴...
収録日:2025/04/26
追加日:2025/11/14
本当の自分とは「見つける」のではなく「出会う」もの
人生と仕事観(10)理不尽なものも全て受け入れる
やりがいは結果論である。今の企業は「生きがいを持って、自分らしい人生を送ってくれ」と社員に言うが、結果として精神を病んだり、辞めたりする社員が増えている。「自分らしさ」とか「本当の自分」は自分ではわからず、外か...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/11/14
「喜んでもらいたい」が自由を生み、自由が勇気を生む
人生と仕事観(9)売上と自由と勇気
人間は忙しいときほど、エネルギーが出る。忙しいときほど新しいことを始めるのは、人間の生命エネルギーである。また、そのとき、「自分たちで決められる」という自由があれば、勇気も湧いてくる。ただし、企業の場合、そこに...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/11/07
制約を乗り越えていくことでこそ「真の自由」が得られる
人生と仕事観(8)いかに「規範を作り直す」か
今は会社でも規範がいろいろと崩れてきているが、キリンビールでは規範を作り直すことができた。それは、絶対的なものに向かうことで真の自由を得て、自分が何者かに気づいたからである。会社には予算や人材などさまざまな制約...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/10/31
「貧」をバカにしない社会を取り戻すには歴史と伝統を学べ
人生と仕事観(7)貧富の格差の問題
いま、「会社は投資家のもの」という時代になり、貧富の格差の問題が大きくなっている。だが、考えてみればかつては金持ちが貧者をバカにするような社会ではなかったし、貧者も必要以上に金持ちを妬(ねた)んだり嫉(そね)ん...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/10/24
仕事には「意味」が不可欠だが、数字は「意味」にならない
人生と仕事観(6)数字は「意味」にならない
フランスのワイン会社の序列は、売上げでは決まらない。ワイン通と認められた50人ほどが決める。つまり評価基準は質が重要であって、売上げだけではないのだ。一方、アメリカングローバリズムは、売上げだけを見るような社会で...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/10/17
なぜ「キリンのビールが最高」という信念を持てるのか
人生と仕事観(5)覚悟こそ幸福への条件
最後は「自分がやるんだ」という覚悟があれば、大変なことでも本人は「大変」と感じないものである。その覚悟は何かというと、勇気である。ただ最近のキーワードは「勇気」ではなく「幸せ」。誰かのために行動して役に立てば、...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/10/10
企業理念でも何でも「信じる」ことは全部勇気の問題
人生と仕事観(4)勇気をもって初心に返れ
どの会社も「理念」とは、創業のときの「初心」である。一番美しいのも初心であり、初心に返ることが重要である。創業のときに何を思い、何をしたかを調べ、それらを土台にすることで、組織はバラバラにならずに済む。初心を信...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/10/03
理念こそが「新陳代謝=売上げ」のダイナミズムを強化する
人生と仕事観(3)企業理念は「世の中の役に立つ」こと
真の人間の生き方とは、魂を燃やすことである。魂は、利益や世間からの評価では燃えない。絶対的な価値に向かっているときだけ燃えるのである。企業理念は「自分たちのあり方で世の中の役に立つ」ということであり、そこに向か...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/09/26
経営とは数字やフレームワークではなく「生き方」である
人生と仕事観(2)「欧米の形式知」対「日本の暗黙知」
経営学者の野中郁次郎氏は日本敗戦の屈辱をリベンジするためにも、アメリカに渡って経営学を研究した。アメリカの思想に対し、日本の思想で戦おうとしたのである。野中氏の経営学は日本の文明論でもあり、そこから「欧米の形式...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/09/19
日本人は「自分のため」だけではエネルギーが出てこない
人生と仕事観(1)日本人が頑張るのは誰かのため
日本はさまざまな分野で急激に衰退している。これは日本人の規律や規範が失われてきたからではなかろうか。ここで企業にとって大事なのは、企業理念を追究することで日本らしさを取り戻すこと。経済的には「失われた30年」とい...
収録日:2025/07/04
追加日:2025/09/12
契機は白村江の戦い…非常時対応の中央集権国家と防人の歌
「集権と分権」から考える日本の核心(2)非常時対応の中央集権と東アジア情勢
律令国家は中国の先進性に倣おうと始まったといわれるが、実際はどうだろうか。当時の日本は白村江の戦いの後、唐と新羅が日本に攻め込むのではないかという危機感から「防人」という徴兵制をつくった。徴兵には戸籍を充実させ...
収録日:2025/06/14
追加日:2025/08/25
村上春樹が『ノルウェイの森』で描いた不自然な嘘と真意
AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(5)『ノルウェイの森』の嘘とメンタル
村上作品の大ベストセラー小説『ノルウェイの森』。ここでも主人公の「僕」はわざと自分の立場を悪くするような嘘をついているのではないか、と加藤典洋氏は読み解く。これが本当ならば、なぜ村上春樹はそのようなことを描いた...
収録日:2025/04/10
追加日:2025/07/23
「信頼できない語り手」とは?村上春樹の謎に迫る文芸批評
AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(4)村上春樹の謎と信頼できない語り手
加藤典洋氏の代表作の1つに、村上春樹の作品を詳細に分析した『村上春樹イエローページ』がある。加藤氏は当時まだ評価が高くなかった村上作品を初期から高く評価していたが、それはなぜか。そこには文芸批評の用語である「信頼...
収録日:2025/04/10
追加日:2025/07/16
キケロは覚悟がいい…終幕でジタバタしない「死」への構え
キケロ『老年について』を読む(9)死について老年はどう対処すべきか
生きていく上で「捨て身でいる」「死を覚悟する」のは、人生のいろいろな時代を通じて人間の強さ、権威にもつながることだと本村氏は言う。そのためには若いうちから「死の練習」をすることが大事である。「生に執着しない」と...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/03/02
アウグストゥスがお手本、老人にとっていかに権威が大事か
キケロ『老年について』を読む(8)「権威」という褒美
古代ローマには「権威をもって支配せよ」という言葉がある。つまり権力も必要だが、最後に重んじられるのは権威であるということだ。アウグストゥスがローマ皇帝の地位を得た理由もそこにある。権威を保つには自制心が必要で、...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/02/24
老年における賭博とは?100円からでも楽しめる競馬の魅力
キケロ『老年について』を読む(7)農夫たちの快楽と賭博の嗜み
老年期の喜びとして、キケロは畑仕事を挙げている。当時の貴族は自分の農園を奴隷たちに耕作させていたので、かけた努力がそのまま返ってくることを知っていた。人生を十分に生きたあと農地に住み、百歳まで耕作を続けたローマ...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/02/17
新しい価値を提供して既得権を打ち破るのが企業の使命
日本企業の病巣を斬る(12)最大の既得権とは
現代社会で一番どうしようもない状態になっているのが既得権の問題である。この問題を解決できないと、日本も世界も、どの国の経済も、いい状態に戻ることはできない。そして今、最大の既得権となっているのは、社会保障である...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/02/16
三日坊主はダメ!学びこそ老年の「心の快楽」のために大事
キケロ『老年について』を読む(6)学びは老年に向いている
老年期のソポクレースは色事から逃れて喜んだが、老年になっても心の華やぎはあったほうがいいという意見もある。一方、肉体の快楽から離れた老年期は、新しいことに挑戦したり学んだりすることが大事であると語っている。同時...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/02/10
なぜ日本の従業員の会社への愛着は世界最低クラスなのか
日本企業の病巣を斬る(11)みんなが「おかしい」と感じている
「いい加減」「適当」「暗黙知」といったことこそが、日本人が持っている非常にいいところ、素晴らしいところであった。それを、コンプライアンスをはじめとしたアメリカンビジネス追従によって、壊してしまった。そのことが、...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/02/09
快楽ほど有害なものはない!元老院から追放された男の教訓
キケロ『老年について』を読む(5)老年には快楽がないのは本当か
老年には快楽がないので「嫌だ」「寂しい」というが、本当か。そもそも「快楽ほど有害なものはない」、だからないほうがいい、そうキケロは書いている。ストア派もエピクロス派も基本的には「自分を解放する哲学」であり、解放...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/02/03
誇るべき自分へ…「使命を自分が果たす」と自分で決定せよ
日本企業の病巣を斬る(10)会社の使命を自分の使命に
アメリカの企業と日本の企業はそもそも成り立ち、性質が違う。アメリカの企業は株主が「金儲けのために作った」のに対し、日本の企業は「どういう儲け方をしたか」を問う歴史伝統に立脚している。日本人はそこに戻る必要がある...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/02/02
盲目の老人アッピウスの気概…必要な老いへの備えと想像力
キケロ『老年について』を読む(4)老いは徐々にやってくる
アッピア街道などを作ったアッピウス・クラウディウスは、老いて盲目になっても元老院でしっかりと演説して、亡くなるまで周りの連中に対して気概ある態度を見せた。これは希有な例だが、大事なのは日頃からの努力で、自分が60...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/01/27
数字を追いかけるな、説明責任を求めるな…共感経営への道
日本企業の病巣を斬る(9)社会的共感経営の実現
野中郁次郎氏の唱える「知識創造企業」を築くには、「暗黙知」の活用と、地域やお客さんとの「共感」が重要である。まさに「共感経営」が重要だが、そのためには、数字を追いかけたり、説明責任を求めたりするのが間違いだとわ...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/01/26
ソクラテスが竪琴!? 老年から新しいことを始める柔軟性
キケロ『老年について』を読む(3)老年には体力がないのか
歳をとって体力が衰えるのは、当たり前のことである。「老年には体力がないのか」という問題設定に対してカトーの答えは、肉体的なことは若い頃に適わなくても、自覚的に精神を磨いていけば、歳をとってから優れた才能を発揮す...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/01/20
宇多、村上、醍醐…大転換期を象徴する天皇名の変化
平安時代の歴史~「貴族道」と現代(3)10世紀の外的環境と天皇名の変化
かつて日本が遭遇した最大の対外的な危機は平安時代、「王朝の時代」といわれる10世紀に訪れる。四方を海に囲まれた日本は諸外国と比べ、歴史的に外部からの危機は非常に少なかったが、その頃の大陸の政治変動に影響され、外部...
収録日:2023/10/20
追加日:2024/01/19
次善を求めよ…ありえぬ「最善」や「絶対正義」を求める愚
日本企業の病巣を斬る(8)「次善」を求める
この世には本来、「最善」などない。必ず欠点がある。それは企業も同じこと。よって「次善を求める」精神が確立してくると、オーバープランニングやオーバーアナリシス、オーバーコンプライアンスの問題も解決に向かう。しかし...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/01/19
ギリシアの将軍が驚いたローマの元老院、老人の見識の高さ
キケロ『老年について』を読む(2)老年が公の活動から引き離される理由
老年になっても、公の活動から引き離されるとは限らない。肉体は弱っても精神的に役に立つ老人向きの仕事はあるだろう。カトーも元老院に指図する立場で、元老院自体が見識を持った老人を中心につくられていた。紀元前3世紀半ば...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/01/13
創造的経営の核心…「個人の信念」を真実として正当化する
日本企業の病巣を斬る(7)信念と創造的経営
理想や使命へ向かうと「自分がこうやりたい」というものが出てくる。それぞれに正解を見つけていくしかないから、おのずと自分の持ち味が発揮されるようになる。ところが、現在の日本の企業社会では会議ばかりを重んじるあまり...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/01/12
老年が惨めと思われる4つの理由とは…キケロの論駁に学べ
キケロ『老年について』を読む(1)キケロの評価と「老年の心構え」
『老年について』の著者キケロは、カエサルやポンペイウスと同時代にあたり、古代ローマ史上随一の弁論家で、哲学者、また政治家でもあった人物である。多くの著作を残したが、政治的発言がしにくくなり、引退生活を送る中で著...
収録日:2023/06/12
追加日:2024/01/06
理念と使命感と塩梅…組織や数字の奴隷にならない生き方
日本企業の病巣を斬る(6)組織の奴隷にならないために
企業の「勝ち負け」は、相手を蹴落とすこととは違う。それは「いかに顧客の心をつかむか」の競争であり、「顧客の心をつかむ」のは「勝ち負け」とは関係ない。顧客の心をつかむことで得られるのは満足や愛である。理念の実現に...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/01/05
暗黙知と形式知…「使命感や恩」で心を燃やすのが日本の道
日本企業の病巣を斬る(5)暗黙知と形式知
欧米の企業と日本の企業の違いは、欧米が数値目標を求めるのに対し、日本はお客さんに喜んでもらうことに主眼を置く。これは野中郁次郎の言うところによれば、日本は「暗黙知」であり、一方、欧米の理論は「形式知」である。「...
収録日:2023/10/18
追加日:2023/12/29
オーバープランニングやオーバーアナリシスをどう変えたか
日本企業の病巣を斬る(4)全社改革の断行
多角経営で失敗するのは、「足るを知る心」や「わきまえ」がないからである。物質には限界があるが、心は無限に成長できる。その点をふまえずに、ライバルメーカーの真似ばかりして成長しようとしても、うまくいくはずがない。...
収録日:2023/10/18
追加日:2023/12/22
最善が堕落したものは最悪である…無限なのは理想や魂のみ
日本企業の病巣を斬る(3)足るを知る
日本の企業には伝統的な成功パターンがある。三井越後屋は地域密着型の商売を行い、300年繁栄を続けているが、これは当主が「足るを知る」をわきまえていたからだ。ローマ帝国の有名なことわざに「最善が堕落したものは最悪であ...
収録日:2023/10/18
追加日:2023/12/15
予算、人員…制約を乗り越えるところから自由は出てくる
日本企業の病巣を斬る(2)「商売の原点」に戻る
「なぜ売れないか」をデータから分析しても正解は出てこない――かつてキリンビール高知支店はこの問題に直面していた。必要なのは、人の心の流れを市場全体の流れとして捉えることで、「お客さんのため」に行動することだった。...
収録日:2023/10/18
追加日:2023/12/08
無理なプランや数値目標を指示されると現場の力は弱くなる
日本企業の病巣を斬る(1)日本企業の4大疾病
日本企業の病巣に「オーバープランニング(過剰なる計画)」「オーバーアナリシス(過剰なる分析)」「オーバーアダプテーション(過剰適応)」がある。これは経営学者の野中郁次郎氏が提唱したものだが、これに「オーバーコン...
収録日:2023/10/18
追加日:2023/12/01
大谷翔平選手が現代の「粋」を体現!?一生懸命よりも遊び心
江戸とローマ~哲人と俳人(4)現代の「粋」とグローバリゼーション
現代の「粋」について考えるとき、大谷翔平選手の名を挙げる本村凌二氏。彼の「二刀流」には野球をとことん楽しみたい、野球の楽しさを体現したい、そんな楽しみ方、遊び心があるのではないだろうか。そして、江戸とローマでな...
収録日:2021/09/16
追加日:2023/10/12
皇帝ネロへの反骨心…哲人ペトロニウスが見せた粋な生き方
江戸とローマ~哲人と俳人(3)ペトロニウスとセネカ
今回は皇帝ネロに仕えた二人の哲人を紹介する。『サテュリコン』を著したペトロニウスは宮廷の「優雅の審判官」と呼ばれて快楽と遊興を手解きし、セネカは政治の舵取りもする哲人として皇帝を導いた。いずれもやがて不興を買い...
収録日:2021/09/16
追加日:2023/10/05
松尾芭蕉と与謝蕪村――江戸の俳人が表現した粋な遊び心
江戸とローマ~哲人と俳人(2)蕪村と芭蕉の風流
自然を題材にすることの非常に多い日本の詩歌だが、そこに「風流」を表現した江戸の俳人の中から与謝蕪村と松尾芭蕉の句を取り上げる。季節の風物を詠んでもどこかおかしさだったり、王朝の歌や絵の影響を匂わせる蕪村。自由気...
収録日:2021/09/16
追加日:2023/09/28
風流とジョーク…粋な遊び、粋な生き様の精神とは?
江戸とローマ~哲人と俳人(1)日本の風流とローマ皇帝のジョーク
江戸っ子の「粋」な生き方はよく言われるが、ローマにもやはり同様の精神を尊ぶ風習があった。生活にゆとりができ、精神的な遊びが可能になった時代や都市の象徴として、江戸では俳人、ローマでは哲人の心豊かな生き方を探って...
収録日:2021/09/16
追加日:2023/09/21
ポンペイの公衆便所を見たらわかる古代ローマの衛生管理
江戸とローマ~下水道と肥溜め(3)公衆便所のシステムと清潔への意識
有名な古代ローマの公衆浴場(テルマエ・ロマエ)は当時1000近くあり、かなり混んでいたというが、公衆便所のシステムもかなり行き届いたようだ。その背景としていえるのが整った上下水道システムで、それが庶民生活を支える基...
収録日:2021/09/16
追加日:2023/09/06
公衆便所の名前になった皇帝ウェスパシアヌスのユーモア
江戸とローマ~下水道と肥溜め(2)江戸とローマの便所事情
日本の便所は「かわや」「せっちん」「はばかり」などと呼ばれ、「せっちん」を「雪隠」と書くようにあまり人の行きたがらないような場所に置かれたが、そうした家の構造が普及したのは江戸時代だった。江戸は循環社会とよくい...
収録日:2021/09/16
追加日:2023/08/30
江戸の下水道は世界一!? 欧米が驚いた「日本の肥溜め」
江戸とローマ~下水道と肥溜め(1)日本人の清潔感と肥溜め
驚くほどインフラが整っていた江戸とローマだが、下水道や糞尿処理も例外ではない。ヴェルサイユ宮殿に一つもトイレがなく、広い庭園で用を足したという話は有名だが、19世紀にオスマンがパリ大改造を行うまで、アパルトマンに...
収録日:2021/09/16
追加日:2023/08/23
江戸時代、参勤交代が果たした役割とその基礎としての五街道
江戸とローマ~アッピア街道と東海道(3)近代に通じる道
日本の街道はまっすぐな道が続くローマの街道とは異なり、防御を優先とした設計思想のもと発達してきたが、特に近代化に向かう時代、重要な役割を担った。「参勤交代」を研究した書籍には、「江戸における各藩の交流が、武士階...
収録日:2021/08/20
追加日:2023/07/19
アウグストゥスが強調した「権威」、象徴としての街道
江戸とローマ~アッピア街道と東海道(2)権威に通じる道
アウグストゥスが『業績録』の最後に強調したのは「権威」だった。大規模な道路建設に、多大な動員力を要するのはいうまでもないが、それは単なる権力だけでなく、「権威」を意味している。ローマの権威とは、それまでに培われ...
収録日:2021/08/20
追加日:2023/07/12
すべての道はローマに通ず――今も残るアッピア街道の軌跡
江戸とローマ~アッピア街道と東海道(1)ローマに通じる道
「すべての道はローマに通ず」――手段や方法は違っていても、中心となる真実、あるいは真理は一つだということわざだが、実際、ローマ帝国の道はローマを起点につくられた。つまり、すべての道は「ローマに始まる」のである。軍...
収録日:2021/08/20
追加日:2023/07/05
お妾さん文化、不倫騒動…時代で変わる価値観の多様性
江戸とローマ~娼婦と遊女(4)変化する価値観と遊女文化
明治以降、ヨーロッパのキリスト教文化の影響を受けてきた日本人は、そうした近代の価値観に基づいて吉原についても批判する。だが、歴史的な事象は、同時代の価値観、あるいはその地域の価値観に基づいて考えてみるべきもので...
収録日:2021/08/20
追加日:2023/05/08
「発酵はマジックだ」心も体も豊かにする発酵食品のアレンジレシピ
和食の深い秘密~なぜ身体に良いのか(5)納豆から蕪村、鮒寿司からアイスまで
ウェビナー終了後、視聴者から多くの質問が寄せられた。ここでは「発酵食嫌いの人にも、発酵食は摂らせるようにしたほうがいいのか」「鮒寿司の<飯>の部分には、どんな栄養が含まれているのか」の質問から、納豆汁をうたった...
収録日:2023/01/24
追加日:2023/05/06
キリスト教以前はおおらかだった…古代ローマの遊女文化
江戸とローマ~娼婦と遊女(3)娼婦のインテリジェンスとキリスト教の影響
ローマ遺跡に娼家の痕跡はないが、後代のルネッサンス期イタリアではインテリジェンスが高く知的な高級売春婦が、貴族を顧客としていたことが分かっている。ローマ時代にはおおらかだった活動が、キリスト教支配を経て変化して...
収録日:2021/08/20
追加日:2023/05/01
花魁は日本独特――洗練された吉原の遊女文化
江戸とローマ~娼婦と遊女(2)遊女の「道」と吉原の文化
江戸の遊郭・吉原において、花魁はトップスターである。遊女たちの住む吉原は厳然たる秩序がある一方、女性や子どもが訪れるエンタメ・スポットでもあったという。ここで育まれた遊女文化は日本独特ともいえる遊女の「道」を究...
収録日:2021/08/20
追加日:2023/04/24
人間は元来ホモ・ルーデンス…遊びから見た江戸とローマ
江戸とローマ~娼婦と遊女(1)遊びと労働
「税金と売春は、有史以前から存在する」といわれることがあるが、人口集中と文明・文化の爛熟の共通項を持つ大都市の江戸とローマにおいて、風俗ビジネスは必然的に盛んになる。近代以降の「労働は美徳」の概念が社会を支配す...
収録日:2021/08/20
追加日:2023/04/17
逆遠近法のこころは「義ならざるものは結局、美ではない」
逆遠近法の美術論(3)高村光太郎の「義」と「真のリアリズム」
高村光太郎の「義ならざるものは結局美でない」を座右銘としている戸嶋靖昌記念館。この言葉は、芸術とは愛ではなく「義」のものであることを意味し、考え方として武士道に近く、イコン文明にも近い。「真のリアリズム」と聞い...
収録日:2022/08/30
追加日:2023/03/24
私心を捨てる――幕臣・山岡鉄舟が体現した武士道
江戸とローマ~「父祖の遺風」と武士道(6)武士道の喪失と現代社会の問題
新渡戸稲造の『武士道』には、古代ローマの「父祖の遺風」に訴えるエピソードが多数盛り込まれていた。「義」を貫き、相手への思いやりを「惻隠の情」として表し、私心を捨て捨て身になることの大切さである。幕末には武士道を...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/12/17
源平の合戦、熊谷次郎直実の伝承にみたローマ建国の精神
江戸とローマ~「父祖の遺風」と武士道(5)勇者の務め
一ノ谷における平敦盛と源氏の熊谷次郎直実の一騎打ちは、『平家物語』「敦盛最期」の段、能や幸若舞の『敦盛』として日本人には馴染み深いものである。新渡戸稲造は『武士道』において、この伝承をローマ建国の精神に響く「敗...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/12/10
新渡戸稲造が『武士道』で説く上杉謙信とカミルスの「義」
江戸とローマ~「父祖の遺風」と武士道(4)上杉謙信とカミルス
今も年末が近づくたびにドラマで再演される『忠臣蔵』は、武士道が大切にした「義」の世界を描き出したものだ。新渡戸稲造の『武士道』には、大量に古代ローマのエピソードが掲載されている。戦国武将の振る舞いと共通するロー...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/12/03
家の名誉を汚さない――武士道と「父祖の遺風」の共通点
江戸とローマ~「父祖の遺風」と武士道(3)家の名誉と教育のために
「父祖の遺風」はローマ貴族の伝統精神として受け継がれたものだが、日本の武士道は明治維新以降、軍隊の中で庶民にも拡大していく。家に対する誇りは両者に共通しているが、ローマでは特に著しい。彼らはそのプレッシャーをど...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/11/26
大カトーが主張した父親の責任。古代ローマ人は教育熱心
江戸とローマ~「父祖の遺風」と武士道(2)ローマ人が大事にした子どもの教育
騎士道精神はキリスト教道徳に付随するものだったが、武士道や父祖の遺風はそうではない。それらは多神教社会、すなわち多様な価値観を認めるローマと江戸の社会において育った価値観である。今回は、ローマの貴族一家において...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/11/19
なぜ新渡戸稲造は『武士道』を英語で著したのか
江戸とローマ~「父祖の遺風」と武士道(1)誠実さと新渡戸稲造『武士道』
ローマと日本の共通項として、オリジナリティのなさが指摘されることがある。かつて西欧のモノマネと蔑まれていた日本がモノづくり大国に成長するには、人間としての誠実さが不可欠だった。実はローマにも共通する誠実さの源、...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/11/12
和田合戦…侍所別当・和田義盛の挙兵理由と三浦義村の策略
源氏将軍断絶と承久の乱(5)和田合戦
和田合戦は、鎌倉幕府初期における最大の武力抗争であった。有力御家人である和田氏と北条氏の間にくすぶっていた対立は、「泉親衡の乱」をきっかけに発火する。北条に恥辱を与えられたとする侍別当の和田義盛は挙兵するが、一...
収録日:2022/07/13
追加日:2022/10/09
自分の幸せと業績向上の好循環を生むフローチャート
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(8)成功のプロセス
キリンの実例をもとに作成したのが「自分の幸せと業績向上の好循環を生むフローチャート」である。高知支店でまったく売れない状況に置かれたなかで、会社の存在意義について「自己との対話」を重ねた結果、「会社の使命を果た...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/10/03
「なぜ売れないのか」は追及せず、今と将来だけを考える
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(7)幸せの正体とは
キリンビールの東海地区の営業責任者だった時代には、毎週月曜日に全員にメールを出し、今週やる仕事の意味と「使命が果たされた現場」の様子を伝えた。これによりどう動けばいいかがわかり、情報を共有することで刺激を得られ...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/09/26
「理念」は言葉ではない、「挑戦」をしつづけることである
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(6)幸せと業績の一体化とは
使命を果たすために大事なのは、行動である。行動しているうちに何かが潜在意識にたまり、やがて顕在化して、よい結果をもたらす。行動に至るパターンはさまざまだが、最大の動機は「幸せになりたい」だった。名古屋では使命を...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/09/19
「相手のロジック」を考えて改革する…使命であれば諦めない
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(5)相手の内在的な論理を把握する
「仕事の定義を変える」「お客様に喜んでもらうことを使命にする」といっても、みんなに納得してもらえるわけではない。では、どのように仕事を進めていくべきなのか。大事なことは、「相手のロジック」に乗っかることである。...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/09/12
ワインの神に対するディオニュソス信仰と文明国の境界線
江戸とローマ~日本酒とワイン(4)ディオニュソス信仰と文明
人間は理性だけで生きているわけではない。古代ローマでは、ワインの神に対するディオニュソス信仰があり、飲酒がもたらす解放感は、人に自由を担保してくれる。ヨーロッパでは、ワインのできる国が「文明国」、そうでなければ...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/09/11
使命を果たすためには「自由」が必須…だから幸福になれる
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(4)自由でなければ始まらない
実は、「使命を果たすこと」を目標にすると、「自由にせざるをえなくなる」。なぜなら、たとえば「お客様に喜んでもらう」ことを使命と考えた場合、お客様は百人百様なので、全部正解が違うからだ。だからこそ、「使命を果たす...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/09/05
なぜガリア産のワインはおいしいのか、ローマ帝国の酒事情
江戸とローマ~日本酒とワイン(3)樽とサロンと酒合戦
古代ローマではワインを「アンフォラ」という壺のような容器で飲んでいたが、やがてガリア地方での貯蔵に「樽」が用いられるようになると、風味が著しく向上する。また、お酒を飲みながら自由な雰囲気で語り合える場としてサロ...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/09/04
1年分の営業予算が3カ月で枯渇…そこからどう逆転したか
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(3)「打つ手が全部当たる」境地とは
お客様に聞きに行く…とひと言でいうが、実際には難しい。最初は、「何を尋ねればいいのか」からわからなかった。また、得意先の要望を聞いているうちに、1年分の予算を3カ月で使い果たしてしまった。これは大失敗で、本社からも...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/08/29
ポンペイのファストフード店、遺跡が物語るローマの酒文化
江戸とローマ~日本酒とワイン(2)ローマの酒文化とファストフード
現在では醸造酒を薄めて飲む習慣はないが、江戸やローマでは今より濃厚な原酒が水割りで飲まれていた。ポンペイからは、ワインとファストフードを商う「テルモポリウム」が出土している。夜間照明のない時代、午後になると貴族...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/08/28
「お客様のため」に心が向かうとイノベーションも起きる
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(2)どうすれば好循環が生まれるか
「自分は自分、人は人」というエゴイズムから、どうすれば脱却できて、好循環に持っていけるのか。田村潤氏は、「自分の利益を超える『1つ上の概念』に向かうことが大切だ」と説く。それこそ、企業の「使命」なのである。なにし...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/08/22
樽廻船とアンフォラの山、酒文化を謳歌した江戸とローマ
江戸とローマ~日本酒とワイン(1)醸造技術の進歩と輸送手段の変遷
都市人口が増加した平和な時代、飲酒の需要は当然大きいが、その要因の一つにノウハウの洗練がある。日本では醸造技術が進み、濁り酒が清酒に変わり、日常的な嗜好品として愛飲されるようになる。一方、ローマではワインのよし...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/08/21
「使命観=パーパス」に立脚できないのは自分のエゴのせい
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術(1)悩みの99%は他者との関係性
いのちの電話にかかってきた内容を2万件調査したところ、その99%以上が「自分と他者との関係性」での悩みだったという。一方、あるコーヒーチェーンの話では、仕事に喜びを感じるのは、「お客さんから喜ばれる」「ほかのメンバ...
収録日:2022/03/30
追加日:2022/08/15
ペリーが驚いた江戸時代の庶民の驚異的な好奇心と識字率
江戸とローマ~図書館と貸本屋(5)江戸のリテラシーと庶民の読み書き能力
江戸のリテラシーは、貸本屋の数とともに寺子屋でも測れる。江戸末期、俗説によると寺子屋への江戸市中の就学率は70~80パーセント。同時代のイギリスやフランスと比較すると驚異的な数字である。実際、来航したペリーは日本の...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/07/24
ローマ大火の謎…タキトゥスの写本に残された修正の痕跡
江戸とローマ~図書館と貸本屋(4)江戸の貸本屋・ローマの図書館
江戸期には貸本屋が庶民の読書の中枢を担ったが、和紙より取扱いが困難な羊皮紙製の写本で残したのはローマの図書館だった。その後、時代は下るがヨーロッパの写本には修正やいたずら書きが散見され、しかも史料として現存する...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/07/17
カラカラ浴場、トラヤヌス浴場…そこにローマの図書館が!
江戸とローマ~図書館と貸本屋(3)写本と朗読
古代ローマの高い識字率は、残念ながら中世ヨーロッパには受け継がれなかった。それだけ古代ローマは余裕のある時代だったということだ。活版印刷がない時代ゆえ、写本で文字を読むわけだが、少部数しか流通しない写本は朗読や...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/07/10
落書きの誤字脱字でわかる古代ローマ人のリテラシー
江戸とローマ~図書館と貸本屋(2)識字率と落書き
古代ローマでは、貴族階級は家庭教師や父親から、一般の庶民は街に集まってそれぞれ文字を学んだ。公務員や兵士になるためにはそれが必要だからだ。特にアルファベットは20数文字と覚えやすく、非常に使い勝手のよいツールであ...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/07/03
識字率の高さを誇った古代ローマ、その独特な教育方法とは
江戸とローマ~図書館と貸本屋(1)リテラシーの重要性
現代人は読み書き能力を当然のものと考えているが、せいぜい100年前には日本にも読み書きのできない人がたくさんいた。リテラシーは教育が普及した現代の賜物なのである。しかし、前近代の世界の中で、江戸とローマは飛び抜けて...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/06/26
名将たちほど敵を怖れ、窓際族は自信に満ちている
自信について(12)自信を持ったら「ただのバカ」
日本人は「自信を持たないこと」が素晴らしい活動のできる根源だった。それは、皇室や家制度があって、尊いものが常に自分の上にあったからこそのものだった。また、理想を掲げていれば負けても「誇り」を持てるが、「自信」は...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/06/10
伝統は「これを日に新たに救い出さなければ」ならぬもの
自信について(11)絶えず挑戦するのが「保守」
たとえば売上げ目標を「前年比102」などにすると、実際には「100」にも到達しない。リスクを侵さず、去年と同じやり方でやろうとするから、時代の変化についていけない。伸びる組織は自分たちで工夫して、イノベーションを起こし...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/06/03
松下電器の製品には「人間の心」が入っていた
自信について(10)人助けが商売の儲けにつながる
現在、ビジネスで大きな儲けを出した創業者たちが、何十億円もかけて宇宙旅行に行っている。これは明治の成功者とは大違いだ。なにしろ明治の成功者たちは、美術事業など日本の役に立つお金の使い方をしていた。財産を使うのも...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/05/27
「質」も「量」も追求して成功した岩波書店・岩波茂雄
自信について(9)「質」と「量」のバランス
「量の文明」が席捲するなかではあっても、「質の追求」は誰でも日常生活でできる。ただし、限界はある。質は、量が増えるとダメになるという相関関係があるからである。だが、大正から昭和初期にかけて、見事に「質」と「量」...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/05/20
自分のためだけの自己実現の「強烈な虚しさ」は何か?
自信について(8)自分の「道」はどうすれば見つかるか
自分の「道」はどうすれば見つかるのだろうか。自分本位の「自己実現」を果たしたところで、「強烈な虚しさ」を感じるだけになりかねない。「量の追求」を求める現代社会では、「道」を見つけるのは難しい。だが、キリンビール...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/05/13
どうして「ズルをする人生」を選んでしまうのか
自信について(7)仕事に「苦悩」はあるか、ないか
現代人は文学を読まなくなり、教養も失った。ゲーテの『若きウェルテルの悩み』を薦めてみても、何が書いてあるかわからない(恋愛文学であることもわからない)人ばかりになってしまった。人間は理想を追求しつづけられる人と...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/05/06
すべての評価が「量」になれば人間はみんな自信を失う
自信について(6)精神論は人間にとって一番大切なもの
一昔前の英米人は、「仕事」と「信仰の生活」とは別ものだった。だからこそ、ビジネスは「金儲け」だと割り切っていた。アメリカの寄附文化も、単に仕事を引退した人が、キリスト教の世界に戻って、慈善を行っているだけである...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/04/29
西田幾多郎と魂の苦悩を共有する時間を持ったことへの共感
自信について(5)西田幾多郎の本の魅力は「永遠の苦悩」
「自分が進む道は、これだ」「うまく行くかはわからないけど、やってみる」……その境地に達するために大切なのは「初心」や「原点」の歴史を知ることである。しかし、それによって「憧れ」は抱けるようになっても、「自信」を抱...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/04/22
「会社の善なるもの」と「個人の善なるもの」が共鳴する
自信について(4)大和魂のあり方を問う『源氏物語』
企業理念の実現に向けて行動すれば、会社はよいほうに向かいだす。行動するために必要なのは「勇気」だが、じつは勇気を持つのが一番難しい。勇気を理解するには、民主主義や平等思想などを1回捨てて、「魂」の問題を考える必要...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/04/15
企業における「自己信頼」の根源は「企業理念」である
自信について(3)理念や理想への共感が自己信頼の源
「自己信頼が高く」「自分を失わない」人はどのような人だろうか。挙げられるのは「心の中に理想として共鳴できる人」を持っているかどうかである。松下幸之助や出光佐三も、自分が理想として共感できる人を心の中に持っていた...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/04/08
諧謔精神を育んだ江戸とローマ、現代社会とどこが違うのか
江戸とローマ~諷刺詩と川柳・狂歌(4)庶民文化を楽しむ社会の形成
川柳と風刺詩を通して庶民文化を楽しんだ「人口100万人都市」江戸とローマ。どちらも当時、大都市でありながらお互いが無関心ではいられない社会を形成していたという。そこには豊かさゆえのゆとりがあったという面もあるが、彼...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/04/04
「すべてをありのまま受け入れる」から可能性を追求できる
自信について(2)「自信がない」から何でもできる
田村潤氏は自分の仕事ぶりを記録して、自分を「失敗する人間」と定義したという。だから失敗を潰すように努力することができたのだ。昔の実業家や成功者もみな「何もできない自分」と考えていた。「自分はダメ」と考えるから、...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/04/01
冷笑から嘲笑、義憤へ、ローマ諷刺詩人の健全な批判精神
江戸とローマ~諷刺詩と川柳・狂歌(3)川柳・狂歌と諷刺詩の時代
日本の川柳や狂歌の源流は、京鴨川の「二条河原の落書」にあるといわれる。悪政に対する批判的風刺の精神が庶民レベルにまで拡大したのが、川柳や狂歌の流行した江戸末期だった。同様のことが、ローマでは風刺詩を通じて紀元前5...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/03/28
豊臣秀吉でさえ自信を持ったら「バカなじいさん」になった
自信について(1)現代は「自信教」にまみれている
執行草舟と田村潤氏が、「自信」についてどう考えるべきかを論じあう対論。最近の日本は、とくに若い人で自分の仕事に自信がない人が多い。もちろん、そうなってしまった大きな要因としては、日本の大家族主義的な気風が失われ...
収録日:2022/01/25
追加日:2022/03/25
江戸時代の粋が生んだ「川柳」を詠んで俳諧の歴史を楽しむ
江戸とローマ~諷刺詩と川柳・狂歌(2)江戸っ子と川柳
川柳や落語では「江戸っ子の粋」が強調されるが、ローマにはそれに匹敵する「ローマっ子」がいたのだろうか。どちらの都市も外部から多様な人が流入したが、「それ以外の人間」により純粋な都会人の定義が行われたのは江戸だけ...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/03/21
諷刺精神に富んだパックス・ロマーナ、悲劇より喜劇が人気
江戸とローマ~諷刺詩と川柳・狂歌(1)諧謔精神の爛熟
古代ローマと江戸を比較するうえで、社会のゆとりは欠かせない。200年以上続いた江戸の平和は、ほぼ同じぐらい続いた「パックス・ロマーナ」に匹敵し、庶民にも生活文化を楽しむ心が磨かれていった。両者に共通するのは、物事に...
収録日:2021/06/16
追加日:2022/03/14