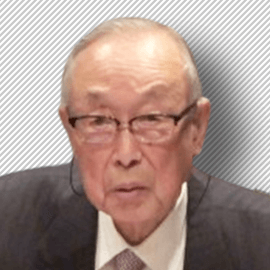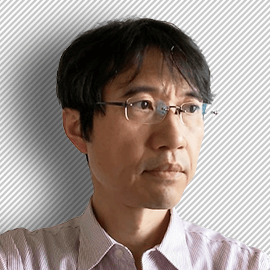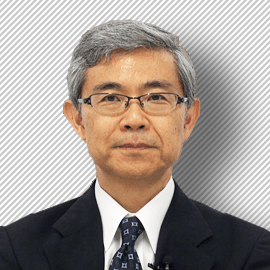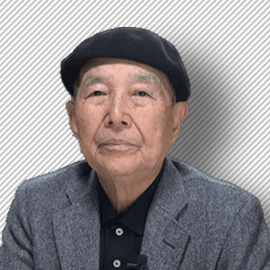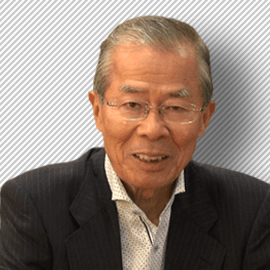緊縮&積極の是非は!?~財政出動が及ぼす景気への影響
お金の回し方…日本の死蔵マネー活用法(3)お金がつくる景気の波…民間VS政府
お金の量が短期間に大量に変化すると、景気に大きく影響を与えるケースがある。米国のリーマンショックやコロナショック、さらに日本のバブル崩壊やアベノミクスなどを検討しつつ、お金の生まれ方と量の変化、そして景気の関係...
収録日:2024/12/04
追加日:2025/03/08
「日本病」をもたらす低賃金、低物価、低成長、高債務
衰退途上国ニッポン~その急所と勝機(2)景気低迷を招く「日本病」の正体
日本は30年ほどずっと「日本病」といわれる症状に陥っているといわれている。その要因として、3つの「低」と1つの「高」があると宮本氏は言う。それらはいったい何か。また、なぜいまだに「日本病」から回復しないのか。一般的...
収録日:2023/06/30
追加日:2023/11/07
逆イールド現象は景気後退の前触れ?歴史的円安の行方は?
2023年前半の金融市場と日本の行方(2)米国の逆イールド現象と為替の動向
アメリカの逆イールド現象は、いかなる状況を招くのだろうか。過去の事例を参照しながら、今後の動向を読んでいく。また、1971年と同レベルの円安状況となった日本。今後もこの状況は変わらないのだろうか。ニクソンショック以...
収録日:2023/06/05
追加日:2023/07/16
IMFはなぜインフレが「一時的」なものだと見誤ったのか
世界経済の見方とIMFの役割(3)世界的な景気減速がもたらすもの
パンデミックによる経済危機から立ち直り始めた世界経済は、「一時的」なインフレを伴いながらも着実に回復するものと予想されていた。ところが、ウクライナ戦争が勃発して世界のエネルギー価格が急騰すると、さらなるインフレ...
収録日:2023/01/11
追加日:2023/02/16
世界経済は「大封鎖」――大恐慌以来の景気後退もとIMF警告
コロナパンデミックと闘う世界と今後の課題(6)ワクチン開発の長期化とIMFの経済予測
コロナウイルスには頻繁に変異が起こりやすいという特徴があるため、このウイルスに対処するためのワクチンを開発・製造するのは非常に難しい。こうした対応の難しさもあり、予期せぬ感染拡大を招き、IMFも景気後退に関して当初...
収録日:2020/07/16
追加日:2020/08/30
景気の谷がオリンピック後にあるとすれば、どうすべきか
オリンピック後の経済を考える(1)需要落ち込みへの懸念
2019年現在、アベノミクスの成果もあり需要サイドはそこそこ安定しているといえるが、潜在成長率の低迷による供給の伸び悩みが日本経済の大きな課題だ。この状況下で多くの人が懸念しているのは米中貿易摩擦の影響、そして2020...
収録日:2019/10/31
追加日:2019/11/27
日本の景気は中長期的に見るとかなり危険な状況
2018年激動の世界と日本(1)激変する世界を展望する
2018年はアメリカ、ヨーロッパ、そして東アジアで、大激動の年になるだろうと、公立大学法人首都大学東京理事長・島田晴雄氏は予測する。ドナルド・トランプ大統領の政策、ブレグジットを含めたヨーロッパの状況、中国の台頭と...
収録日:2018/01/16
追加日:2018/04/21
バブル景気、格差社会、政界再編‥100年前との共通点
第一次世界大戦から100年にあたって(4)大戦期と現代日本を比較して学ぶべきこと
第一次世界大戦は100年前のことでありながら、その戦中、戦後の様子には現代の日本と多くの共通点を見出すことができる。今、私たちは大戦と現代の比較に何を見出し、何を学ぶべきなのか。山内昌之氏による過去に学び現代を...
収録日:2014/11/05
追加日:2014/12/31
景気次第で自民党内に政変の可能性も
今後の政治がどうなるか~安倍政権のゆくえ~
2015年4月の統一地方選挙を皮切りに、安倍政権の前に「4つのハードル」が次々とあらわれる。難局は、向こう2年にわたって続く。自民党内の政変にもつながりかねない、「4つのハードル」とは?
収録日:2014/12/18
追加日:2014/12/24
貨幣数量説と大恐慌…大恐慌の本当の原因はFRBのミスだった
本当によくわかる経済学史(8)1929年世界大恐慌の真実
よく知られているように、1929年から大恐慌が始まってしまう。はたして、大恐慌はどうして起こったのだろうか。その原因を知るためには、まず、貨幣数量説を知っておいたほうが良い。そして貨幣数量説を理解するためには、「長...
収録日:2022/06/08
追加日:2023/01/25
「ヒトラーの経済政策はケインズ的で大成功だった」は大嘘
本当によくわかる経済学史(12)ヒトラーの経済政策への誤解
「ヒトラーはケインズ的な政策でドイツ経済を復活させた」などと、ナチスの経済政策を評価する言説も日本では多い。だが、これはとんでもない間違いだという。では、当時のドイツの実状とは、いかなるものだったのか。そこには...
収録日:2022/06/08
追加日:2023/02/22
高齢化で財政政策の有効性が低下…財政乗数に与える影響
日本の財政政策の効果を評価する(1)「高齢化」による効果の低下
バブル崩壊以降、いまだに低迷し続ける日本経済。その間、政府はさまざまな財政政策を打ち、浮上の糸口を探ってきた。では、これまでの財政政策は失敗だったといえるのだろうか。財政政策を評価する議論はそれほど単純ではない...
収録日:2023/12/14
追加日:2024/03/07
オリンピック後に日本経済は崩壊する可能性がある
2019年激変する世界と日本の針路(14)世界恐慌のリスク要因
世界経済は成熟して、今後景気は下降していくという。日本経済も東京オリンピック以降、下降していくことは間違いないだろう。今、世界には世界恐慌のトリガーが5つある。現在ではリーマンショックの時と異なり国際協調の動きが...
収録日:2019/01/28
追加日:2019/05/21
ケインズ革命への誤解…真に独創的なのは、どの部分か?
本当によくわかる経済学史(10)「ケインズ政策」の誤解と真実
不況の際は政府の財政出動によって景気回復を図る。これがケインズの政策であり、1929年の大恐慌を救ったのはケインズ革命によるものだと一般にはいわれるが、実はこれは必ずしも正しい理解ではないと柿埜真吾氏は言う。ケイン...
収録日:2022/06/08
追加日:2023/02/08
寄付行為に表れる社会貢献や人生観は日米でかなり違う
「公益資本主義」の確立に向けて(2)社会貢献や人生観、経済システムから日米の違いを読み解く
実体経済から金融経済へと移行した米国経済のなかで、いま何が起きているのか。社会貢献、人生観、経済システムから日米の違いを読み解く。
収録日:2013/11/07
追加日:2014/02/24
株価急上昇を正当化できるほど中国経済は良い状態にはない
半年で2倍に急上昇した中国株~バブル到来か~
ここ半年で2倍にまで急上昇した中国株に世界の注目が集まっている。しかし、これはバブル現象なのではないかという懸念が大きいのも事実だ。中国経済における経済成長率と経済的非効率増大という図式や、危機感の増す不良債権...
収録日:2015/06/16
追加日:2015/06/25
ノーベル賞受賞者も指摘!男女の賃金格差を埋めるために
日本の財政政策とその効果を検証する(5)ジェンダー平等と反循環的な財政政策
世界の中でもジェンダーギャップが大きい日本だが、それを改善する糸口はどこにあるのだろうか。経済を刺激する財政政策はジェンダー平等の実現にもつながるのだが、より抜本的には、働き方の柔軟性が必要だ。日本がそれを実現...
収録日:2023/12/14
追加日:2024/04/04
新古典派経済学への誤解と実際…特徴と古典派との違いは?
本当によくわかる経済学史(7)新古典派経済学とは何か
限界革命以降に登場した「新古典派経済学」。これについては、ケインズ経済学やマルクス経済学と対立するものだという誤解が現代でも非常に多い。それはなぜか。また、その具体的な中身は何なのか。新古典派の具体的なグループ...
収録日:2022/06/08
追加日:2022/12/28
大恐慌とケインズ…様々な恐慌克服の処方箋の真実を探る
本当によくわかる経済学史(9)ケインズ、計画経済、オーストリア学派
1929年の世界大恐慌ではFRBの金融政策の失敗が明らかにされなかったため、「古典派経済学には限界があるのではないか」と皆が考えるようになってしまった。そこで代わって台頭したのが、ケインズ経済学やマルクス主義、オースト...
収録日:2022/06/08
追加日:2023/02/01
「貨幣量と物価」の現代経済史…そしてスタグフレーション
本当によくわかる経済学史(14)ケインズ政策の限界と転換
フリードマンの研究によって次第に金融政策の重要性への認識は高まってきたものの、いまだケインズ政策への支持は強かった。だが、ケインズ政策がうまくいかない局面が多くなっていく。ここでは、サッチャー政権時のイギリスや...
収録日:2022/06/08
追加日:2023/03/08
古典派経済学が繁栄をもたらした…柱は自由貿易と貨幣数量説
本当によくわかる経済学史(4)古典派経済学の特徴と時代的背景
古典派経済学の7つの特徴として、自由貿易をはじめ、貨幣数量説、労働価値説、人口論などを挙げることができる。中でも現代でも通用する2つの柱は「自由貿易」と「貨幣数量説」だというが、それはなぜか。また、その他の特徴に...
収録日:2022/06/08
追加日:2022/12/07
小林秀雄をより深く理解するための「近代日本小史」
小林秀雄と吉本隆明―「断絶」を乗り越える(2)なぜ「批評」は昭和初期に登場するのか
日本は明治維新によって西洋近代化へと大きく舵を切るが、それは大きな矛盾を抱えた大改革だった。そして「和魂洋才」という言葉が象徴するように、日本の国体主義と西洋の資本主義を両輪に推し進めた結果、経済は発展していっ...
収録日:2023/04/07
追加日:2023/08/22
セキュラースタグネーションの背景にある先進国の成熟化
アベノミクス~第3の矢は如何に投資を引き出すかがポイント
政府の経済財政諮問会議の議員も務める経済学者 伊藤元重がアベノミクスとその効果、今後の重要ポイントを解説する。
収録日:2014/01/28
追加日:2014/02/24
アベノミクスの課題、重要なポイント
アベノミクスの中間総括
2012年12月の安倍政権発足以来、20カ月を経過し、内閣改造も経た今、これまでのアベノミクスを総括する動きが各所で出始めている。アベノミクスの特徴やこれまでの成果、そして今後の課題について、伊藤元重氏が大いに...
収録日:2014/09/08
追加日:2014/09/14
インフラの波及効果を科学的に分析する必要性
新しいインフラの役割とその波及効果
インフラは需要面だけでなく、供給面にも貢献し得るものである。よって、総需要および総供給への刺激という観点でインフラの効果を見なければならない。今回の講義では、インフラの在り方とその新しい役割、またその波及効果に...
収録日:2019/02/20
追加日:2019/05/12
長期金利が低いまま続く場合、どのような政策運営が必要か
長期金利の低水準下で取るべき日本の政策
長期金利はほとんどゼロに近い。だからといって、借金を増やしても大丈夫というのは非常に乱暴な議論だと伊藤元重氏は言う。債務は減らしていく必要があるが、歳出を抑え込むことは経済にマイナスの効果を産むこともある。では...
収録日:2019/04/16
追加日:2019/06/02
トランプ大統領が再選されると世界にどんな影響が及ぶのか
2020世界の政治経済と日本(5)次期米国大統領選と米中対立
仮にトランプ政権が2期目に突入した場合、財政的な行き詰まりを迎えて、国際政治・経済に大きな混乱を招くと島田晴雄氏は指摘する。しかし、対抗する民主党側も現状を打開できる公算は限りなく小さい。そのようななかで非常に大...
収録日:2020/01/23
追加日:2020/04/27
コロナ禍で予測される世界経済の「三つの代替シナリオ」
コロナ禍で揺れる世界経済の行方(8)IMFの経済予測
IMFは、「世界経済見通し」として通常は4月と10月に中期的な予測を発表し、1月と7月にアップデートしている。今回、アップデートは6月に前倒しになっているが、ここでは4月の見通しに基づいて、その意図を考えている。なお、金...
収録日:2020/06/15
追加日:2020/07/14
「ケインジアン」の分岐とMMT?…正統と異端の見分け方
本当によくわかる経済学史(15)3つのケインジアンとMMTの違い
ケインジアンにはさまざまな分派がある。よく耳にするのが「オールドケインジアン」「ニューケインジアン」「ポストケインジアン」だが、それぞれ何を指すのか。その主張や代表的な経済学者について解説する。そこで気になるの...
収録日:2022/06/08
追加日:2023/03/15
派閥解体をめざす党風刷新運動の挫折…不遇から大蔵大臣へ
福田赳夫と日本の戦後政治(5)党風刷新運動の失敗と佐藤栄作政権
池田勇人政権の方針との食い違いが顕著になり、政調会長を辞職した福田赳夫。その後、自民党の派閥政治を改めるために「党風刷新運動」を展開したが、それも失敗に終わる。キャリアにおいて「冬の時代」を迎えた福田だったが、...
収録日:2022/09/29
追加日:2023/06/09
インフレ激化の真実…デフレ脱却を困難にした日本の労働市場
経済と社会の本質を見抜く(1)世界的インフレと労働市場の影響
現在の経済、そして社会の本質を、どのように見抜いていけばいいのだろうか。最初に考えるのは、インフレについてである。可能性は低いが、インフレが激化する「ハイパー・インフレーション」が起こると、いったい社会はどうな...
収録日:2023/08/09
追加日:2023/10/29
1900年代日本経済の不安定化を招いたインフレと不人気政策
歴史的転換点における影の主役「インフレ」(2)幕末のインフレと1900年代前半
インフレ傾向が強まる現在の日本経済だが、幕末にもインフレは起こっていた。黒船来航に震災、疫病など複合的な要因で発生したインフレの影響により明治維新へと突き進んでいくことになるのだが、実は現在の日本とよく似た状況...
収録日:2023/12/26
追加日:2024/02/22
長寿雇用戦略で構造改革、高齢化はピンチではなくチャンス
日本の財政政策の効果を評価する(3)高齢化をチャンスに変える方法
「財政政策の有効性を低下させる」という高齢化だが、まさに高齢化が進んだ日本社会において、どのようにすれば経済を立て直すことができるのか。一見ピンチに見える高齢化だが、実はチャンスなのだと宮本氏はいう。鍵は「メリ...
収録日:2023/12/14
追加日:2024/03/21
国の借金は誰が払う?人口減少による社会保障負担増の問題
教養としての「人口減少問題と社会保障」(4)増え続ける社会保障負担
人口減少が社会にどのような影響を与えるのか。それは政府支出、特に社会保障給付費の増加という形で現れる。ではどれくらい増えているのか。日本の一般会計の収支の推移、社会保障費の推移、一生のうちに人間一人がどれほど行...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/11/19
叩き潰せ、正しいのは自分だけ…ロイ・コーンの教えとは
[深掘り]世界を壊すトランプ関税(1)トランプ大統領の動機と思考
トランプ政権が発表した関税政策は、世界を大きな混乱に落とし込んでいる。はたして、トランプ大統領の「動機」や「思考」の淵源とはいかなるものなのか。そして世界はどうなってしまうのか。
島田晴雄先生には、テンミニ...
収録日:2025/04/15
追加日:2025/04/25
単なる不況に非ず…破壊規模は「台風か気候変動か?」
[深掘り]世界を壊すトランプ関税(2)米国の自爆と中国の思惑
トランプ政権が発表した関税政策は、世界を大きな混乱に落とし込んでいる。はたして、トランプ大統領の「動機」や「思考」の淵源とはいかなるものなのか。そして世界はどうなってしまうのか。
島田晴雄先生には、テンミニ...
収録日:2025/04/15
追加日:2025/04/26
株式リターンの歴史検証…大きな構造変化の影響を見抜く
株価と歴史…トランプ関税の影響を読む(2)株価リターンの歴史から考える
トランプ関税の影響を、歴史を踏まえつつ分析していく講義。第2話ではいよいよ、アメリカ、ドイツ、香港、日本などの株価の歴史を追いながら検証していく。実は株価の歴史的な動きを把握するためには、「株価」の動きでみるので...
収録日:2025/04/18
追加日:2025/05/02
2013年3月に交渉開始なら、進めているのはハメネイ?
米国とイランの秘密交渉が与える影響力
米国とイランの秘密交渉の結果次第で、中東情勢は大きく変わる。この動きに反発を示すのはどの国か?石油価格に与える影響は?本交渉が日本に与える影響も考えていく。
収録日:2014/01/16
追加日:2014/02/24
デフレ脱却を目指している今こそ法人税率引き下げを
法人税改革はアベノミクス第三の矢の試金石
今、世界の中でも格段に高い日本の法人税率の引き下げが議論されている。財政健全化も同時に推進しなければならない日本の法人税改革はいつ、どのように行うべきなのか? 諸外国の実例とともに税率引き下げの背景から分かりや...
収録日:2014/04/25
追加日:2014/05/02
先送りされてきた最たるものが「社会保障と税の一体改革」
社会保障と税の一体改革(1)時代の変化と法案作成理由
野田佳彦前総理が推し進めた「社会保障と税の一体改革」は、アベノミクスのベースとなり、4月の消費税アップへとつながっていった。なぜ野田政権は当時、消費税増税というリスクある政策を掲げたのか。「社会保障と税の一体改...
収録日:2014/06/07
追加日:2014/07/03
自民党が「いま解散には一番いい時期」と判断する理由
「消費増税先送り」解散の意味を問う
ここに来て、安倍晋三首相が消費税率10パーセントへの再引き上げを先送りすると判断した場合、直ちに衆議院を解散し、年内の総選挙に踏み切るとの見方が広がっている。この解散を成り立たせているいつかの要素やそのロジック...
収録日:2014/11/12
追加日:2014/11/17
「三本の矢」の成果は? 2年間の是非を問う
今回の選挙の経緯と争点であるアベノミクスについて
衆議院選挙が始まった。今回の選挙の裏側には何があるのか。最大の争点・アベノミクスは果たしてどうなっているのか。星浩氏が語る総選挙・第1回目。
収録日:2014/11/20
追加日:2014/11/21
非常に特徴的だったのは史上最低の投票率になったこと
今回の選挙を振り返る
誰もが驚いた、「消費増税先送りを問う」突然の解散。今回の選挙は、一体、何が争点だったのか。朝日新聞特別会編集委員の星浩氏の明快な解説で振り返る。
収録日:2014/12/18
追加日:2014/12/23
なぜギリシャは危機的事態に陥ったのか?
ギリシャ危機~経済指標から見る今後の展望~
一応の合意にたどりつつある今回のギリシャ問題だが、まだギリシャ議会を通す作業に加え、ユーロ諸国による具体的支援を詰める作業も残っているため、先行きは不透明だ。一体なぜギリシャはこのような危機的事態に陥ったのか。...
収録日:2015/07/15
追加日:2015/07/17
アメリカ経済の好況はトランプではなくオバマ時代の成果
トランプ政権研究(7)トランプ相場に湧く株式市場
公立大学法人首都大学東京理事長の島田晴雄氏が、最高裁判事の任命とトランプ相場について解説する。トランプ大統領は最高裁判事に史上最年少のゴーサッチ氏を任命した。今後半世紀ほど、司法が保守に傾く可能性がある。経済は...
収録日:2017/05/23
追加日:2017/06/28
戦後日本はなぜ復興できたか…占領からバブル崩壊への流れ
現代ドイツの知恵と経験に学ぶ(3)戦後日本の復興
2017年7月のドイツ訪問で多くの情報、知見を得た公立大学法人首都大学東京理事長・島田晴雄氏が、ドイツと日本の戦後復興の経緯を徹底比較。戦後、ドイツと異なり間接占領で復興に向かった日本は、東西冷戦を経て世界における位...
収録日:2017/09/12
追加日:2017/10/27
トランプ大統領は経済学の基本が分かっていない
2018年激動の世界と日本(4)トランプの経済政策
公立大学法人首都大学東京理事長・島田晴雄氏は、ドナルド・トランプ大統領は経済学の基本を理解できていないと喝破する。貿易収支の不均衡を不当貿易のせいにしたり、無闇にWTOを批判してみせたりと、話題に事欠かないトランプ...
収録日:2018/01/16
追加日:2018/04/21
マクロでみる世界経済の需要と供給のバランス
需要は安泰なのか~マクロ経済の観点から考えるリスク要因
今、日本もアメリカも需要は強いが、供給が追いつかない状態にある。このように需要が景気を引っ張っている場合、一度それが減退すると経済失速に陥りかねない。マクロ経済の観点から、世界経済の需要と供給のバランスを分析し...
収録日:2018/11/14
追加日:2019/01/05
バブル世代は「バブル崩壊世代」、苦労の先に見えるものがある
バブル世代の現実とこれからの生き方
バブル世代はバブル経済に恩恵を受けた世代ではなく、じつはバブル崩壊でとても苦労した世代である。その苦労してきた人生を僻みに思うことなく、自分にとって本当にやりたいことを求めていけば、この先の人生で精神的な充足を...
収録日:2021/08/31
追加日:2021/12/14
結局、主流派と異端派の何が違うか…経済学史の大きな示唆
本当によくわかる経済学史(16)現代の経済学のコンセンサス
1970年後にスタグフレーションに陥ったことにより、ケインズ的な政策よりもフリードマンの金融政策が受け入れられていくことになる。柿埜氏は「実態と理論が合っているからこそ、主流派は主流たり得る」ことを強調し、異端派と...
収録日:2022/06/08
追加日:2023/03/22
介入主義?社会主義?…ニューリベラリズムとは何か?
日本人が知らない自由主義の歴史~前編(5)ニューリベラリズムの台頭
19世紀後半になると、リベラリズムに変容が見られるようになる。自由実現のために政府が積極介入すべきという「大きな政府」を肯定するニューリベラリズムの台頭である。ここでは、ニューリベラリズムが登場した背景やその思想...
収録日:2022/07/01
追加日:2023/05/16
「三種の神器」ブームの後に来た最大の危機…その予兆とは
松下幸之助の危機克服~熱海会談の真実(2)最大の危機と予兆
佐久間氏は自身の苦境を乗り越えるにあたり、松下幸之助の「最大の危機」を参考にしたという。それは1964年7月、松下関係者と販売会社・代理店のトップ200名を集めて行われた「熱海会談」である。(2023年12月1日開催日本ビジネ...
収録日:2023/12/01
追加日:2024/06/17
風景画家だけの集まり…?誤解された印象派の本当の姿
印象派とは~画家たちの関係性から技法まで(1)印象派への誤解
印象派はしばしば誤解されている。風景画だけを描いていたのではないか、画家たちがとても貧しかったのではないか。そういった誤解が印象派にはまとわりつくのだが、実際には、風俗画も印象派の主題として欠かせない要素だった...
収録日:2023/12/28
追加日:2024/12/28
モネの作品が売れない!? 印象派に与えた不況の影響
作風と評論からみた印象派の画期性と発展(3)印象派展とサロン
アカデミックなサロンに対して距離を取り、前衛的な作風に挑むというイメージが強い印象派だが、実際にはそんな単純な関係ではなかった。印象派展を顧客へのアピールの場と捉え作品を出品していたモネをはじめとする印象派と、...
収録日:2023/12/28
追加日:2025/07/24
政治家が線香を持参してお供えすることは公職選挙法違反
政治家としての原点、そして挫折と再生
「塞翁が馬」とは、小野寺五典氏のための言葉ではないだろうか。公務員を辞めるきっかけは「文句は政治家になって言え」の一言。トントン拍子の初当選から2年後には議員辞職を余儀なくされる。しかし、その後のつらく苦しい期...
収録日:2014/06/17
追加日:2014/07/17
黒字申告割合が3割―日本の納税企業率の驚異的な低さ
法人税改革の三つの論点
日本企業の黒字申告割合は3割に満たない。国の歳出増大が続く中、法人税増収のための活路はどこにあるのか。国と企業、政治と経済の間に横たわる「法人税改革」に必要な三つの論点を曽根泰教氏が見抜く。
収録日:2014/05/28
追加日:2014/08/01
消費税率引き上げ後の消費の反動減は思った以上に厳しい
アベノミクスの正念場~東大日次指数から見る~
2パーセントの物価目標を導入した日銀。しかし、民間の予測とは大きな乖離があり、市場関係者は今、固唾をのんでその動向を見守っている。輸出や生産、賃金などの各指標の動向の解説とともに、速報性に優れる売上高や物価に係...
収録日:2014/08/05
追加日:2014/08/08
Jカーブ効果における為替のタイムラグも輸出に関連
円安が進んでいるのになぜ輸出が増えないのか?
アベノミクスの効果による円安の進行により、輸出が増えるという期待を皆が抱いた。ところが、輸出は思ったほど増えず、現状は期待通りにはいっていない。円安が進んでいるのに、なぜ輸出が増えないのか?伊藤元重氏がその要因...
収録日:2014/09/08
追加日:2014/09/15
五・一五事件は2年前にすでに予告されていた!?
本当のことがわかる昭和史《3》社稷を念ふ心なし――五・一五事件への道(1)若者に歌い継がれた『青年日本の歌』
1932年の五・一五事件の中心人物となる海軍の三上卓中尉が、事件の2年前に作詞・作曲した『青年日本の歌』という歌がある。犬養毅首相を殺害した三上中尉ら被告人たちに国民から数多くの減刑の嘆願書が寄せられたが、三上...
収録日:2014/12/22
追加日:2015/08/24
安い労働力を使い捨てる企業が淘汰される時代に
日本経済の救世主は「雇用」の中から出現するか
アベノミクス第2ステージを迎え、実体経済が大いに変わっていく。中でも東京大学大学院経済学研究科教授・伊藤元重氏が注目しているのは「雇用」の分野。そこから、日本経済の救世主が現れる可能性があるという。
収録日:2015/09/17
追加日:2015/10/22
新興国に流れた資金が逆流し始めていることが懸念材料
BRICsの幻想・中国の勘違い
東京大学大学院経済学研究科教授・伊藤元重氏が、世界的金融不安をBRICsの観点から解説する。「これからはBRICsが世界経済を引っ張る」「中国経済は今後も成長し続ける」――多くの予想が浮かんでは消えてきた中、世界...
収録日:2015/09/17
追加日:2015/11/05
観光戦略に注目!2020年にむけて進めるべきこととは
アジア大交流時代の観光戦略
10年後、20年後、アジアに「大交流時代」が訪れると、東京大学大学院経済学研究科教授・伊藤元重氏は語る。大交流時代に向けた「新たな観光戦略」を考える。
収録日:2015/12/02
追加日:2016/01/11
日本と世界の経済認識のズレが露見した伊勢志摩サミット
伊勢志摩サミットを総括する
政治学者で慶應義塾大学大学院教授・曽根泰教氏が2016年5月26日、27日に行われた伊勢志摩サミットを総括する。曽根氏は、議長国の首相として安倍晋三氏の根回しは評価に値するとしながらも、安倍首相の主張にはある大...
収録日:2016/06/01
追加日:2016/06/09
島田晴雄が評価する第一次アベノミクス
2017年世界と日本(7)第一次アベノミクスの評価
第一次アベノミクスは2013年初頭から2015年9月に行われた「デフレからの脱却」を目指す政策だった。その結果がしっかりと検証されないまま、第二次アベノミクスへ突入した安倍政権だが、公立大学法人首都大学東京理事長・島田晴...
収録日:2017/01/24
追加日:2017/05/13
トランプ大統領の4つの経済政策の現状
トランプ政権研究(8)主要経済政策の分析
公立大学法人首都大学東京理事長の島田晴雄氏が、トランプ大統領の主要な経済政策について解説する。目玉である大幅な減税と大規模なインフラ投資には、財源の問題が浮上している。オバマケアを廃止して提出された共和党案も、...
収録日:2017/05/23
追加日:2017/06/29
欧米の中央銀行による金融政策正常化の論点
金融政策正常化の難しさ(1)欧米の金融引き締め政策
最近、欧米では金融政策正常化の機運が高まっているという。その正常化の経緯やそこに伴ういくつかの困難、その背景等について、共立女子大学国際学部教授の植田和男氏が2話にわたり解説する。今回は、特に顕著なFEDの引き締め...
収録日:2017/07/19
追加日:2017/08/12
欧米で高まる金融政策正常化の背景と今後の可能性
金融政策正常化の難しさ(2)今後の可能性と日本への影響
欧米で高まっている金融政策正常化とその難しさについて、共立女子大学国際学部教授の植田和男氏が解説。第2話では、正常化の背景と今後の可能性を論じ、量的緩和の出口に向かうであろう日本への影響を考える。(全2話中第2話)
収録日:2017/07/19
追加日:2017/08/13
「日本再興戦略」の欠点は優先順位、原因分析の欠如
少子高齢化と財政の役割(1)経済と財政の現状
明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授の田中秀明氏が少子高齢化とひっ迫する日本財政の問題を取り上げる。第1回レクチャーでは、アベノミクスの経緯、成果に触れつつ、日本の経済および財政の現状を概観。経済はそこそこ...
収録日:2017/07/28
追加日:2017/09/06
経済成長だけに頼った財政再建は困難だ
日本の財政の未来(4)財政再建と成長率・金利論争
法政大学経済学部教授の小黒一正氏が、財政再建問題について、成長率と金利の観点から解説する。金利と成長率はこの30年間、同じように推移してきた。トレンドとしては、金利と成長率の差が1パーセントという状況が、OECD諸国に...
収録日:2017/08/01
追加日:2017/09/20
日本の将来のために増税の是非を本気で考えるべき
高齢化と財政危機~その解決策とは(10)異次元金融緩和と消費増税
公立大学法人首都大学東京理事長の島田晴雄氏が、債務累積問題の解消に向けて、日本が取るべき方策を検討する。異次元金融緩和は、すでに出口戦略を模索すべき時期に達している。消費税増税も2019年に延期されてしまったが、増...
収録日:2017/10/05
追加日:2017/11/24
2020年以降の日本経済を動かす要因とは何か?
2020年以降の日本経済を動かす3つの要因
安倍内閣6年目にして概ね回復傾向を見せる日本経済だが、依然として景気悲観論は根強く、2020年の東京オリンピック・パラリンピックが終わればまた厳しくなるという声すらあるほどだ。そこで東京大学名誉教授で学習院大学国際社...
収録日:2018/02/21
追加日:2018/03/23
産業再生機構の取り組みは今後日本の参考になる
産業再生機構に学ぶ新産業の人材育成
人材が薄い新産業にとって有効なアプローチはどのようなものか。バブルの負の遺産を処理するために5年間の時限立法で作られた産業再生機構の運営ルールから、ボストン・コンサルティング・グループ シニアパートナー&マネージ...
収録日:2018/03/12
追加日:2018/06/02
全国に広がった「空襲を記録する会」の運動
東京大空襲と私(2)「空襲を記録する会」と戦災誌の編纂
一面の焼け野原から出発した東京の復興を後押ししたのは、1950年の朝鮮戦争勃発に伴う特需景気である。しかし、横田や入間の米軍基地から飛び立つB-29の行く手に、民間人の多大な被害が待っていることはあまりに明らかだ。苦渋...
収録日:2018/03/26
追加日:2018/08/01
世界史の大転換点、世界と日本の未来を考える
2019年激変する世界と日本の針路(1)米貿易戦争の影響
2019年は世界史の大転換点を迎えていると、島田晴雄氏は言う。アメリカをはじめ、イギリス、EU、ロシア、中国、そして日本と、世界経済や日本経済においていったい何が起こっているのか。このシリーズレクチャーでは「激変する...
収録日:2019/01/28
追加日:2019/05/15
マクロ経済の動向を決める第一要因はオリンピックではない
オリンピック後の経済を考える(2)日本の取るべき道
一般に、オリンピック後は経済が低迷するといわれているが、必ずしもそうではないとして、伊藤元重氏はロンドンオリンピック後のイギリス経済について解説する。ただ、マクロ経済の動向を決める第一要因は決してオリンピックで...
収録日:2019/10/31
追加日:2019/11/27
経済学史の基礎知識…大きな流れをいかに理解すべきか
本当によくわかる経済学史(1)経済学史の概観
現代社会の「経済」を正しく理解するためには、実は、正しい「経済学史」を理解していることが大きな助けとなる。逆に、正しい「経済学史」を知らなければ、怪しげな経済理論にダマされてしまうことにもなりかねない。気鋭の経...
収録日:2022/06/08
追加日:2022/11/16
異端の経済学者…ドイツ歴史学派、社会主義、マルクス主義
本当によくわかる経済学史(5)古典派を批判した異端者たち
古典派経済学が一世を風靡した時代には、それに批判的な意見も登場する。それが、ドイツ歴史学派や、社会主義、マルクス主義といわれるグループだった。これらの考え方は今でも根強く残っているのだが、やはり「異端」であって...
収録日:2022/06/08
追加日:2022/12/14
大きな政府も第三の道も行き詰まり…現代リベラリズムの混迷
日本人が知らない自由主義の歴史~前編(7)現代リベラリズム
「現代リベラリズム」はニューリベラリズムの流れを組んでおり、特にアメリカでは大恐慌から1960年代までは有力であったが、その後はリベラルな政党はどんどん没落していくことになる。あらためて現代リベラリズムによる政策と...
収録日:2022/07/01
追加日:2023/05/30
日銀の金融政策はどうなるか?日本株の動きをどう読むか?
2023年前半の金融市場と日本の行方(1)全体観と日本株の動向
2023年春の時点で、世界経済ならびに金融市場でどのようなことが起こっているかについて解説する。実は現在、米国2年国債と10年国債の利回りの逆転現象が起きている(逆イールド現象)。これは通常、大きな景気後退前に現れる現...
収録日:2023/06/05
追加日:2023/07/09
新しい価値を提供して既得権を打ち破るのが企業の使命
日本企業の病巣を斬る(12)最大の既得権とは
現代社会で一番どうしようもない状態になっているのが既得権の問題である。この問題を解決できないと、日本も世界も、どの国の経済も、いい状態に戻ることはできない。そして今、最大の既得権となっているのは、社会保障である...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/02/16
借金は悪ではない!? どうやって「賢い支出」をすればいいか
日本の財政政策とその効果を検証する(6)「賢い支出」のすすめ
世界では近年、財政政策が非常に注目を集めている。これは先進国が「セキュラー・スタグネーション」と呼ばれる長期停滞に陥っているからだ。そこからの脱却のためには財政出動が必要なのだといわれているのだが、日本は特に「...
収録日:2023/12/14
追加日:2024/04/11
未来が危ない…メガトレンドの変化が生み出す2100年の日本
第2の人生を明るくする労働市場改革(3)3つのメガトレンドの変化
「雇用は生産の派生需要」という言葉が経済学にはある。これは非常に重要な命題で、人や雇用が先ではなく、生産があって初めて雇用が生まれるという考え方だ。そして、経済の状況が変われば雇用環境も変化を余儀なくされるので...
収録日:2024/08/03
追加日:2025/02/21
このように投資にお金を回せば、社会課題も解決できる
お金の回し方…日本の死蔵マネー活用法(6)日本の課題解決にお金を回す
国内でいかにお金を生み、循環させるべきか。既存の大量資金を社会課題解決に向けて循環させるための方策はあるのか。日本の財政・金融政策を振り返りつつ、産業育成や教育投資、助け合う金融の再構築を通した、バランスの取れ...
収録日:2024/12/04
追加日:2025/03/29
先進国の自動車保有台数は二人に1台からもう増えない?
人工物の飽和
地球規模の環境問題、人工物の飽和、豊さから生まれた新たな課題に遠からず世界が直面する。長期のGDP推移、自動車保有台数、セメント投入量など、様々な指標から現代を読み解く。
収録日:2013/10/21
追加日:2014/06/29
日本の市場に大きな影響を及ぼす米国の金融政策
FEDの金融政策、米国株価から見る日本経済の今後
過去20年間の米国株価の下落時には日本の株価も下落傾向にあった。今後の米国の金融政策に応じて株高が続く米国経済はどう動き、日本の資産価格と経済はいかに見通せるだろうか。経済学者 植田和男が解説する。
収録日:2014/02/13
追加日:2014/02/24
インフレターゲット論の欠陥とは?
中央銀行の役割
巷に溢れる金融緩和論。では、無制限にお金を供給すればインフレは起こり、実体経済は本当に回復するのか?従来型の金融政策の限界点やインフレターゲット論の問題点を論じつつ、中央銀行がとるべき姿勢と役割を示唆する。
収録日:2012/11/20
追加日:2014/03/27
TPP、日韓関係、ウクライナ―オバマ来日前に難問山積み
前原レポート:米国から見た日本(2)アベノミクスと財政、オバマ来日の主要テーマ
前原誠司氏による、ワシントン訪問記第二弾。前半の安全保障問題に加えて、いまアメリカから見た日本の問題点が広く集まった。オバマ首相4月来日に向けて、カウントダウンの今、日本は何を決断して動くべきか。
収録日:2014/03/20
追加日:2014/04/17
運が悪いときは「時間」と「距離」が解決してくれる!
わが行動原則「運気と波動」
経営には「運気」は重要な要素だ。良い運気を引き寄せるために大切なことは、第一に、いい気をもつ企業や人を見極めて付き合う。第二に、世の中のすべては「陰と陽」でまわっていると心得て、そのバランスを大切にする。そし...
収録日:2014/03/31
追加日:2014/05/22
経営の神様から学んだ「国家経営」という考え方
四人の恩師
政治家・前原誠司氏にとって、欠かすことができない四人の恩師がいる。国際政治を学んだ学生時代、松下政経塾の頃、そして政治家になってからと、大事な時期に前原氏を支えた恩師たち。その人物像について、前原誠司氏が熱く語る。
収録日:2014/03/20
追加日:2014/06/05
クビチェック大統領が築いた「ブラジリア」は人類史的偉業
ブラジルの繁栄と転落(1)ブラジリアと軍政時代
BRICsのトップと言われたブラジルが低迷段階に入ったと言われている。しかし、ブラジルには復元力があると語る島田晴雄氏。繁栄と転落の歴史の中で、ブラジル経済がいかに復活を遂げていったのか。シリーズ前編となる今回...
収録日:2014/04/10
追加日:2014/06/12
大切なのは量的緩和で買った時間で日本の将来を考えること
量的緩和で日本経済の体質改善は果たせるか?
不況下において、世界中で量的緩和政策がとられ、日本でも大規模な量的緩和を推進してきた。この人類にとってはいわば未知の領域において、日本が手に入れたものとは何なのか? そして、日本はそれを今後の経済政策にどのよう...
収録日:2014/05/28
追加日:2014/06/26
成長戦略に注目する声もあるが市場の本心は再度の量的緩和
アベノミクスの行方を読む~量的緩和とインフレ期待~
安倍政権発足から1年と半年が過ぎた今、アベノミクスへの不安が広がっている。昨年12月に暴落した株価や、今年4月から8パーセントに上がった消費税の影響など、果たして今後アベノミクスはどうなっていくのか。第一の矢で...
収録日:2014/05/28
追加日:2014/07/03
規制中心の行政から県民総幸福量の最大化を目指す行政へ
蒲島県政(1)決断の政治
熊本県知事・蒲島郁夫氏が、「熊本県政」ではなく自らの名前を冠して「蒲島県政」と呼ぶには訳がある。そこにはリーダーシップのあり方を追究し実践する、知事としての覚悟が込められているからだ。蒲島県政の「決断の政治」「...
収録日:2014/05/16
追加日:2014/07/10
危機管理のプロ・宮城県村井知事と二人三脚で被災地を回る
東日本大震災を振り返る~地元・気仙沼への想い~
東日本大震災のときの貴重な経験が、今の小野寺五典氏を支えている。果たして震災時はどんなことがあったのか。それが、その後の政治活動にどんな影響をもたらしたのか。当時を振り返りながら、地元・気仙沼への想い、自らの役...
収録日:2014/06/17
追加日:2014/07/24
「ボールを離さないと日本がつぶれる」と感じて解散を決意
社会保障と税の一体改革(3)質疑応答
「社会保障と税の一体改革」に関する講演を終えた野田佳彦氏への質問は三つ。民主党の存在価値、安倍政権、そして2年前の党首会談で解散と決めたときの気持ちについて。それぞれ野田氏が真摯に答えていく。(2014年6月7...
収録日:2014/06/07
追加日:2014/07/17
21世紀の毛沢東と周恩来を目指しているのか?
習近平の野望~中国の権力闘争
薄熙来、徐才厚、周永康と相次ぐ超大物の摘発、失脚。この「粛正」を断行しているのが習近平国家主席だ。「腐敗追放」のスローガンの背後で習近平が真に狙うものは何なのか。岡崎久彦氏が彼を「毛沢東かスターリンか」と評する...
収録日:2014/08/01
追加日:2014/09/04
安倍・菅体制で官邸からのコントロールが相当利いている
内閣改造とは何か~安倍政権の内閣改造を分析・評価する~
地方創生や女性の登用を目玉として打ち出した2014年9月の安倍政権の内閣改造。曽根泰教氏が安倍政権の特徴を明らかにしつつ、今回の内閣改造を分析・評価し、内閣改造の本質を浮き彫りにする。
収録日:2014/09/11
追加日:2014/09/21
厳しい時代にも生き残れるのは、底力のある人
松下幸之助と上甲晃の人づくり(2)志と底力
松下幸之助氏、そして上甲晃氏が重視する“人間力”とは、“志”や“底力”だと上甲氏は言う。では、志、底力とは何なのか。豊富な具体例をもとに上甲氏が分かりやすく解説する。(後編)
収録日:2014/07/31
追加日:2014/11/06
英語でどう言えばいいのか分からない「念のための解散」
衆院解散総選挙の理由と安倍首相にとってのリスク
2014年11月18日、安倍晋三首相が衆院の解散を表明した。12月2日公示・14日投開票で総選挙が行われる。この解散総選挙の理由や、安倍首相にとってのリスク要因を、日本の政治に精通するジェラルド・カーティス氏が...
収録日:2014/11/18
追加日:2014/11/22
アベノミクスの総合評価―第一の矢と第二の矢
アベノミクス2年の評価~第一の矢と第二の矢
先の衆院選で、日本はこれから4年間、安倍政権に命運を委ねることを選択した。島田晴雄氏は、だからこそ今、「アベノミクス」とは何なのか、その課題はどこにあるのかを、しっかりと考え理解しなければならないと語る。アベノ...
収録日:2015/01/27
追加日:2015/02/12