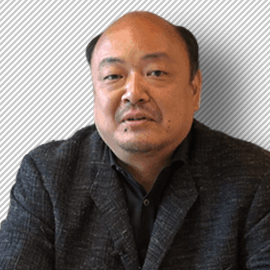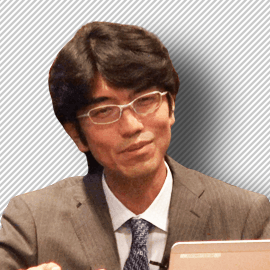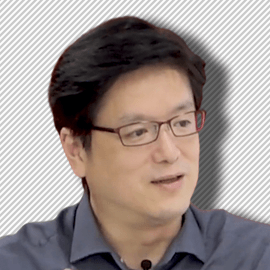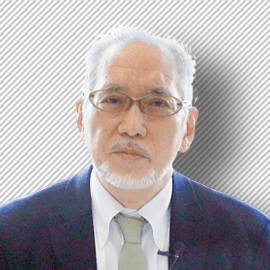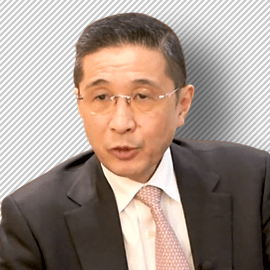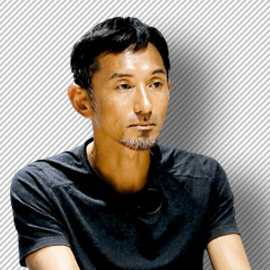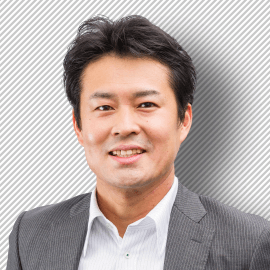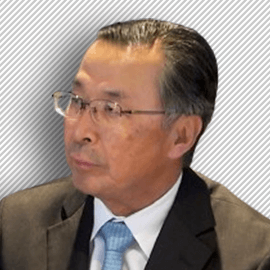マルチスケールエンジニアリングによる安心で安全な未来
教養としてのナノテクノロジー(10)界面現象とマイクロ流体システム
ナノメートルスケールの発見をメートルサイズスケールの人間の生活に役立てるには、実用に供するデバイスをつくり出す必要がある。近年、マイクロ流体システムを使用したデバイスの開発により、医療効率が格段に上がることが予...
収録日:2021/03/29
追加日:2021/09/23
GAFAやBATHに学ぶべきは「リバースエンジニア」という方法
日本企業の弱点と人材不足の克服へ(5)「リバースエンジニアリング」せよ
抽象化や普遍化が苦手な日本人は、まず現場を抽象化するといい。トヨタ生産方式はアメリカのスーパーマーケットの仕入れ方式を抽象化するところから生まれた。加えて、GAFAやBATHのようにリバースエンジニアする。つまりは真似...
収録日:2020/10/28
追加日:2021/01/24
経済学的な発想のポイントは社会のありようを考えること
経済学的発想とは何か(1)エンジニアリング的との違い
経済学は幅広く、奥も深い。それは、社会のありようを見つめ、人と人の相互作用を考える学問であるからだ。エンジニアリング的に明快にINとOUTを切り分けることもするが、その間のブラックボックスは人間任せの複雑さが影響して...
収録日:2019/07/10
追加日:2019/09/03
なぜ「ジョブズと仕事をすると限界を突破できる」のか
スティーブ・ジョブズの成功哲学(7)才能とお金をどう生かすか
開発者としてだけではなく、経営者としても卓越した才能を持っていたスティーブ・ジョブズは、アップルに復帰後、当時どん底だったアップルを劇的に復活させ、世界を代表する企業に押し上げた。相手の才能を引き出す考え抜かれ...
収録日:2022/03/15
追加日:2022/06/04
禅はジョブズの哲学にどのような影響を与えたのか
スティーブ・ジョブズの成功哲学(9)なぜ「禅」に魅せられたのか
スティーブ・ジョブズが若い時から東洋の思想に強く影響を受けていたことはよく知られている。ジョブズはどのようにして禅に出会い、それは製品にどのような影響を与えたのか。ジョブズの死生観や時間の感覚などから、ジョブズ...
収録日:2022/03/15
追加日:2022/06/18
海底で働く自律型海中ロボットの作業をスライド解説!
自律型海中ロボットは何を目指すか(3)海に眠る鉱物資源
近年、日本周辺には海底鉱物資源が豊富にあることが分かってきた。海中ロボットの研究を進める九州工業大学社会ロボット具現化センター長・浦環氏は、日本は地の利を生かして新技術開発を率先して行うべきだ、と主張する。ハー...
収録日:2016/01/12
追加日:2016/07/13
日本の技術はスゴイ!世界が注目する日本企業の可能性
半導体から見る明日の世界(11)3次元半導体の世界と日本の可能性
限界を超えたともいわれている半導体の超微細化は、ついに2次元から3次元の技術に突入した。しかし、半導体の技術が高度化すればするほど、それを加工して製品化するためにはさまざまな特殊技術が必要となる。さらに、それらの...
収録日:2023/07/14
追加日:2023/11/06
木造建築の耐震・耐火性能は都市なら鉄骨・RC造並みが必要
都市木造の可能性~木造ビルへの挑戦(5)より豊かな都市空間へ
「木造」といえば問われる耐震性、耐火性。だが木造建築が強度で劣ったのは過去の話。技術の向上は鉄骨・RC並みの強度を実現し、木造による大空間さえも現実のものとした。東京大学生産技術研究所教授・腰原幹雄氏が都市木造...
収録日:2015/10/06
追加日:2016/02/11
フラッシュメモリの開発者は「評価されない英雄」
世界を変えた「フラッシュメモリ」(1)開発者の実像
資産価値2兆円にも上る半導体事業の売却が話題となった東芝。その半導体事業の内実については、これまでメディアで詳しく報じられてこなかった。その中核である「フラッシュメモリ」は、個性的な開発者による“人類史上、最も重...
収録日:2018/10/19
追加日:2019/01/01
中国とアメリカでダイナミズムを生んでいる理由
日本企業の弱点と人材不足の克服へ(8)日本でダイナミズムを生むために
中国の驚異的な経済発展は、中国が「大国」であることが大きい。大国の強みはアメリカのシリコンバレーを見ても分かる。シリコンバレーには政府から多額のお金が落ちているが、一方で無政府主義者も多い。相容れない2つが共存し...
収録日:2020/10/28
追加日:2021/02/14
心理的安全性の阻害要因「5つの対人不安」とは
チームパフォーマンスを高める心理的安全性(3)心理的安全性と対人不安の関係
「率直な意見を」と促されても気を許せないのが日本の企業風土。「空気が読めない」「立場をわきまえろ」と言われてしまうことへの不安や、自分は無知であるという意識から発言を控えることもある。だが、そんな対人不安こそ、...
収録日:2022/04/26
追加日:2022/08/06
ポジショニングアプローチと資源アプローチの考え方とは
ダイナミック・ケイパビリティ~組織の戦略変化(3)ビジョンと戦略経営
戦略的な経営に必要なのは、自己と他者について知り、目指すべきビジョンを示すことだ。かつてマイケル・ポーターは競争の場の選択が重要(ポジショニングアプローチ)だとし、ジェイ・バーニーは良質な資源を育てることが競争...
収録日:2016/06/23
追加日:2016/09/13
論文の数に見る日本の研究開発の国際的な遅れ
科学技術とイノベーションマネジメント(4)研究開発動向
東京工業大学環境・社会理工学院教授の梶川裕矢氏が、イノベーションを生み出すためのデータ分析手法である「計量書誌学」の活用例を解説する。このデータ分析によって、世界中で行われている科学技術の開発動向や、今後重要な技...
収録日:2018/06/18
追加日:2018/10/21
イノベーションのためのアイデアはどう生まれるか?
科学技術とイノベーションマネジメント(5)探索的設計
計量書誌学の活用例としては、異なる技術の新しい組み合わせ可能性を探る関連性分析や、新しい技術アイデアを事業に結び付ける、「論文-特許関連性分析」を挙げることもできる。東京工業大学環境・社会理工学院教授の梶川裕矢氏...
収録日:2018/06/18
追加日:2018/10/22
フラッシュメモリの歴史は「非常識なアイデア」から
世界を変えた「フラッシュメモリ」(2)誕生秘話・発明編
フラッシュメモリは、意外にも「性能を悪く」して生まれたものだった。当時の業界からすれば、あまりに“非常識”な発想で、受けいれられるものではなかった。しかし、その発想をきっかけに、メモリ業界に革命を起こしていくこと...
収録日:2018/10/19
追加日:2019/01/04
リアルエコノミーにICT技術をどう活用するか
デジタルトランスフォーメーション(1)製造業の場合
技術革新の加速度的スピードを少しでも取りこめれば、社会も企業も大きな変化を起こせる。現に、リアルエコノミーはデジタルトランスフォーメーションによって変化し始めている。今回は、AIやICTの活用により、需要起点のソリュ...
収録日:2018/11/14
追加日:2019/01/07
醸造酒から蒸留酒の作り方を学問する面白さ
科学的思考はなぜ大切か(4)基礎数学の大切さ
よく耳にする醸造酒と蒸留酒。この2つの違いや作り方などについて岡部徹氏の解説が進んでいくが、それを理解する上で伝えたいのは「基礎的な数学」の大切さだ。岡部氏も学生の時には、「自然対数など、何でこんな訳が分からない...
収録日:2019/08/30
追加日:2019/10/04
人工流れ星の実現を目指す宇宙ベンチャー起業への経緯
宇宙ビジネスの現在と未来(1)人工流れ星が果たす役割
これまでは「宇宙への進出」といえば、国を挙げての一大プロジェクトという印象が強かったが、ここにきて民間企業の「宇宙ビジネス」への投資が加速している。人工流れ星の実現を目指す宇宙ベンチャー・ALEの代表取締役社長であ...
収録日:2019/09/10
追加日:2019/11/28
男性脳と女性脳の違いから分かる「子育てのトリセツ」
黒川伊保子先生に学ぶ「子育てのトリセツ」(1)男性脳と女性脳はどこが違うのか
「男性と女性では、とっさに見る場所が異なる」――。まだ男女の脳が違うということが社会的に話題にならなかった頃から人工知能開発に携わってきた黒川伊保子先生。その過程で気づいた「男女の脳の特性の違い」とは何か。(全7話...
収録日:2021/06/28
追加日:2021/08/23
トヨタから学んだ重要な戦略要素は「時間」の概念
シリコンバレー物語~IT巨人の実像と今後(6)トヨタ方式に学ぶアメリカ
アメリカはトヨタの「カイゼン」や「カンバン」方式に学び、研究を進めてきた。その最初の一歩はトヨタが再生させたGMの工場視察である。彼らはこれをケーススタディとするだけでなく、普遍化し、一般的に通用する理論を導き出...
収録日:2021/07/08
追加日:2021/12/26
ジョブズがパロアルト研究所で気づいた「パソコンの未来」
スティーブ・ジョブズの成功哲学(2)ジョブズの略歴〈上〉
20歳の若さでアップルを創業したスティーブ・ジョブズだったが、30歳のときに自分がつくった会社をクビになってしまう。養子であることがジョブズの思想に与えた影響や、スティーブ・ウォズニアックとの出会いなど、アップル追...
収録日:2022/03/15
追加日:2022/04/30
ジョブズが考える「永遠に続く会社」、大事なのは価値観
スティーブ・ジョブズの成功哲学(4)永遠に続く会社のつくり方
スティーブ・ジョブズが目指したのは、社会に影響を与え、後世に続く会社を作り上げることだった。目先の利益に惑わされず、明確な理念を掲げ、それを共有した社員とともにより良い製品の開発のために絶えず努力を続けたことが...
収録日:2022/03/15
追加日:2022/05/14
偶然が生み出す魔法――ジョブズのイノベーション哲学とは
スティーブ・ジョブズの成功哲学(6)イノベーションの起こし方
常に社会にイノベーションを起こそうとしてきたジョブズは、イノベーションを起こすための会社づくりにも力を入れてきた。人びとが自然と交流できるオフィスづくりや、突出した製品を生み出すための選択と集中、また製品のプレ...
収録日:2022/03/15
追加日:2022/05/28
食肉3.0時代に突入、「培養肉」研究の今に迫る
培養肉研究の現在地と未来図(1)フェイクミート市場とリアルミート研究
食糧難、環境保護などの観点から、そのあり方に見直しを迫られている畜産業界。その状況にあって、近年、技術開発が進んでいるのが「培養肉」だ。味や食感を似せる「フェイクミート」から、本物の肉と同じ筋肉を再現する「リア...
収録日:2022/10/11
追加日:2023/01/10
企画立案、膨大な社内情報の整理、顧客対応…AI活用事例
Microsoft Copilot~AIで仕事はどう変わるか(5)AI活用のメリット
私たちの日常生活や仕事に深く入り込みつつある生成AI。その汎用性やポテンシャルは歴史的にも画期的で、これからますます不可欠な存在になることは間違いない。私たちはどのようにそのAIを活用し、メリットを享受するのがいい...
収録日:2023/08/01
追加日:2023/10/25
AIへの不安と懸念…だからこそ「教養」が必要になる
Microsoft Copilot~AIで仕事はどう変わるか(7)AI活用の落とし穴
今後、AIが私たちの生活に不可欠な存在になることは間違いないが、そこにはサステナビリティやセキュリティの面で、さまざまな懸念がある。国家、企業、個人は、AI活用に伴うマイナス面に対してどのように対処していくべきなの...
収録日:2023/08/01
追加日:2023/11/08
山尾庸三―工部大学校を設立した「工学の父」
技術と民生から見た明治維新(2)山尾庸三
本編シリーズ講話第2回は、「工学の父」、山尾庸三。現在の東京大学工学部である工部大学校を設立し、近代国家の土台を技術で支える人材を輩出した教育者。明治の文明開化を「生きた機械」として助力した男は、もともと「尊王...
収録日:2014/02/12
追加日:2014/03/06
「ヒートアイランド現象」に対して打つ手はないのか?
身近なところから技術でエコ
日本の都会の夏を住みづらくさせている「ヒートアイランド」。誰もが「仕方がない」とあきらめているこの現象に、打つ手はないのか。われわれの身近なところから、この問題の解決策を小宮山宏氏がポイントを絞って解説する。
収録日:2008/05/21
追加日:2014/04/30
物事の本質と価値のその先に何があるのか考える
LINE流イノベーティブ思考術(3)価値の「先」をデザインする力
3年足らずで4億ユーザーを突破したLINE。ネット史に残る成長を可能にした、シンプルな発想とは。LINE株式会社代表取締役社長CEO森川亮氏の成功のカギに迫る。(全5話中第3話目)
収録日:2014/05/14
追加日:2014/06/26
縁と偶然! 指導教官と真面目な黒沢君とのエピソード
研究者を志したきっかけ
「人生はアクシデンタリーに決まるものだ」と言う小宮山宏氏。 化学工学を研究する道に進んだが、そこにはいくつかの偶然が重なっていた。果たしてその偶然とは? 一般のメディアではなかなか触れることができない、小宮山氏の...
収録日:2014/07/15
追加日:2014/10/23
小さな水力発電を日本中数千カ所で行う!
再生可能エネルギーの未来~小水力発電と地方再生
小宮山宏氏が推進してきたプラチナ構想ネットワークが、小中水力発電という形でもいよいよ実践の段階に入る時が来た。稼働率がよく安定的というメリットを持つ水力発電だが、実は日本にとってはもう一つ本質的な意味がある。地...
収録日:2014/12/05
追加日:2015/01/02
「ソリューション」を売ることが日本の産業界がとるべき道
「島田村塾」リベラルアーツ特講(2)武器としてのソリューション
グローバルな視野に立ちこれからの日本に必要な人材を育成すべく「島田村塾」を主宰している島田晴雄氏が、日本のビジネスの将来のために挙げるキーワードは「ソリューション」。ソリューションを武器に日本が世界市場でサバイ...
収録日:2014/12/05
追加日:2015/01/21
飽和社会、残るわずかなシェアを競ってもゼロサム競争に
飽和型から創造型に移り変わる需要
時代は「飽和型需要」から「創造型需要」に向かうべきだ、と株式会社三菱総合研究所理事長・小宮山宏氏は語る。飽和社会において、その「創造型需要」の鍵になるのが再生可能エネルギーなのだが、中でも小宮山氏が注目するのが...
収録日:2015/02/05
追加日:2015/03/21
そのものより運ぶ方が高い―水はローカル財
水と地球と人間と~日本と世界の水問題(2)水と経済
水リスクマネジメントが、民間主導でグローバルスタンダードになりつつあるという。水リスクマネジメントとは何か。なぜ急激に広まっているのか。地球規模の水循環と世界の水資源に関する研究の第一人者である東京大学生産技術...
収録日:2015/03/19
追加日:2015/08/13
太陽電池の発電コストは2030年に1kWh 6円になる!
蓄電池はより安くなる~再生可能エネルギーの技術予測
米国のテスラモーターズが10kWh蓄電池を約42万円で新発売するという。対する日本製品は、現状160万円台だ。株式会社三菱総合研究所理事長で科学技術振興機構低炭素社会戦略センター長・小宮山宏氏が、再生可能エネル...
収録日:2015/05/13
追加日:2015/06/18
隠れたうつ病を確定診断するポイントとは
うつ病治療最前線(1)うつ病の身体症状と治療の実際
「心の風邪」とも呼ばれる「うつ病」は、いつだれがかかってもおかしくない病気である。しかし、その実態を正確に知っている人は多くない。典型的な症状は? 薬物療法は効果があるのか? 休職して治療すれば、また戻れるよう...
収録日:2015/09/03
追加日:2015/10/15
支払損害保険金額では東日本大震災を上回ったタイの大洪水
水と地球と人間と~日本と世界の水問題(3)水と気候変動
地球温暖化による気候変動の悪影響は、ほぼ水を通じて人間社会に影響が及ぶ。では、温暖化の将来はどうなるのか。どのような水被害が起こるのか。地球規模の水循環と世界の水資源に関する研究の第一人者である東京大学生産技術...
収録日:2015/03/19
追加日:2015/11/02
失敗してもいいから難しいテーマを選んで挑戦せよ!
水と地球と人間と~日本と世界の水問題(7)勉強と研究の違い
大学時代、科学や数学の研究をすることは、社会に出て、ビジネスをする上でも役に立つという。それは一体なぜなのか。地球規模の水循環と世界の水資源に関する研究の第一人者である東京大学生産技術研究所教授・沖大幹氏の語る...
収録日:2015/03/19
追加日:2016/04/21
ディープラーニングとは?AI研究の第一人者松尾豊が解説
人工知能のディープな可能性(1)現在のブームは本物か
SiriやPepperなど、いま人工知能がブームだ。しかし研究者が理想としてきた、「人間のように考えるコンピュータ」の実現はまだ程遠いようにも思える。最前線の人工知能研究は、どのような状況にあるのか。東京大学大...
収録日:2016/01/15
追加日:2016/05/12
技術の優位がビジネスの優位につながるとは限らない?
水ビジネスの動向(2)サービス産業への投資事業
逆浸透膜を使った海水淡水化技術が低廉化し、水ビジネスの展開が期待されている。しかし、単なる技術提供を超える大型の投資プロジェクトであることや民間が水道事業をすることへの不信感が根強いなど、困難も多い。東京大学生...
収録日:2015/05/25
追加日:2016/05/12
水リスク管理は国ではなく私的設置の基準が席巻しつつある
水ビジネスの動向(3)水リスクマネジメントの現況
東京大学生産技術研究所教授・沖大幹氏が、注目される水ビジネスの最新動向を論じる。まずインフラ輸出の難しさだ。社会的価値が高いインフラの整備は、ビジネスとして見ると撤退しにくさや事業展開の面で、他の業種と異なる。...
収録日:2015/05/25
追加日:2016/05/19
同一労働同一賃金における重要なポイント
「同一労働同一賃金」~日本の働き方がどう変わるのか
学習院大学国際社会科学部教授・伊藤元重氏が、安倍内閣の下で盛んに言われるようになった「同一労働同一賃金」の議論について解説する。長らく終身雇用、年功賃金方式をとってきた日本社会がなぜ今、同一労働同一賃金へシフト...
収録日:2016/04/20
追加日:2016/06/16
ロボットにとっては頭脳や身体よりも「五感」が大切だ
自律型海中ロボットの仕事(3)ロボット学のサイクル
「ロボットにとっては、頭脳(コンピューター)や運動器官(ハードウェア)よりも、五感(センサー)が大切だ」と、九州工業大学社会ロボット具現化センター長・特別教授の浦環氏は語る。センサーが大事だというのは、一体どう...
収録日:2016/05/17
追加日:2016/08/29
ビジネスエコシステムでは競争相手をライバルと捉えない
ダイナミック・ケイパビリティ~組織の戦略変化(5)感知・捕捉・転換
組織を戦略的に変える力であるダイナミック・ケイパビリティは、新たな事業機会を「感知」し、それを「捕捉」するビジネスモデルを構築して、それに合わせ組織を「転換」していくことで構成される。ポイントとなるのは「ビジネ...
収録日:2016/06/23
追加日:2016/09/27
GRIPS(政策研究大学院大学)の課題は日本人学生の獲得
GRIPSの課題と人材育成(1)日本人学生を増やすために
立命館大学特別招聘教授でジェトロ・アジア経済研究所長の白石隆氏は、GRIPSの次なる課題を日本人学生の獲得強化だとする。GRIPSには60余の国から留学生が訪れるため、英語漬けの議論を通じて、徹底したトレーニングと人脈作り...
収録日:2017/02/16
追加日:2017/04/25
親が子どもの進路を決めるのは、人的資本の壮大な無駄
GRIPSの課題と人材育成(2)高度な人材の優遇策
最近の日本の若者は内向きになっていると言われるが、立命館大学特別招聘教授でジェトロ・アジア経済研究所長の白石隆氏は、発展途上国への留学はむしろ増えていると指摘する。日本の親はとかく安定した職業へと子どもの進路を...
収録日:2017/02/16
追加日:2017/04/28
南三陸町海底の再調査とカメラロボット普及の課題
遠隔操縦機~カメラロボ(5)水産高校への普及
九州工業大学社会ロボット具現化センター長・浦環氏が、南三陸町での2度目の調査について解説する。この調査では、新たに音響装置を用いることに成功した。今後は、いざというときのために、カメラロボット操縦者の育成が課題で...
収録日:2017/01/27
追加日:2017/06/04
原発事故の海水汚染調査に用いた全自動の無人船ロボット
遠隔操縦機~原子炉ロボット(1)海水の放射能汚染
九州工業大学社会ロボット具現化センター長・浦環氏が、福島第一原発事故の海水汚染調査に用いた、全自動の無人船ロボットについて解説する。30キロ圏内が立入禁止になったため、全自動の無人船ロボットを用いて、海水の放射能...
収録日:2017/01/27
追加日:2017/06/18
企業経営に活用され始めた「サービソロジー」とは何か?
サービソロジーと経営~サービスイノベーション(1)サービソロジーとは
「サービソロジー」を経営に活用する企業が増えているという。それは一体どういう手法なのだろうか。サービス産業の生産性向上が日本経済を力強い成長軌道に復活させる切り札だといわれて久しいが、サービソロジーはその起爆力...
収録日:2017/09/20
追加日:2017/11/15
アシックスによる「顧客との利用価値共創」の事例
サービソロジーと経営~サービスイノベーション(6)利用価値共創と満足度評価
産業戦略研究所代表の村上輝康氏が、前回に続きサービソロジーによるサービスイノベーションについて具体的事例をもとに解説する。今回は優れた技術を店頭に持ち込んだことで顧客との利用価値共創を実現したアシックスと、便益...
収録日:2017/10/12
追加日:2017/11/28
経済活性化のポイント「賃金」が上がらない理由とは?
アベノミクス5年間の成果と課題
東京大学名誉教授で学習院大学国際社会科学部教授の伊藤元重氏が2012年から始まったアベノミクス5年間を総括し、その成果と課題、今後の方向性について論じる。厳しい意見も多いアベノミクスだが、伊藤氏は名目GDP、財政赤字の...
収録日:2017/11/27
追加日:2017/12/28
経営者はステイクホルダーに方向性を示さなければならない
比較制度分析とは何か(2)企業とステイクホルダー
比較制度分析の創始者、青木昌彦教授は企業をステイクホルダーの連合体として捉えていた。経営者はステイクホルダーに対してビジョンを提示し、制度的補完性のある組織をデザインしなければならない。慶應義塾大学商学部教授の...
収録日:2017/11/02
追加日:2018/01/28
イノベーションを「やり遂げる」には何が必要か?
科学技術とイノベーションマネジメント(6)組織設計
東京工業大学環境・社会理工学院教授の梶川裕矢氏によれば、イノベーションを起こすためには科学技術だけでなく、その前提となる社会的環境も同時に考えなければならない。そのために求められる組織設計の要諦とはいかなるもの...
収録日:2018/06/18
追加日:2018/10/23
非常識な発想に基づく開発は、非常に合理的だった
世界を変えた「フラッシュメモリ」(4)貫いた「非常識」
NAND型フラッシュメモリの開発には、さまざまな障壁があった。それを乗り越えられたのは、舛岡富士雄氏が当時の常識からすれば全く「非常識」な考えを持ち、その信念を貫き続けたからだ。また、そこには社内の重要な支援者の存...
収録日:2018/10/19
追加日:2019/01/11
バカな発想に執着し実践する人がイノベーションを起こす
世界を変えた「フラッシュメモリ」(5)「硬骨の人」の真意
2004年、元東芝社員・舛岡富士雄氏が古巣・東芝を訴えたというニュースが飛び込んできた。フラッシュメモリの発明対価として約10億円を請求するという内容。しかし、舛岡氏の真意は、金銭より日本の技術者やものづくりを大切に...
収録日:2018/10/19
追加日:2019/01/15
中国とアメリカの覇権闘争と北朝鮮問題の行方
2019年激変する世界と日本の針路(11)中国の行方と北朝鮮
苦境に立たされている中国ではあるが、長く反植民地化されてきた歴史を踏まえ産業連関を踏まえた30年計画の経済成長戦略に基づいている。これは米国にとっては脅威であり、両国の間で覇権闘争が起きている。また、トランプ大統...
収録日:2019/01/28
追加日:2019/05/21
暗黙知と形式知とはどのようなものなのか
知識創造戦略論~暗黙知から形式知へ(6)暗黙知と形式知
私たちが生み出すべき知識は、どのようにして成り立っているのだろうか。知識には暗黙知と形式知の二種類があり、それらの相互作用によって知識が生まれるという。両方の知識は共に必要だが、特に暗黙知は競争優位の源泉として...
収録日:2018/11/24
追加日:2019/08/29
生態心理学者としてのダーウィンを考える
「アフォーダンス」心理学~環境に意味がある(8)ダーウィンの心理学-1
『種の起源』で知られるダーウィンは、動植物に関する緻密な観察記録も多数残している。『植物の運動力』『ランの受精』など、いずれも豊富な図版を多用し、植物は外からの生態学的な情報を受けて、動きや形を生みだしているこ...
収録日:2019/03/18
追加日:2019/08/31
アメリカで無名だったSonyがなぜ世界を席巻したのか
戦後復興~“奇跡”の真実(14)井深大、盛田昭夫とソニー
ソニー(Sony)を作り上げた井深大と盛田昭夫の半生を、3つ目の事例研究として取り上げる。自身の機械への興味から製造業へと向かい、戦時下という特殊状況下で国家への貢献を求められたという点では、2人の半生は松下幸之助や...
収録日:2019/07/23
追加日:2019/09/24
日本の戦後復興を支えた最後の起業家・本田宗一郎の奇跡
戦後復興~“奇跡”の真実(15)本田宗一郎とホンダ
日本の戦後復興を支えた最後の起業家として、ホンダ創業者の本田宗一郎氏を取り上げる。本田氏も戦前にさまざまな機械の修理や販売を請け負う中で、技術者としての能力を身につけていった。戦後の苦境の中で、戦前の経験から培...
収録日:2019/07/23
追加日:2019/09/24
ディープラーニングを取り巻く3つの動きに注目
2019年ディープラーニングの最新事情
近年、画像認識の精度が非常に上がっているディープラーニングだが、現状はどうなっているのか。「世界モデル」「AutoML」「多数パラメータの科学」といったキーワードを挙げて、ディープラーニングの最新の動向について解説する。
収録日:2019/08/28
追加日:2019/10/03
AI人材育成に向けて高専生に注目した「高専DCON」とは
日本のAI人材育成に向けた取り組み
日本のAI人材育成の課題とその解決のための取り組みについて語る松尾豊氏。ディープラーニングという新しい技術を伝達、活用するための仕組みづくりが重要だと説く。そこで注目しているのが高専生だ。2019年、ビジネスでの価値...
収録日:2019/08/28
追加日:2019/11/24
宇宙ビジネスでイノベーションを起こすには基礎科学が重要
宇宙ビジネスの現在と未来(2)基礎科学の重要性
基礎科学がおろそかにされている――。そういった危機感に背中を押され、株式会社ALE(エール)が実用化を目指す人工流れ星。そして、社長の岡島礼奈氏は「宇宙ビジネスは大きくなるしかない領域だ」という。このプロジェクトが実...
収録日:2019/09/10
追加日:2019/11/28
「トゥキュディデスの罠」で警告した状況が生まれつつある
国際秩序の変容~危機の予兆(3)中国の技術革新とトゥキュディデスの罠
中国の社会体制は、企業が政府や軍と強く結びついているため、新しい技術や情報の相互利用も容易になっている。日本は今後、こうした動きに対抗できるようなインテリジェンス機能と最新技術の活用を進めていく必要がある。(全7...
収録日:2019/09/03
追加日:2019/12/02
ファーウェイとはどんな会社?なぜ短期間で世界トップに?
中国、驚異の情報革命(3)ファーウェイ発展の歴史
強力な国家戦略があるなか、実質的に中国の情報革命を推進してきたのは、意欲的な企業の数々である。その最も顕著な例として、今回から2話に分けて「ファーウェイ」(華為技術社)を取り上げる。任正非氏がほとんど「裸一貫」と...
収録日:2019/11/11
追加日:2019/12/08
スノーデン氏によって明らかになったアメリカ諜報機関の真相
米中ハイテク覇権戦争(7)「諜報戦略」と「強国化戦略」
ここまで中国の諜報、情報収集の脅威に関するアメリカの警戒に関して議論してきたが、アメリカの諜報活動も決して明るみにできるものではないことが内部告発によって示された。自国の諜報活動を制限したくないアメリカは、直接...
収録日:2019/11/20
追加日:2020/02/22
「隠れた価値」にはお金の世界と相性が悪いものもある
経済社会と「隠れた価値」の行方(5)貨幣に代わるもの
急速に変化し続ける現代の経済システムの中で、かつて良いものとされてきたさまざまな価値は姿を消しつつある。そうした「hidden value(隠れた価値)」の問題をなんとか解決したいが、その中には市場経済になじまないものもあ...
収録日:2020/03/02
追加日:2020/05/29
MRJの失敗にみる「日本のものづくり」の問題点
失敗する日本企業の構造と改革への宿題(1)「日本のものづくり」の課題
MRJ(現・三菱スペースジェット)など、日本のものづくりにおける失敗事例を参照しながら、日本企業の構造的課題と今後の展望について解説するシリーズ講義。今までの日本のものづくりは優れた技術に支えられてきた一方で、顧客...
収録日:2020/11/18
追加日:2020/12/26
水中映像と写真や図面を照合し、沈没船を大洋丸と特定!
戦時徴用船の悲劇と大洋丸捜索(4)大洋丸の発見
浦環氏のチームの大洋丸探索は、船の図面や残された写真から得られたものと酷似した構造の沈没船を発見し、大洋丸であることを特定していった。実は、今回確認で用いられた図面は、日本ではなくドイツに所蔵されていたものであ...
収録日:2020/02/28
追加日:2021/04/17
ディープテックのシンボルとして自動運転の民主化を目指す
「自動運転の民主化」が生み出す近未来の社会(1)自動運転の民主化と大学発べンチャー
「自動運転はディープテックの一つのシンボルではないか」――ディープテックとは、それが実現されれば社会が変わるものを総称した呼び方だが、自動運転はそれぐらい大きな社会的インパクトを与えるテクノロジーだということだ。...
収録日:2020/11/25
追加日:2021/04/01
なぜ「日産リバイバルプラン」を前倒しで達成できたのか
ゴーン改革の反省とグローバル経営の教訓(2)最初のステップ
西川氏が振り返るのは、ゴーン体制の最初のステップの鮮やかさだ。個別に抱える複雑な問題を解決するために、グローバルな横軸を通し、さらに地域毎の「マネジメントコミッティ」をつくった。そして「共通の定義」による「共...
収録日:2020/11/10
追加日:2021/05/10
水はナノの世界から理解していかなければいけない命題
教養としてのナノテクノロジー(2)科学における教養とは何か<中編>
無限の可能性を秘めたナノテクノロジーは、学問体系をも再構成するほどの力を持っている。なぜなら、そこでは特定の分野を超えて物事を考えていくことが求められるからだ。その好例になるのが、「水」である。われわれにとって...
収録日:2021/03/29
追加日:2021/07/29
燃料電池車、がんの治療などで活用されるナノテクノロジー
教養としてのナノテクノロジー(5)ナノテクノロジーとは何か<後編>
国家ナノテクノロジーイニシアティブでは、ナノスケールで生じる現象やプロセスの根本的理解から社会的側面まで、7つのプログラムが構成されている。これに合わせて日本でもいろいろと動き出しているが、こうした世界的な動きの...
収録日:2021/03/29
追加日:2021/08/19
水滴にみる表面張力の分子起源とその制御について考える
教養としてのナノテクノロジー(9)水とナノテクノロジーの関係
地球を地球たらしめるもの、それが「水」である。水は他の物質と比較してもその性質は特異だ。その理由は、水の熱的性質と強力な表面張力にある。前者はナノスケールで起こる「水素結合」、後者はナノスケールでの制御である「...
収録日:2021/03/29
追加日:2021/09/16
自分を知るためのヒントは「いいな」と思う瞬間にある
生き抜くためのチカラ~為末メソッドに迫る(2)柔軟に観察する
「自分の人生はこれだ」と分かりやすく定まることはそうそうない。だから、日常の生活の中で「いいな」とか「好きだな」という小さな瞬間を集めながら、積み上げていくほうが、結局は近道なのではないだろうか。他者に委ねすぎ...
収録日:2021/06/30
追加日:2021/09/17
スタンフォード大学を中心に構築した世界最強エコシステム
シリコンバレー物語~IT巨人の実像と今後(7)政府と軍の支援とスタンフォード大学
1980年代の日本潰しにはさらなる遠因がある。1957年の「スプートニク・ショック」だ。宇宙は軍事に、ひいては産業に直結している。他国に先を越されることはアメリカにとって安全保障上の問題なのである。シリコンバレーが世界...
収録日:2021/07/08
追加日:2021/12/26
模倣からは生まれない――「すごい製品」へのジョブズ哲学
スティーブ・ジョブズの成功哲学(5)「すごい製品」のつくり方
アップルはこれまで、iPodやMac、iPhoneなど、人びとの生活を大きく変える革新的な製品を次々と生み出してきた。なぜこんなことが可能なのか。「すごい製品」をつくるためにジョブズがこだわったこと、ものづくりに対する哲学に...
収録日:2022/03/15
追加日:2022/05/21
アマゾンとグーグル創業者が疾走した世界最大・最強への道
続・シリコンバレー物語~創業者群像と課題(3)ベゾスとペイジ&ブリン
創業者群像の第3話では、アマゾンのジェフ・ベゾス氏、グーグルのラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏を紹介していく。「アマゾン・エフェクト」を及ぼして既存の小売業を消滅させるアマゾンの商法の原動力はどこにあるのか。...
収録日:2021/07/20
追加日:2022/05/24
プロティアン・キャリアの語源は変幻自在なプロテウスの神
プロティアン~最先端の自律的キャリア形成(1)変幻自在のキャリア論
人生100年時代、ただ働き続けるためだけでなく、より本人の可能性を開いていくキャリア論が登場している。40年前からよみがえった「プロティアン・キャリア」がそうで、主体的かつ変幻自在に働く方法を提唱したものだ。第1話で...
収録日:2022/03/11
追加日:2022/05/19
キャリア資本ポートフォリオで人生100年時代を心豊かにする
プロティアン~最先端の自律的キャリア形成(6)キャリア資本戦略の中長期計画
キャリア形成は一朝一夕にはならない。しかし、キャリア資本を戦略的に考えるなら、あらゆる人生経験が自己投資となり、目指すキャリアの役に立つ。ただし、それは偶然ではない。仕事とは関係のないところでキャリア資本が蓄積...
収録日:2022/03/11
追加日:2022/06/23
なぜ「知っている」だけでは「教養」とはいえないのか
「今、ここ」からの飛躍のための教養(2)日本の教養離れと知の構造化
日本で教養離れが起こった理由の一つに、いわゆる「教養人」の姿勢があった。世間から遊離して机上の空論をもて遊ぶのではなく、知を活用する人になるためには、広い興味を持って知識を集め、それを構造化する必要がある。そし...
収録日:2022/04/21
追加日:2022/06/01
イーロン・マスクは何がすごい?生い立ちと経歴
イーロン・マスクの成功哲学(1)マスクが「世界一」になるまで
2022年、フォーブス誌が発表した世界長者番付の一位となったイーロン・マスク。テスラの電気自動車やスペースXのロケット開発などを通じ、革新的なイノベーションを実現してきたことで知られるマスクは、いかにして現在のような...
収録日:2022/06/22
追加日:2022/08/23
同調圧力で何も言わない若者、議論を阻むタテ社会の壁
現代人に必要な「教養」とは?(3)ダイバーシティの場とタテ社会の問題
知識が圧倒的に不足していた時代には、いわゆる「知識人」とよばれる人が尊敬された。しかし、情報があふれ、それに誰でもたやすくアクセスできる現代では、知識の多寡は教養の有無にとって決定的な条件ではない。むしろ違う分...
収録日:2022/06/29
追加日:2022/10/14
上士幌町が「SDGs未来都市」に!逆参勤交代の可能性と課題
逆参勤交代が日本を変える(2)実証実験の好事例と実装への課題
逆参勤交代プロジェクトは今、その実証実験が北海道から九州まで全国に広がっており、なかでも北海道の上士幌町が「SDGs未来都市」に選定されるなど、好事例も生まれている。福沢諭吉の「半学半教」という言葉にもあるように、...
収録日:2022/08/29
追加日:2022/12/05
アウシュヴィッツの悲劇をAIは理解できるか…母語の有無
ChatGPT~AIと人間の未来(2)AIは意味を理解しているのか
第2話では、「AIが意味を理解しているのかどうか」を、深掘りしていく。そもそも「意味」とは何だろうか。AI研究者からは、「AIはそれなりに意味分析も行なっている」という声も挙がる。しかし西垣氏は、人間とAIとでは、言語の...
収録日:2023/03/15
追加日:2023/05/25
生命情報・社会情報・機械情報と本居宣長「もののあはれ」
ChatGPT~AIと人間の未来(8)シンギュラリティと「もののあはれ」
AIに関する議論では、シンギュラリティのような悲観論も多い。未来が暗くならないために必要なことは何か。重要なのは、アメリカ的な考え方をそのまま受け入れるのではなく、日本の伝統と文化を尊重した日本ならではのAIとの関...
収録日:2023/03/15
追加日:2023/07/06
なぜ世界の半導体不足は起きた?台湾TSMCと日本復活への鍵
半導体から見る明日の世界(1)世界的な半導体不足と日本の可能性
世界的な半導体不足によって、一時、自動車や家電製品の生産に大きな影響を及ぼした。さらに新型コロナウイルスのパンデミックとロシアのウクライナ侵攻が拍車をかけ、半導体生産の不安は全世界に広がった。今や自動車から家電...
収録日:2023/07/14
追加日:2023/08/28
半導体から解決をめざす!課題先進国・日本の進むべき道
半導体から見る明日の世界(12)課題先進国・日本の生き方
世界は今、大量生産が可能となった時代から個々の消費者ニーズに合わせた少量・高品質なものを提供する時代へと変化している。その中で半導体が担う役割はますます大きくなっているのだが、高度文明社会が進展する陰で新たな課...
収録日:2023/07/14
追加日:2023/11/13
Outlook、TeamsとAI…驚くべきアシスタント力
Microsoft Copilot~AIで仕事はどう変わるか(4)アシスタントとしてのAI
前話では、生成AIが導入されたMicrosoft 365 CopilotのうちWord、PowerPoint、Excelなどについて見てきた。この第4話では、OutlookとTeamsについて、その驚くべきサポート能力を見ていく。手紙の文章を作成したり、オンライン会...
収録日:2023/08/01
追加日:2023/10/18
世界の中心!?ケンブリッジ大学でギリシア哲学を学ぶ
哲学の役割と近代日本の挑戦(4)ケンブリッジが「世界の中心」?
日本がバブル最後の1990年代初頭、海外留学は多い時代だったが、留学先であるイギリスの情報は乏しく、通信手段は手紙とファックスだけだったという納富氏。苦労しながら交渉して落ち着いた先はロビンソンカレッジ。そのケンブ...
収録日:2023/07/28
追加日:2023/10/21
『戦略子育て』に学ぶこれからの世界で大切な「3つの力」
楽しく未来を生き抜く「戦略子育て」を学ぶ(1)「3つの力」の伸ばし方(前編)
子育てにおいて、子どものどんな力を伸ばすことを親は意識すればいいのか。三谷宏治氏によれば、発想力、決める力、生きる力の「3つの力」が重要だという。それらの力を育てるには、子どもが失敗をしたときの親の接し方が大事に...
収録日:2023/10/06
追加日:2024/02/21
「バカげたアイデア」が成功する!? カギは不満と情熱と改善
サム・アルトマンの成功哲学とOpenAI秘話(5)スタートアップ成功の秘訣:前編
Yコンビネーターで経験を重ね、紆余曲折を経てOpenAIの事業を成功させたサム・アルトマン。彼のように、革新的で、多くのユーザーに愛されるサービスを生み出すためには、どのようなマインドセットが必要なのだろうか。「素晴ら...
収録日:2024/03/13
追加日:2024/05/17
縮小均衡の悪循環とおひとり様の世界…いま攻めの経営を!
グローバル環境の変化と日本の課題(3)日本経済30年間の悪循環
「失われた30年」といわれている日本経済だが、実は2001年頃にわずかだが経済成長しており、悪循環から脱却するチャンスはあったのだ。ではなぜそうならなかったのか。日本経済衰退の要因とともに、非正規雇用の定着と出生率の...
収録日:2025/01/17
追加日:2025/03/18
世界は音楽と数学であふれている…歴史が物語る密接な関係
数学と音楽の不思議な関係(1)だれもがみんな数学者で音楽家
数学も音楽も生きていることそのもの。そこに正解はなく、だれもがみんな数学者で音楽家である。これが中島さち子氏の持論だが、この考え方には古代ギリシア以来、西洋で発達したリベラルアーツが投影されている。この信念に基...
収録日:2025/04/16
追加日:2025/08/28
世界で最もクリエイティブな国は? STEAM教育が広がる理由
数学と音楽の不思議な関係(4)STEAM教育でつくる喜びを全ての人に
世界では「創造性がどれくらい大事か」という問題意識が今、急激に高まっている。創造性とは全ての人にあり、偏差値などでは絶対に計れない、まさに無限軸の創造性のこと。そうした創造性を育む学びが「STEAM教育」である。最終...
収録日:2025/04/16
追加日:2025/09/18
コスパが鍵!? 顧客満足につながる品質マネジメントとは
プロジェクトマネジメントの基本(2)プロジェクトの複雑性とマネジメント
「プロジェクトはとても複雑だ」「不確実である」といわれるが、それはなぜか。イノベーションとエンジニアリング、モジュールとインテグラル、オープンとクローズドという対立項をかけ合わせてプロジェクトが成立するからだ。...
収録日:2025/09/10
追加日:2025/12/04