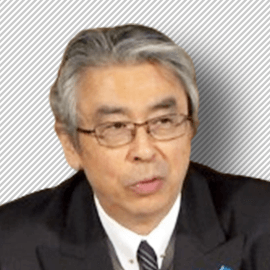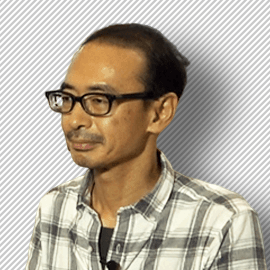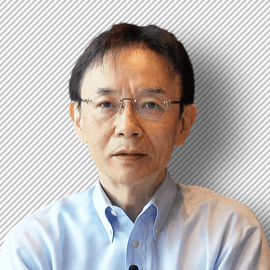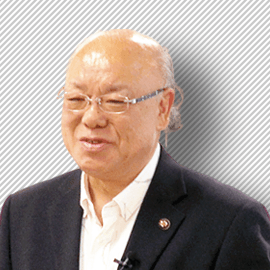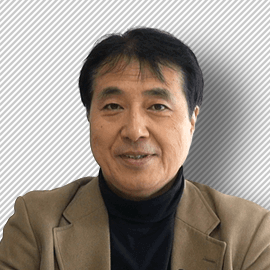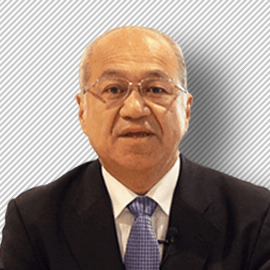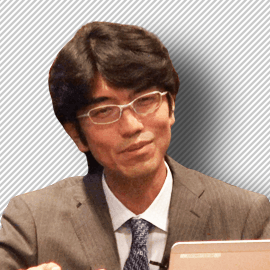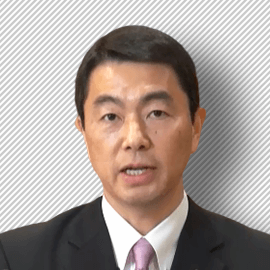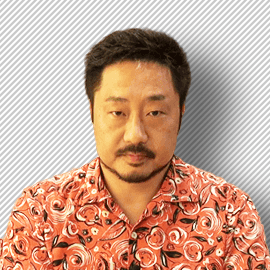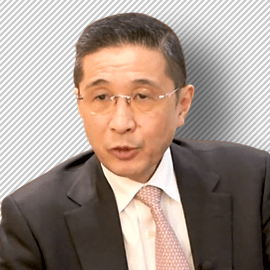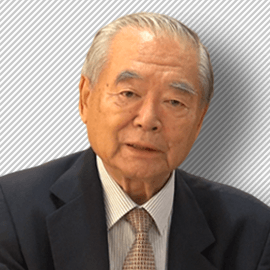日本が必要なのは「軽武装・経済優先主義」からの大転換
グローバル・サウスは世界をどう変えるか(8)日本の新しい平和戦略
日本は戦後70年以上、日米安保の下で経済活動だけに注力してきた。そして1人当たりのGDPではアメリカと肩を並べるほどに急成長したものの、この「軽武装・経済優先主義」の代償として国民の安全保障への意識低下を招いた。だが...
収録日:2024/02/14
追加日:2024/05/22
8世紀を代表する知識人・山上憶良が感じたグローバリズム
山上憶良「好去好来の歌」を読む(1)山上憶良に学ぶ国際感覚
万葉歌人として名高い山上憶良は8世紀当時、阿倍仲麻呂と肩を並べる国際的な知識人だった。豊富な知識や見識を支えたのは遣唐使としての経験であり、彼のもとに教えを乞いに訪れる遣唐大使もいた。今回のシリーズでは、グローバ...
収録日:2024/04/02
追加日:2024/05/19
世界の紛争…アメリカの空母機動部隊は3正面で戦えるのか
「同盟の真髄」と日米関係の行方(1)日本を占う3つの選挙と軍事作戦
2024年は日本にとって重要な選挙が3つある。それは1月に行われた台湾総統選、4月の韓国総選挙、そして11月のアメリカ大統領選である。これらの選挙結果は、ロシア・ウクライナの戦争や、ガザ地区での紛争が収束の気配を見せない...
収録日:2024/04/23
追加日:2024/06/12
20億人以上が肥満…飽食の時代に大事な「選食力」3カ条
飽食時代の「選食」のススメ(1)選食の提唱と「食の多様性」
世界の肥満者数が増加の一途をたどり、偏食や低栄養などの問題も叫ばれている昨今。そんな飽食の時代に対応するための食への態度として堀江氏が提唱するのが、食事の質と量を見極める「選食」である。では選食とはいったいどの...
収録日:2023/05/23
追加日:2023/08/24
多くの認知症の原因は「脳のゴミ」の蓄積
認知症とは何か(1)疾患の種類と対応
認知症は高齢化に伴ってますます増加しており、今後は「当たり前の病気」となる。国立研究開発法人国立長寿医療研究センター長寿医療研修センター長の遠藤英俊氏によれば、認知症に対する偏見をなくし、正しい知識を身に付ける...
収録日:2018/05/26
追加日:2018/09/01
最初の日本列島人はいつ、どうやって日本に渡ってきたのか
最初の日本列島人~3万年前の航海(1)日本への移住 3つのルート
人類はアフリカにいたホモサピエンスが世界に拡散し、その一部が日本に渡ってきたとされている。では、いつ頃どんなルートをたどってきたのか。この大いなる謎解きに挑んだのが海部陽介氏だ。海部氏は、日本にホモサピエンスが...
収録日:2019/08/29
追加日:2019/10/01
小さな不幸と大きな安定をバランスする社会のあり方とは
価値と人間(8)小さな不幸と大きな安定
「国家は消滅しなければならない」とレーニンが『国家と革命』で述べた。本当にいい社会とは、国家のない社会なのだろうか。一方、日本の大問題は少子高齢化だが、国民が少なくても成り立つ社会を築けば問題は解決する。つまり...
収録日:2024/01/31
追加日:2024/05/17
80歳まで現役へ、磨くべき「5つの変身資産」とは何か
人生100年時代の「ライフシフト概論」(8)変身資産を磨く
今後80歳まで自分のありたい姿を描き、それに向けて「変身資産」を磨く。そのために必要な要素として「マインド」「知恵」「仲間」「評判」「健康」の5つを挙げることができる。ではこれらはそれぞれなぜ重要で、どのようにすれ...
収録日:2022/06/15
追加日:2022/10/29
フラッシュメモリの歴史は「非常識なアイデア」から
世界を変えた「フラッシュメモリ」(2)誕生秘話・発明編
フラッシュメモリは、意外にも「性能を悪く」して生まれたものだった。当時の業界からすれば、あまりに“非常識”な発想で、受けいれられるものではなかった。しかし、その発想をきっかけに、メモリ業界に革命を起こしていくこと...
収録日:2018/10/19
追加日:2019/01/04
ルネサンスはどうやって始まった?…美術の時代背景
ルネサンス美術の見方(1)ルネサンス美術とは何か
ルネサンス美術とはいったい何なのか。これを考えるためには、なぜその時代に古代ギリシャ、ローマの文化が復活しなければならなかったのかを考える必要がある。その鍵は、ルネサンス以前のイタリアの分裂した都市国家の状態や...
収録日:2019/09/06
追加日:2019/10/31
日本経済の強靭性を高めるタイミングは今…必要な戦略は?
世界経済の見方とIMFの役割(6)これからの世界経済と日本経済への視座
パンデミックに始まり、金融のタイト化、大幅な金融緩和、地政学的リスクの増大と、わずかの期間に世界経済は激しい波に晒されている。デフレ懸念がインフレ懸念に逆転すると、その圧力はさらに強まっている。また、ウクライナ...
収録日:2023/01/11
追加日:2023/03/09
日本美術の特徴を示す矛盾した2つの要素とは?
日本美術論~境界の不在、枠の存在(1)具象と抽象の共存
東京大学大学院人文社会系研究科教授の佐藤康宏氏が、日本美術の特質について、美術史の知識を補足しながら解説する。ヨーロッパや中国では、具象的なものと抽象的なものが区別される傾向にあるが、日本美術にはそうした区別は...
収録日:2017/08/02
追加日:2018/02/08
睡眠障害がからだと脳に与える影響
睡眠:体、脳、こころの接点(3)睡眠不足と病気のリスク
睡眠不足が昼間のパフォーマンスに影響するのは、誰もが経験することだが、脳科学により、そのメカニズムが解明されつつある。シリーズ第3話では、睡眠の国際比較や長時間労働との関係を通じて、睡眠不足による病気のリスクを考...
収録日:2018/08/24
追加日:2019/01/19
たたき上げの英雄である劉備と優れた外交力持つ諸葛亮
「三国志」の世界とその魅力(5)漢室復興
現在の中国には、「三義廟」「三顧堂」「成都武侯祠」と、劉備や諸葛亮にまつわる歴史遺跡が多く残されている。真偽はともあれ、『三国志演義』によって、いかに劉備・関羽・張飛が愛され、諸葛亮が慕われているかを示すものだ...
収録日:2017/11/10
追加日:2018/03/01
サラリーマンも「SDGs」を――持続可能な暮らしとは
会社人生「50代の壁」(2)「上手に下る」ための方法
「50代の壁を乗り越える」「50代の坂を上手に下る」ためにはどうすればいいか。漠然と不安を抱えるのではなく、具体的に一つ一つ挙げ、それと向き合うことが大切だと語る江上剛氏。さらに、国連が提唱している「SDGs」をサラリ...
収録日:2021/08/31
追加日:2021/11/16
「天下再興」に向けた足利義昭の呼びかけに応じた織田信長
天下人・織田信長の実像に迫る(2)足利幕府と天下再興
戦国時代の足利将軍は無力だったといわれるが、足利氏は京都周辺を治め、朝廷や寺社の庇護に努める「天下人」の役割を担い続けていた。しかし、連立を組んでいた三好氏による13代将軍義輝の殺害によって、天下は乱れることにな...
収録日:2020/03/17
追加日:2020/07/06
上士幌町が「SDGs未来都市」に!逆参勤交代の可能性と課題
逆参勤交代が日本を変える(2)実証実験の好事例と実装への課題
逆参勤交代プロジェクトは今、その実証実験が北海道から九州まで全国に広がっており、なかでも北海道の上士幌町が「SDGs未来都市」に選定されるなど、好事例も生まれている。福沢諭吉の「半学半教」という言葉にもあるように、...
収録日:2022/08/29
追加日:2022/12/05
原発攻撃の被害範囲と対策…使用済燃料の乾式貯蔵が急務
原子力発電の戦争リスク(2)ウクライナ原発の被害状況と日本の対策
実際に原子力発電所が攻撃を受けると、どのような被害が発生するのか。ロシア・ウクライナ戦争の事例をもとに具体的なリスクの内容を解説しながら、原子力発電所の構造的な問題点を指摘する。また、原子炉本体だけでなく、その...
収録日:2022/10/18
追加日:2022/11/25
水が使えるかは雨量ではなくインフラの整備で決まる
水ビジネスの動向(1)水不足は本当か
人はなぜ水が足りないような場所にわざわざ住むのか。「水不足=乾燥している」は正しいのか。食べ物を通じて、日本はどの程度の水を海外から買っているのか。あまりにも身近で、それでいて多くの謎を持つ水をめぐる知の最前線...
収録日:2015/05/25
追加日:2016/05/05
本能寺の変直前の派閥の「三層構造」
織田信長と足利義昭~検証・本能寺の変(8)結び~中世と近世の相克~
「事件史」や「人物史」として語られることが多かった本能寺の変だが、それでは本質的な見方にならないことをこれまで7回に分けて伝えてきた。これは織田政権の持っていた矛盾が臨界点に達して爆発したものである。織田政権の本...
収録日:2018/10/29
追加日:2019/03/22
論理に勝るのは空気?知っておくべき日本の特殊性
TOTOの北九州発グローバル戦略(2)実は海外でも稼ぐTOTOの「けじめ」
日本社会をコントロールしているのは、法律でも人でもない。では何か? 日本企業が海外へ進出するときに知っておくべき「日本の特殊性」とは? 実は海外でも稼いでいるTOTO株式会社の北九州発グローバル戦略。その根底に...
収録日:2014/09/18
追加日:2015/01/20
働き方改革4つのポイント!重要なのは管理職の意識改革
経営戦略としての働き方改革(3)企業事例にみる改革成果
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長・小室淑恵氏が、「働き方改革」のためのマネジメント手法とチームでの具体的な取り組み方、そしてそれを実践した企業事例を紹介する。小室氏は、その事例から多くの企業が抱える...
収録日:2017/02/21
追加日:2017/03/27
強まるアンチ・グローバリズムの動きをどう見ればいいか
アンチ・グローバリズムの行方を読む(1)世界情勢の転換
グローバリズムとそれへの対抗(アンチ・グローバリズム)の関係をどのように考えれば良いのか。グローバリズムは、格差の拡大、既成権益の毀損、製造業の没落などを引き起こし、バックラッシュを浴びている。その中で米中など...
収録日:2019/11/07
追加日:2019/11/30
「健幸ポイント」制度導入によるブレイクスルー
スマートウエルネスみつけの実現へ(3)健幸ポイント制度
見附市では、スマートウエルネスシティ事業を進めるため、自治体レベルで研究組織が立ち上げられた。その組織は健康施策とそのための都市政策の一環としてつくられたのだが、具体的にどのような研究が進められているのか。そこ...
収録日:2018/07/04
追加日:2018/12/24
世界の発電トレンドは「自然エネルギー100%」
加速する自然エネルギーの拡大(1)世界的構造変化の背景
エネルギー分野において世界的な構造変化が起こっている今、私たち日本の消費者は、新エネルギー時代にどう向かっていくべきなのか? 認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所所長・飯田哲也氏が、世界中で急速に普及しつつあ...
収録日:2015/12/25
追加日:2016/03/21
組織改革は最初に全体像と将来像を示すのが重要
組織改革の要諦~活性化と人材活用(1)準備、スピード、タイミング
人口減少社会や激化する国際競争の中でますます重要になっていく、組織改革の要諦とは何か。会社を成長させ、社員に能力を発揮させるための要素を、事業再生に長く携わってきたボストン・コンサルティング・グループ シニアパー...
収録日:2018/03/12
追加日:2018/05/31
生活の糧を得るだけではない「働くこと」の意味
労働基準法の精神(6)働く人にとって必要な5つの橋
日本労働組合総連合会(連合)第6代会長の古賀伸明氏が労働法について解説する、シリーズレクチャー最終話。「働く」とは生活の糧を得る手段だけでなく、人間らしい社会的営みを意味する。その営みを健全に維持していくためには...
収録日:2018/06/25
追加日:2018/09/25
再生可能エネルギーによる新しい産業の創出
地方銀行が取り組む地域資源を活用した地方創生
山積する地域課題を乗り越えていくためには、地域資源を生かした産学官金連携でなされる新産業の展開が有効であると、株式会社北都銀行取締役頭取の斉藤永吉氏は指摘する。これを実現した北都銀行の経営戦略とはいかなるものだ...
収録日:2018/09/11
追加日:2018/12/27
海底で働く自律型海中ロボットの作業をスライド解説!
自律型海中ロボットは何を目指すか(3)海に眠る鉱物資源
近年、日本周辺には海底鉱物資源が豊富にあることが分かってきた。海中ロボットの研究を進める九州工業大学社会ロボット具現化センター長・浦環氏は、日本は地の利を生かして新技術開発を率先して行うべきだ、と主張する。ハー...
収録日:2016/01/12
追加日:2016/07/13
食文化の研究には様々な分野を総合した食科学が必要
食科学の扉を開く~立命館大学食マネジメント学部の試み~
現在われわれが直面している食の問題は、従来の価値観や知識では解決できない、人類的・社会的課題となっている。この問題に取り組むためには、社会科学・人文科学・自然科学全ての視座が必要である。立命館大学食マネジメント...
収録日:2018/04/27
追加日:2018/09/26
外国人への飲食サービス…食文化の違いにどう対応する?
飲食サービスと異文化対応
近年、宗教的禁忌に対応した特別食が注目を集めているが、立命館大学食マネジメント学部教授の阿良田麻里子氏によれば、食の異文化対応にあたっては、宗教的禁忌だけでなく食べ物に対する認識や嗜好など多様な要素を視野に入れ...
収録日:2018/04/27
追加日:2018/09/26
スローフード運動とは?…イタリア発の歴史と新たな展開
スローフード思想と新しいガストロノミー
スローフード思想は、ファストフードに代表されるモダニズム的価値観への対抗として誕生した。その活動は、地域の伝統的な食や持続可能な食の在り方の保存として展開され、近年「新しいガストロノミー」という考え方に行き着い...
収録日:2018/04/26
追加日:2018/09/27
戦国時代とは何か?意外と知らない戦国大名と国衆の関係
戦国大名の外交、その舞台裏(1)戦国大名という地域国家
戦国時代とは、主たる政権が不明確で、多数の戦国大名によって分裂した地域国家の時代である。そこにおいて重要だったのは、それぞれの戦国大名に服属していた国衆の存在である。この国衆の動向は戦国大名同士の「外交」にどの...
収録日:2019/06/13
追加日:2020/01/21
不思議なことに人類の歴史は千年ごとに大変化を見せている
三つの千年紀から見た世界の変遷
国家百年の計というが、人類史には千年ごとの変化があると、高橋一生氏は言う。普段は使わない長大なスコープを通して見ると、人類と世界の課題も、将来への展望も、手に取るように見えてくる。いざ、三つの「千年紀」が語る世...
収録日:2014/10/28
追加日:2015/02/04
負けない体制をつくり、戦わない―不戦不敗
安全保障のチャイナリスク対応(4)日本が生き残る道
米中という大国のパワーシフトの下で、日本が生き残るための戦略はどのように立案すればよいのだろうか。前海上自衛隊佐世保地方総監・吉田正紀氏が、いま大きな転換点を迎えるわが国の安全保障システムを再点検しつつ、シミュ...
収録日:2014/12/01
追加日:2015/07/06
戦争、独裁、マイノリティを題材に人権保護の活動を行う
ヒューマン・ライツ・ウォッチ(1)活動の3つの柱
「人権保護の世界では、日本の力、特に日本政府や日本企業の力が求められている」と、国際人権NGO「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」日本代表の土井香苗氏は話す。なぜ日本の力が必要なのか。土井氏が日本と世界の人権保護の...
収録日:2016/03/03
追加日:2016/06/09
浜松市の提唱で「外国人集住都市会議」が2001年に設立!
浜松市の多文化共生の取り組み(4)外国人集住都市会議
外国人が多く住む地域同士の横の連帯をつくっているのが、浜松市の提唱で2001年に発足した「外国人集住都市会議」だ。浜松市長・鈴木康友氏は、この会議が多文化共生のための情報交換やノウハウの共有の場となり、同時に基礎自...
収録日:2016/11/17
追加日:2017/01/22
福島第一原発事故の比較制度分析で見えてくるものとは?
比較制度分析とは何か(5)原発事故の分析
福島第一原発事故の対応は、なぜ意思決定が遅れたのか。青木昌彦教授は、組織アーキテクチャにおける集団認知に着目し、原発事故の比較制度分析を行ってきた。慶應義塾大学商学部教授の谷口和弘氏が、現実に対してさまざまなイ...
収録日:2017/11/02
追加日:2018/02/01
大航海時代の「コロンブスの交換」が食文化に与えた影響
「食」から世界史を考える
世界における現在の食文化は、「コロンブスの交換」の影響を大きく受けているという。「コロンブスの交換」は大航海時代に起こった事象を指すが、そこからどのようなことが世界中に広まっていったのか。立命館大学食マネジメン...
収録日:2018/04/26
追加日:2018/10/07
「津波てんでんこ」の深い意味は家族の絆と信頼
釜石の子どもたちにみる防災教育(3)「津波てんでんこ」
釜石での防災教育として子どもたちに行ったのは、津波の記念碑のところに連れていき、先人の気持ちに想いを馳せることだった。東北地方には「津波てんでんこ」という言葉がある。そこには悲しい過去の繰り返しから生まれた災害...
収録日:2019/03/30
追加日:2019/06/01
県民が自分の力を使い自分の足で立っていける県土をつくる
創造的復興 ~震災から3年、民間活力とリスク予想に基づく宮城の挑戦~
マグニチュード9.0の大地震と津波の直撃を受けた宮城県では、3年目の現在、県土の創造的復興に向けた抜本的なチャレンジが始動している。税金を使い旧態へと戻す復旧には何が足りないのか?村井知事が復興の現場から熱く語る。
収録日:2014/02/14
追加日:2014/02/24
日米は21世紀の世界ルールを守る上で重要なパートナー
日米同盟の必要性~アメリカにとって日本は死活的に必要な同盟国~
今後の日米同盟は、果たしてどうすべきなのか。第二次世界大戦を反省し、日本の地理上の位置や日米の社会価値基盤などを踏まえて、JR東海の葛西敬之名誉会長が、日米関係の将来を提案する。
収録日:2014/04/15
追加日:2015/04/23
中国ビジネス負け組企業の典型例は、社長が中国に行かない
中国ビジネス成功のカギ(2)社長の決断力
中国ビジネスにおける日本企業が勝ち組と負け組に二極分化している状況が分かった。今回は多くの事例を見てきたキヤノングローバル戦略研究所研究主幹・瀬口清之氏が「負け」の理由を詳しく分析。その根本原因を探ることから、...
収録日:2015/01/05
追加日:2015/03/27
財務的な継続可能性と社会的なインパクトの両立を目指す
社会的インパクト投資~社会課題を解決する(1)社会課題の解決を追求する投資
「社会的インパクト投資」をご存じだろうか。イギリス、アメリカなどでいま盛んに行われている新たな形の投資である。一体どのようなものなのか。日本ではどの程度進んでいるのか。日本財団社会的投資推進室室長・工藤七子氏が...
収録日:2016/03/18
追加日:2016/05/02
テロに対する過剰反応こそがテロリストの成功例となる
テロ対策の理論と実際(1)テロとは何か
2020年東京オリンピックに向けて、本格的なテロ対策が求められている。しかしテロとはどのようなもので、その真の脅威はどこにあるのか。防衛省防衛研究所防衛政策研究室主任研究官の片山善雄氏は、テロに対する過剰反応こそテ...
収録日:2017/12/08
追加日:2018/02/21
元旦は9月、1年は13か月―エチオピアの複雑な暦
映像で考えるエチオピア(4) エチオピア暦とティムカット
多様な文化を持つエチオピアでは、暦も独特だ。長い歴史を持つエチオピア暦はグレゴリオ暦と異なり、新年は9月に始まる。また、13の月があり、ユニークな祝日も多くある。エチオピアの代表的なお祭り「ティムカット」の映像を観...
収録日:2018/07/13
追加日:2018/12/10
電気自動車の世界的競争で勝ち残るポイントとは?
電気自動車で、自動車業界の激変は起きるのか
これから、自動車業界にとってのゲームチェンジのメガトレンドとなりうるのが電気自動車である。日産は電気自動車に力を入れてきたが、その日産を率いてきた西川氏の眼に、今後の電気自動車への動きは、どのように映っているの...
収録日:2020/11/10
追加日:2021/07/05
今起こっている国際秩序の変容は「危機の20年」の再来か
国際秩序の変容~危機の予兆(1)「危機の20年」の再来か
今、国際秩序は変容の時代に入っている。第二次世界大戦の反省から、戦後「復讐のサイクル」をつくらないための国際的な信頼関係と和解が築き上げられてきた。しかし2010年代に入ってから、以前の信頼関係を切り崩す戦略を取る...
収録日:2019/09/03
追加日:2019/11/18
沖縄米軍基地移設「最低でも県外」とは何だったのか?
沖縄問題を考える(3)名護市長との議論と鳩山首相の発言
基地移転の問題について、名護市長と島田晴雄氏はどのような議論を交わしたのか。また民主党政権時代、鳩山首相の発言によって沖縄県民がどれほど怒りを覚えたのか。当時の様子を振り返りながら詳しく状況を語る。(全6話中3話目)
収録日:2013/12/25
追加日:2014/02/24
「中東」とは何か?~3つの手がかりから深める理解
中東を理解するために
2011年の「アラブの春」以後、いまだに厳しい内戦やテロが続く中東情勢だが、そもそも「中東とは何か」「イスラムとは何か」など複雑で分からないという声も多い。中東秩序の変化と歴史的背景、そして西洋大国やロシアとの関係...
収録日:2014/02/05
追加日:2014/02/24
スズキ自動車社長に教わった「中小企業のおやじ」の心構え
県知事として大切にしていること-「自分が前に出ていく」
東日本大震災で甚大な被害をこうむった宮城県は、村井知事のもと驚くべきスピードで復興計画を立て、着実にそれを実行に移している。「ピンチをチャンスへ」との決意のもと、宮城県を復興へと導く村井知事の信条とは?
収録日:2014/02/14
追加日:2014/03/13
「戦後レジームからの脱却」は外国人からすると意味不明
いまアメリカが日本に問う(2)誤解を招きがちな首相の表現・言葉
安倍首相の外交政策を「実利的かつ現実的」と評するカーティス氏。しかし、それでも疑問視されているのは、安倍首相の表現・言語が誤解を招きがちだからだと指摘する。その具体例の解説を通じ、安倍首相が今後どうすべきである...
収録日:2014/03/17
追加日:2014/03/17
ドバイやシンガポールに見る日本の経済成長の余地
日本経済の成長の本当の可能性はどこにどれほどあるのか
今後の日本経済の成長可能性を否定する論者は、高度成長期と対比して人口減少や高齢化を指摘する。だが、果たしてそれらは本当に経済成長を阻む要因なのだろうか?われわれが「失われた20年」で本当に失ってしまったものと、...
収録日:2014/01/14
追加日:2014/03/20
田辺朔郎―北垣国道と土木事業の前線を担った「水運の父」
技術と民生から見た明治維新(5)田辺朔郎
本編シリーズ講話第5回は、北垣国道とともに京都や北海道で数々の土木事業に取り組んだ田辺朔郎。その仕事に見る明治の先人たちの発想の豊かさ、教養とセンス、志の深さに触れつつ、現代日本の繁栄がこの努力に根差しているこ...
収録日:2014/02/26
追加日:2014/03/27
シンガポールはなぜ驚異的な経済発展を遂げたのか?
シンガポールの謎~驚異的な経済発展の秘密(1)植民地時代から分離独立までの歴史
一人当たり国民所得ではすでに日本を抜き去り、驚異的な経済発展を遂げたシンガポール。淡路島ほどの国土で、資源もない東南アジアの小国が、なぜ急成長できたのか。シンガポールの歴史的経緯を辿りながら、その訳に迫っていき...
収録日:2013/10/03
追加日:2014/04/03
大使召還事件はGCCに新たな枠組みをもたらす
中東・湾岸情勢(2)新しい戦略的互恵と提携の時代へ
中東・湾岸の諸国間関係が大きく揺れている。長らく伏流していたズレが「アラブの春」を契機に表出しはじめ、米国の方針転換により噴出した。サウジアラビアを中心とした湾岸協力会議(GCC)は、アメリカ、ロシアを含む世界...
収録日:2014/04/23
追加日:2014/05/22
「ユニエイト」というあり方がウクライナの民族文化を醸成
ウクライナの宗教と民族の歴史(2)ギリシア・カトリック信仰と民族文化
ウクライナ語を話す西ウクライナ地方の住人には、独特なギリシア・カトリック(ユニエイト教会)信仰が深い。対立と弾圧を余儀なくされた彼らの間には「教会に対する戦いは、文化に対する戦いだ」との言い回しがある。その手掛...
収録日:2014/05/22
追加日:2014/06/05
複雑なウクライナの宗教と民族との関係
ウクライナの宗教と民族の歴史(1)四大宗派併存の歴史と背景
国際的関心の集まるウクライナ情勢だが、ウクライナを理解するにはこの地方特有の複雑な宗教と民族の関係を知らなければならない。ロシアとウクライナ、西部と東部、ローマカトリックとギリシア正教、といった二項対立のみでは...
収録日:2014/05/22
追加日:2014/06/05
クビチェック大統領が築いた「ブラジリア」は人類史的偉業
ブラジルの繁栄と転落(1)ブラジリアと軍政時代
BRICsのトップと言われたブラジルが低迷段階に入ったと言われている。しかし、ブラジルには復元力があると語る島田晴雄氏。繁栄と転落の歴史の中で、ブラジル経済がいかに復活を遂げていったのか。シリーズ前編となる今回...
収録日:2014/04/10
追加日:2014/06/12
イスラム教スンニ派とシーア派の違いとは?
イスラム教におけるシーア派とスンニ派の違い
世界三大宗教の一つであるイスラム教は、シーア派、スンニ派の二派に大別されるが、その二派の最も特徴的な違いは何なのか? 何を発端としてその違いは生じたのか? イスラム地域研究の第一人者である山内昌之氏が解説する、...
収録日:2014/05/22
追加日:2014/06/12
ブラジル的楽観性をもって将来を展望せよ!
日本とブラジルの将来に向けて~何を学び合えるか?
歴史的に深い関係を築いてきた日本とブラジル。日本がブラジルに提供できるものが多々あるのはもちろんだが、ブラジルから日本が学べるものもまた、決して少なくない。双方何を学び合い、教え合い、そして手を取り合って何を世...
収録日:2014/04/10
追加日:2014/06/19
課題の多さを可能性と見る人が大勢いればすぐに変革できる
LINE流イノベーティブ思考術(5)常に変化し続ける
成功に絶対のセオリーはない。しかし変化・革新には不可欠なものがある。日本企業が海外に進出するとき、また新しい価値を生み出し世の中を変えていくときに必要な力とは。LINE株式会社代表取締役社長CEO森川亮氏のポジ...
収録日:2014/05/14
追加日:2014/06/26
先送りされてきた最たるものが「社会保障と税の一体改革」
社会保障と税の一体改革(1)時代の変化と法案作成理由
野田佳彦前総理が推し進めた「社会保障と税の一体改革」は、アベノミクスのベースとなり、4月の消費税アップへとつながっていった。なぜ野田政権は当時、消費税増税というリスクある政策を掲げたのか。「社会保障と税の一体改...
収録日:2014/06/07
追加日:2014/07/03
東京-名古屋間を40分で結ぶ夢の超高速鉄道
東海道新幹線50周年と海外展開(2)21世紀の新たな飛躍 超電導リニア(SCMAGLEV)
東京-名古屋間を40分で結ぶ超電導リニア(SCMAGLEV)。21世紀の新・鉄道革命として50年以上にわたり開発を進めてきた。その技術の強み、開発経緯、海外展開、社会的インパクトとは。JR東海の葛西敬之名誉会長が...
収録日:2014/04/15
追加日:2014/07/03
「衝突回避の原則」は従来の常識を覆す鉄道革命!
東海道新幹線50周年と海外展開(1)日本型高速鉄道システムを世界標準へ
安全性と効率性をきわめて高い水準で両立した日本の高速鉄道には、それを支える日本独自の概念と技術があった。その革命性と国際化に向けた将来展望を、JR東海の葛西敬之名誉会長が語る。(前編)
収録日:2014/04/15
追加日:2014/07/03
六日戦争で聖地「嘆きの壁」を回復したユダヤ民族
近代イスラエルの誕生:その苦闘の背景(2)
近代イスラエル史の後編では、建国以後の状況に触れる。欧州列強に翻弄されたユダヤ人がイスラエルを建国したのは1948年5月14日。しかし、国をつくればそれで安泰というわけではない。納得しない周辺諸国との度重なる紛...
収録日:2013/10/04
追加日:2014/07/24
なぜ土砂崩れが頻発するのか?林業先進国と日本の違い
プラチナ社会における林業
国土の65パーセントが森で覆われている森林国日本。しかし、その林業の生産性は世界の林業先進国に大きな後れを取っている。「プラチナ構想」に基づく21世紀スマート林業の創生に向けた林業活性化の意味と三つの鍵を小宮...
収録日:2014/06/19
追加日:2014/07/25
カテゴリーキラーを殺すAmazonの流通革命
Amazonが促す流通革命
夜ネットで注文した本が、翌朝には自宅に届く時代。現在のこの「流通革命」を先導するのがAmazon(アマゾン)である。インターネットと物流の激変、それらを支える情報化の急進とは? 流通業の「今」を伊藤元重氏が解き...
収録日:2014/06/16
追加日:2014/08/01
古代イスラエルの歴史…メサイア信仰とユダヤ人の離散
イスラエルの歴史、民族の離散と迫害(1)前編
近代イスラエル史に続き、古代イスラエルの歴史を年代を追ってさらにひもとき、ユダヤ民族離散と迫害の歴史を島田晴雄氏が解説。イスラエル建国の意味を考え、イスラエルの今を知るために必見の歴史講義の前編。(全5話中第4...
収録日:2013/10/04
追加日:2014/08/01
トルコ大統領選とISによるイスラーム国家の樹立
トルコ大統領選とISIL
10MTVではおなじみの歴史学者・山内昌之氏が、2014年6月22日から7月5日のトルコ研究調査から戻られた。クリミア半島と中東。今最も激震する両地域に挟まれているのが、トルコ共和国である。現地の報道機関や市民...
収録日:2014/07/17
追加日:2014/08/08
「歩こうアメリカ、語ろうニッポン」プロジェクトとは?
『歩こうアメリカ、語ろうニッポン』レポート(1)プロジェクトの経緯と背景
『歩こうアメリカ、語ろうニッポン』は、首相官邸でこの春急きょ企画、始動したプロジェクトである。果たして、このプロジェクトにはどんな意図があって、どのように進められたのか。その経緯と背景について島田晴雄氏が語る「...
収録日:2014/06/24
追加日:2014/08/14
くまモンがもたらした経済的豊かさ・誇り・安全安心・夢
蒲島県政(3)目標の政治とくまモンの政治経済学
蒲島県政が目指す「目標の政治」を一言で表現すれば「県民総幸福量の最大化」だ。その施策の核となっているのが、熊本県営業部長・くまモンだが、そこには単なるキャラクターを超え、政策としてとらえたくまモンの姿があった!...
収録日:2014/05/16
追加日:2014/08/21
メンバーシップを発揮させる仕組みの地方導入は有効?
カントリークラブの発想
英米のカントリークラブの発想、あるいは自律分散協調型システム、クラウドコンピューティングの構造が、日本の地方自治・地方分権を組み立て直す際の参考になるだろうと曽根泰教氏は言う。その真意を説く。
収録日:2014/05/28
追加日:2014/08/21
日本への関心は低いが、「トヨタには世話になっている」
『歩こうアメリカ、語ろうニッポン』レポート(2)ケンタッキー篇-1 アメリカのハートをつかんだ日本企業の姿
島田晴雄氏一行がまず向かった先は、ケンタッキー。この草深い町で、「日本」はどのような印象を持たれているのだろうか? そこには、控えめに努力し続け、ケンタッキーの人々のハートをつかんできた日本企業の姿があった。『...
収録日:2014/06/24
追加日:2014/08/21
クオリティを求める社会を実現する全国規模の連携組織
プラチナ構想ネットワークとは?
量的に豊かな時代を迎えた21世紀、次に目指すべきは「プラチナ社会」であると語る小宮山宏氏。果たして、「プラチナ社会」とはどんな社会なのか。そして、その社会を作っていくための「プラチナ構想ネットワーク」とは。
収録日:2014/06/19
追加日:2014/08/21
ガザ地区のイスラエルとハマスの対立を3つの次元で考える
ガザ地区におけるイスラエルとパレスチナの対立(1)三つの次元の変化
多くの犠牲者を出して、今なお、戦火の絶えないパレスチナ・ガザ地区。イスラエルとパレスチナの問題は、なぜ根本的解決に至らないのか? 歴史学者・山内昌之氏が三つの次元でこの問題の深層に迫る。
収録日:2014/07/30
追加日:2014/09/04
ガザを統治するハマスはなぜ妥協なき戦いを続けるのか?
ガザ地区におけるイスラエルとパレスチナの対立(2)イスラエルの軍事作戦とハマスの政治的戦術
ガザ地区ではなぜ、恒久的平和はおろかしばしの停戦状態さえ維持できないのか? そこにはイスラエルの報復的軍事行為もさることながら、イスラエルとの交戦を高次の政治的意図をもって捉えるハマスの発想が大きく影響している...
収録日:2014/07/30
追加日:2014/09/08
ISの戦闘と第3次ガザ戦争では歴史的な意味合いが違う
ガザの悲劇、その反復の理由―新しい三つの変化
ハマスとイスラエルによる第3次ガザ戦争が続いている。しかし、この戦争がイスラエル南部国境の恒久的な安全保障の確立に成功するとは思えないと語る山内昌之氏。それは、イスラエルとパレスチナとの争いに新しい三つの変化が...
収録日:2014/08/20
追加日:2014/09/12
アベノミクスの課題、重要なポイント
アベノミクスの中間総括
2012年12月の安倍政権発足以来、20カ月を経過し、内閣改造も経た今、これまでのアベノミクスを総括する動きが各所で出始めている。アベノミクスの特徴やこれまでの成果、そして今後の課題について、伊藤元重氏が大いに...
収録日:2014/09/08
追加日:2014/09/14
国家と国民のあり方を根本から問う「イスラム国」
三つの戦争と「イスラム国」―中東情勢における悲劇の本質
混迷を極める中東の戦い。その台風の目は「イスラム国(IS)」なる新興の過激派組織だ。過日、この組織により邦人男性が拘束された。今、中東を揺るがすISの動向と主張、国際情勢への影響を歴史家の山内昌之氏が平易に解説...
収録日:2014/08/20
追加日:2014/09/18
非国家的な世界主義者と非難された西田の思想とは?
過去から未来へ、京都学派の役割(3)ランケの考えと西田幾多郎の立場
「世界史的立場と日本」を世に問うた京都学派。その思想について考えるうえで、ドイツの歴史学者ランケと西田幾多郎の考え方、立場を押さえておきたい。彼らがそれぞれヨーロッパとアジア、そして日本という立ち位置からどんな...
収録日:2014/07/18
追加日:2014/09/20
安倍首相が掲げた「積極的平和主義」とは何か?
「積極的平和主義」とは何か(1)世界史と世界情勢
「積極的平和主義」とは、どんな意味なのだろう。それを知らずに、「良い・悪い」や「好き・嫌い」を表明しても始まらない。この言葉が生まれた背景を知るには、近現代の世界がたどった歴史と地政学的問題を、「一つながり」で...
収録日:2014/07/08
追加日:2014/09/22
次の目標は中東におけるアメリカ最大の同盟国
「イスラム国」米イラク空爆~六つの背景とシリア情勢への対応~(前編)
イスラム国に対する米軍のイラク空爆開始からはや1カ月、事態は長期化の様相も呈し、出口が見えない。米欧、特にアメリカが軍事攻撃に打って出た六つの背景と、シリア情勢への対応について、山内昌之氏が鋭く分析する。(前編)
収録日:2014/09/18
追加日:2014/09/24
アメリカの伝統的な「二重封じ込め」政策の再現
「イスラム国」米イラク空爆~六つの背景とシリア情勢への対応~(後編)
イスラム国に対する米軍のイラク空爆開始からはや1カ月、事態は長期化の様相も呈し、出口が見えない。米欧、特にアメリカが軍事攻撃に打って出た六つの背景と、シリア情勢への対応について、山内昌之氏が鋭く分析する。(後編)
収録日:2014/09/18
追加日:2014/09/25
江藤淳が調査した戦後日本の言論統制
「積極的平和主義」とは何か(3)戦後教育でゆがめられた日本人の危機意識
尖閣列島、もしくは日本周辺を世界が「今、最も危険な地域」と注目しているにもかかわらず、当の日本人の危機感はあまりにも薄い。なぜ、日本人の自国に対する安全保障意識はかくも低いのか? その根っこにある戦後体制に焦点...
収録日:2014/07/08
追加日:2014/10/07
「Gゼロ」時代で日本はどのように行動すべきか?
「積極的平和主義」とは何か(5)「Gゼロ」時代と日本の安保意識
世界は多極化と混迷化の「Gゼロ」時代を迎えた。不安定な世界情勢の中、日本はどのように行動すべきなのか。オバマ政権の対応が及ぼす世界への影響を手すりに、日本が採るべき道を考える。(島田塾第115回勉強会 島田晴雄...
収録日:2014/07/08
追加日:2014/10/12
イノベーションが生まれやすい都市のサイズがある
TOTOの北九州発グローバル戦略(3)北九州市から本社を移さない理由
TOTO株式会社は、今も北九州市に本社を置き、そこから本社を移さないと公言している。それはなぜなのか。東京一極集中の時代に不便ではないのか。同社取締役常務執行役員・成清雄一氏が語る北九州市のメリットとは。(全5話中第...
収録日:2014/09/18
追加日:2015/01/21
親切が第一! 初代社長の手紙に残る経営理念の原形
TOTOの北九州発グローバル戦略(4)TOTOを鍛えたカリフォルニア州の規制とコアバリュー
TOTOは、あることをきっかけにして、アメリカで有名になったという。これがターニングポイントとなって、今や海外で成功を収めている。それは何か。なぜだったのか。TOTO株式会社のコアバリューや先人の言葉と併せて、...
収録日:2014/09/18
追加日:2015/01/22
高齢化社会の水まわりという社会課題への挑戦
TOTOの北九州発グローバル戦略(5)「ブランドを買う」ことを目的にしない理由
グローバル化といっても、日本人は日本人。「グローバル人」のパスポートというものを見たことがない。それぞれの国の国民であるから世界にも行ける。だから「まず日本」。「ブランドを買う」ことを目的にはしない。TOTO株...
収録日:2014/09/18
追加日:2015/01/23
長州藩の財政的基盤を支えた「防長三白」
幕末長州~松下村塾と革命の志士たち(03)“実質”百万石、成功の要因
関ケ原の戦いで120万石から37万石に減封された長州藩が、天保の改革後、実質的に加賀の前田家に匹敵する大藩になっていたという。このことが、明治維新を理解する上で大事な点だと山内昌之氏は指摘する。鍵となるのは「防...
収録日:2014/12/15
追加日:2015/01/19
「ソリューション」を売ることが日本の産業界がとるべき道
「島田村塾」リベラルアーツ特講(2)武器としてのソリューション
グローバルな視野に立ちこれからの日本に必要な人材を育成すべく「島田村塾」を主宰している島田晴雄氏が、日本のビジネスの将来のために挙げるキーワードは「ソリューション」。ソリューションを武器に日本が世界市場でサバイ...
収録日:2014/12/05
追加日:2015/01/21
イスラム国掃討には2つの世界大戦より時間がかかる
イスラム国とクルド独立(1)イスラム国と世界のジレンマ
2014年は、イスラム国成立の年として歴史に刻まれるだろう。「それ以前の中東に戻ることは考えづらい」と歴史学者の山内昌之氏は言う。2015年、第二次世界大戦敗戦から70年を迎える日本は、イスラム国をどう見るべき...
収録日:2014/12/12
追加日:2015/01/21
イスラム、中国、インドの歴史を知らずにいるのは大問題
「島田村塾」リベラルアーツ特講(3)学校では教えない「イスラム」
「長い間、イスラム文明を学ぶ機会がなかった」と振り返る島田晴雄氏。イランについて調べるため、本を何十冊か読んでいるうちに、大きな発見をしたという。果たしてその発見とは? かつて世界を支配した偉大なイスラム文明に...
収録日:2014/12/05
追加日:2015/01/22
クルド人とイスラム国(ISIL)…対立の経過と意味
イスラム国とクルド独立(2)イスラム国vsクルド~中東の新たな対決構図
イラクとシリアで戦闘を繰り広げるイスラム国によって国際的な表舞台に登場したのが「クルド問題」だ。トルコ、シリア、イラク、イランに四散して虐げられ反目し合ってきたクルド人は、厳しい戦いを通じて自らの存在と勢力を世...
収録日:2014/12/12
追加日:2015/01/22
イスラム国がもたらしたクルド独立国家への道
イスラム国とクルド独立(3)イスラム国がもたらしたクルド独立国家への道
中東におけるイスラム国とクルド民族の対決は思わざる波及効果を引き起こしていると、山内昌之氏は見る。それは、クルド人の反目を解消させ、イラク軍の腐敗を露呈させ、欧米を中心とする国際世論を揺るがす勢いとなっている。...
収録日:2014/12/12
追加日:2015/01/23
海上自衛隊の活躍でソマリア沖の海賊被害は年々減少
安全保障最前線(1)戦略の視点で見るソマリア沖海賊対処活動
ソマリア沖の海賊行為に対する海上自衛隊の対処活動の成果は国際的にも評価が高く、近年海賊行為件数は減少している。それでも、海賊を根絶できないのはなぜなのか? 日本と世界の安全保障を見守り続けてきた吉田正紀氏が、平...
収録日:2014/08/01
追加日:2015/02/14
尖閣諸島問題で海上自衛隊が取っている対応とは?
安全保障最前線(3)中国の活発な海洋進出への対応(前編)
前海上自衛隊佐世保地方総監吉田正紀氏が語る、現場から見たわが国の安全保障最前線。今回は中国の海洋進出問題に焦点を当てる。アジア太平洋地域内のリスクとして、わが国の安全保障に影を落とす「尖閣問題」の経緯と実情から...
収録日:2014/08/01
追加日:2015/02/16
中国の海洋進出の目的を元海上自衛隊 海将が徹底解説
安全保障最前線(3)中国の活発な海洋進出への対応(後編)
前半では中国の海洋進出問題の現状を見たが、後半では解決への道を探っていく。中国の海洋進出の狙いを知り、日本の国際的な立場を分析していけば、進むべき道はおのずと浮かび上がってくるだろう。前海上自衛隊佐世保地方総監...
収録日:2014/08/01
追加日:2015/02/17
「21世紀はアジアの時代」をアンガス・マディソンが予測
近代のドラマ~民族国家と経済成長~
英国の経済学者、アンガス・マディソン博士は「21世紀は、アジアの時代」であることをいち早く予測した人物だった。しかし、この予測も、「民族国家」としての覇権争いが戦争という局面を迎えなければという話であることは言...
収録日:2014/10/28
追加日:2015/02/05
予算は半減したのに日本の開発援助に高い評価という皮肉
権力政治化する国際社会と国際協力(2)国際開発協力における日本の役割
現在、世界全体が権力政治を優位とする社会になっている。そんな中、国際協力における好材料として、環境と国際開発協力という二つの側面を提示した高橋一生氏。今回は、国際開発協力について、現在の世界状況を踏まえながら、...
収録日:2014/10/28
追加日:2015/02/10